絶縁抵抗測定のやり方完全マニュアル|安全・基準値・トラブル対策まで
初心者でも迷わない手順と安全確認、印加電圧の選び方、記録のコツまで。 現場でそのまま使えるチェックリスト付き。
「絶縁抵抗測定って難しそう」…
やり方がわからないまま放置していませんか?
電気設備を扱ううえで欠かせない作業なのに、専門的な言葉ばかりでつまずいてしまう人は少なくありません。
数値の見方や測定手順を誤ると、機器の故障や感電リスクにもつながるため、不安を抱えたままでは安心して作業できないのが本音でしょう。
そこで本記事では、初心者でも迷わず取り組めるように「絶縁抵抗測定のやり方」をステップごとに徹底解説します。
必要な準備から安全確認、測定後の記録方法まで一連の流れをわかりやすく紹介するので、初めての方でも安心して取り組める実践ガイドになっています。
- 初心者向けに手順をやさしく解説
- 安全確認と放電の必須ポイント
- 印加電圧の選び方を早見表で
- 対地間・線間の測り方と目安
- 記録術と要観察運用で再発防止
絶縁抵抗測定とは?初心者向けに目的とメリットを整理
電気を通さないはずの場所(被覆・筐体など)がどれだけ 電気を逃がしにくいかを、メガー(絶縁抵抗計)が一時的に直流高電圧をかけて測る試験。 表示はMΩ(メガオーム)などで、数値が大きいほど良好=漏電しにくい、という見方です。
- 感電・火災の予防:漏電の芽を数値で早期発見。
- 工事・点検品質の確認:施工ミス/汚れ・湿気の影響を可視化。
- 予防保全:定期測定で推移を追い、劣化兆候を把握。
主観ではなくMΩという客観指標で「今」の状態を説明できます。
最低ラインを決めれば、合否や要再点検を瞬時に判断できます。
台帳化していけば、湿気・経年などの傾向が見えて対策に直結します。
いつやる?(タイミング)
いつやる?(タイミング)
- 工事完了直後の検査(送電前)
- 定期点検(例:年1回/半年1回など現場基準)
- 漏電遮断器作動・異臭・発熱など異常時
- 長期停止設備の再始動前(モーター等)
どこを測る?(代表例)
- 分電盤:各分岐回路の端子−アース
- コンセント回路:L/N − アース
- モーター:各相端子 − 枠(アース)、必要に応じて相間
- 配線ケーブル:芯線 − シース(接地金属)
よくある誤解と注意ポイント
- 1 活線のまま測定は絶対NG。必ず停電・検電・表示で保護。
- 2 インバータや精密機器を接続したままの印加は故障リスク。切り離しが基本。
- 3 「∞=常にOK」ではない。過去記録と比べ急低下がないかも確認。
- 4 モーター相間はY/Δ結線で読みが変わる。構造を把握してから評価。
しきい値(最低ライン)の考え方: 低圧回路では一般に対地電圧区分ごとの最低抵抗値(例:0.1MΩ / 0.2MΩ / 0.4MΩ)が目安として使われます。 ただし正式判断は所属組織の基準・最新規程に従ってください。
- 安全前提(停電・検電・周知)とゼロチェックのコツ
- 対地間→線間の実践フローと読み取り
- 分電盤・コンセント・モーター・長尺ケーブルのケース別手順
- 0MΩ/無限大(OL)の切り分け・記録・復旧
- リードは塗装面を避けて金属地肌に挟む
- 充電電流が落ち着くまで数秒待って読み取る
- インバータ類は必ず切り離し、機器保護を最優先
絶縁抵抗測定の基本をわかりやすく理解する
⚡ 絶縁抵抗測定のやり方を始める前の安全チェック
絶縁抵抗測定は「感電」と「機器破損」のリスクが常につきまといます。初心者が安心して作業を行うには、測定を始める前の安全準備が何よりも大切です。 ここでは、必ず守るべき停電処置や保護具の装着方法を、現場で実践できるレベルまで具体的に整理しました。
🛑 ブレーカーOFF・検電・表示札の基本手順
測定前の「停電処置」は感電防止の最重要ステップです。以下の3ステップを必ず順番通りに実施してください。
- ブレーカーOFF:対象回路の分岐ブレーカーを落とし、できれば主幹もOFFにする。
- 検電:必ず検電器で「電気が来ていない」ことを確認。検電器自体の動作確認(自己確認)も忘れずに。
- 表示札・施錠:「作業中・投入禁止」の表示札をかけ、誤操作防止のためにブレーカーハンドルに施錠(ロックアウト)が望ましい。
🦺 感電・短絡を防ぐ身につける保護具
安全対策は「二重・三重の防御」が鉄則です。作業対象や環境に合わせ、最低限以下の保護具を使用しましょう。
感電を防ぐ基本装備。サイズが合ったものを使用し、破れや劣化がないか確認。
湿気や漏電時に体へ電流が流れるのを防止。ゴム底タイプが一般的。
火花や破片が目に入るのを防ぐ。特に配電盤作業では必須。
現場条件によって追加。アークフラッシュリスクのある盤では防炎服が推奨。
📟 絶縁抵抗計(メガー)の基本と使い方の流れ
絶縁抵抗測定の中心となる道具が絶縁抵抗計(メガー)です。メガーは回路や機器に直流の高電圧を一時的に印加し、 その時に流れるごく小さな電流から「抵抗値=漏れにくさ」を計算して表示します。使い方の流れを理解しておけば、 初心者でも安全に測定を進められます。
🔍 デジタルとアナログの違い/読み取り方
- 数値が液晶に直接表示されるため初心者でも分かりやすい。
- オートレンジ機能搭載機種も多く、測定レンジ切替の手間が少ない。
- 「OL(オーバーリミット)」=無限大に近い値を意味する表示がある。
- 針の動きで抵抗値を確認する。変化の「傾向」を掴みやすい。
- バッテリーが弱いと針の振れが不安定になる場合がある。
- 読み取りは目盛りを正面から見る必要がある。
🎛️ ゼロチェック(リード・接地の確認)のやり方
測定を始める前に必ず行うのがゼロチェックです。測定リードの接触不良や内部故障を見抜くための 事前自己診断であり、これを怠ると誤測定や危険につながります。
- リード棒同士をしっかり接触させる。
- 表示値が0MΩ(またはそれに近い値)を示すか確認。
- 反応がない/数値が大きい場合はリードの断線や接触不良を疑う。
❗ 0MΩにならないときの原因と対処
- リード線の劣化・断線:→ 予備リードと交換して再確認。
- 接触部の酸化・汚れ:→ 端子を磨き、金属部分にしっかり当てる。
- メガー内部不良:→ 他の測定器で代替確認し、必要なら修理。
※現場では「0に近い値=正しく短絡状態を確認できている」と判断します。 少しでも値が高い場合、測定前に必ず原因を突き止めましょう。
⚙️ 印加電圧の選び方:100V・200V・400Vでどう変わる?
絶縁抵抗測定の印加電圧は、基本的に回路の使用電圧に見合う値を選ぶのが鉄則です。 現場ではおおむね次のような目安が使われます(代表例)。
※以下は一般的な実務目安です。最終判断は所属組織の基準・最新版の規程に従ってください。
- 回路の使用電圧を確認(100/200/400Vなど)
- 配線のみ(負荷未接続)なら→おおむね 125V/250V/500V を目安に選定
- 負荷(電子機器・インバータ・計装)が接続されたまま? → 切り離す or レンジを下げる
- 湿気・長尺ケーブルなどで初期電流が大きい? → 数秒待って安定値を読む
- 測定後は自動/手動放電を確実に(感電防止)
🧯 機器がつながる回路で電圧を下げる判断基準
メガーは直流の高い電圧を一時的にかけるため、電子機器がつながった状態での印加は故障リスクがあります。 以下の項目に一つでも当てはまる場合は、原則:機器を切り離す、それが難しいときは印加電圧を下げることを検討します。
半導体素子・EMIフィルタ・サージ素子が直流印加に弱い。必ず切り離しが第一選択。
内部に整流・コンデンサ・サージ吸収(MOV)あり。低レンジ(100〜125V)運用や代替試験を検討。
コンセント機器が多い場合は抜けるものは抜く。抜けない場合は低レンジ+短時間印加。
内部回路が繊細。印加は最小限にし、可能なら配線単独で測定。
- 漏れ電流計(クランプ)で常時の漏れ傾向を確認する。
- 短時間印加+低レンジで安全側に評価する。
- 可能な区間だけ配線単独化して部分的に測定する。
🚫 高すぎる印加電圧のリスクと回避策
SMPSやインバータの素子が直流高圧で破壊される可能性。サージ吸収素子(MOV)が発熱・劣化する場合も。
EMIフィルタや安定器がアースへ電流経路を作り、絶縁低下と誤解する恐れ。
不要に高電圧をかけるほど残留電荷が増え、放電忘れによる微小ショックや誤接触リスクが上昇。
- 機器を切り離す(インバータ・UPS・SMPS・照明電源)。
- 回路電圧に合わせて125/250/500Vを基準に、必要時は低レンジへ。
- 長尺・湿潤・高静電容量の回路は、数秒待ってから値を読む(初期充電電流の影響を避ける)。
- 印加は短時間、終了後は自動/手動で放電する。
- 判定は合否ライン+過去推移の両方を見る(急低下は要調査)。
📝 環境要因も印加電圧選定に影響。湿度が高い・結露の疑い・粉じん多めの現場では、低レンジ+短時間印加で様子を見つつ、 清掃・乾燥後の再測定で安定値を確認すると安全です。
🔌 線間と対地間の違い:どちらを測る?どう使い分ける?
絶縁抵抗測定には「線間」と「対地間」の2種類があります。 それぞれ目的が異なり、使い分けを理解することが安全確保と誤診断防止のカギです。 ここでは「漏電」か「短絡」かという視点から、初心者でもわかりやすく整理しました。
🟢 対地間測定の狙い(漏電チェック)
対地間測定は、電線(活線または中性線)と大地(アース)の間の絶縁状態を調べるものです。 主な目的は漏電の有無を確認することにあります。
- 配線の被覆劣化や湿気による漏電を早期に発見できる。
- アースに電流が逃げているかどうかを確認するため、感電事故や火災防止につながる。
- 住宅・工場・オフィスなど、日常の点検で最も多く行われる測定方法。
🟡 線間測定の狙い(短絡・誤配線チェック)
線間測定は、活線と活線(または活線と中性線)の間で絶縁が確保されているかを確認します。 短絡事故や誤配線を見抜くのが大きな狙いです。
- 本来つながってはいけない線間に導通がないかをチェックできる。
- 新設配線や改修工事後に必須の確認項目。
- 誤配線をそのまま通電するとブレーカー遮断や火災につながるため重要。
🔄 測定順序のおすすめ(対地間→必要に応じて線間)
実務では、まず対地間を測定して漏電の有無を確認し、その後で必要に応じて線間測定を行うのが基本です。
📏 絶縁抵抗の基準値と正常値の目安をやさしく解説
絶縁抵抗の数値は「最低限クリアすべきライン」と「実務上、安心といえる目安」の2つで考えるとスッキリします。 まず最低ラインの意味を整理し、その上で現場感覚の“健康域”を具体的に示します。
🟢 0.1MΩ・0.2MΩ・0.4MΩ「最低ライン」の意味
回路の対地電圧に応じて「これ以下はNG」という最低抵抗値が定められているのが一般的です。 代表的には0.1MΩ / 0.2MΩ / 0.4MΩの区分が使われます。
直感的にはオームの法則で説明できます。100Vで0.1MΩだと電流は 約1mA(=100V/100kΩ)です。同様に200V/0.2MΩ、400V/0.4MΩでも約1mA。 人体・設備の安全を考慮した漏れ電流の上限目安との整合が取れるため、と考えられます。
これらは最低ライン=合否境界の考え方で、ここをギリギリ通過しても 実務的に「安心」とは言い切れません。余裕(マージン)を持つことが重要です。
🔵 現場感覚の正常値:数MΩ〜∞が安心な理由
最低ラインぎりぎりは偶発要因(湿気・汚れ)で簡単に下振れします。数MΩ以上あれば、日々の変動に対してクッションが効きます。
記録を重ねて推移を見ると、10MΩ→5MΩのような低下傾向を把握できます。基準合格でも減少が速ければ要点検です。
EMIフィルタやコンデンサで若干の漏れ経路が生じても、高い絶縁なら合否に影響しにくいのが利点です。
100MΩ以上〜∞が多い。塵・湿気がなければほぼ振り切り(OL)でも自然です。
数MΩ〜数十MΩが現実的。EMIフィルタ等で対地に経路があり、配線単独より下がりがち。
数十MΩ〜数百MΩが目安。長期停止直後は湿気で下がることがあり、乾燥後の再測で回復するケースも。
1〜5MΩ付近まで落ちることも。合否は満たしても、推移低下や局所的な傷・汚れを疑い要点検。
- 合否は最低ラインで判定、運用可否は余裕度(数MΩ以上)も併せて見る。
- 前回値との比較で劣化傾向を把握(∞→50MΩ→20MΩ…は要原因調査)。
- 季節・環境を記録(温湿度・天候・清掃有無)し、データに文脈を持たせる。
⚡ 測定結果が0MΩ・無限大のとき:意味と次の一手
絶縁抵抗測定では「0MΩ」と「無限大(OL)」という極端な値が表示されることがあります。 この2つは意味がまったく異なるため、正しい切り分けと記録方法を理解することが重要です。 ここでは初心者でも迷わないように、実務的な判断ステップを整理しました。
🟥 0MΩ(ほぼ導通)の原因切り分け手順
0MΩは「ほぼ短絡=絶縁不良」を意味します。測定対象が大地や別の線と完全に導通している可能性があるため、 すぐに対処が必要です。以下のステップで原因を切り分けましょう。
- まず測定器を疑う:リードをショートさせ、正常に0MΩ表示されるか確認。
- 回路の切り分け:ブレーカー単位で対象を切り離し、どの区間で0MΩかを特定。
- 湿気や結露をチェック:屋外盤や長期停止設備では水分で0MΩになる場合あり。
- 配線損傷を疑う:圧迫、被覆割れ、ネズミによる齧り跡などを点検。
- 機器内部の短絡:モーター巻線や電子機器がショートしているケースも。
0MΩを放置すると感電や火災のリスク大。原因が特定できるまでは通電禁止です。
雨の日だけ0MΩ近くに落ちる → 湿気要因。乾燥後に回復するなら恒常的な故障ではない可能性もあります。
🟦 無限大(OL)の解釈と記録のコツ
無限大(またはOL表示)は「測定器のレンジ上限を超える=非常に高い絶縁状態」を意味します。 新設配線や乾燥した良好な環境では自然な結果です。ただし記録・評価の仕方には注意点があります。
- 「異常ではない」:むしろ健全と考えてよい。
- 記録は「OL」や「∞」ではなく「≧(上限値)」とするのが推奨。
- 例:500VレンジでOL → 「≧1000MΩ」と表記。
- 次回比較のため、測定条件(湿度・温度・機器状態)を一緒に記録しておく。
「OL」とだけ書くと次回比較ができません。
「≧1000MΩ(500Vレンジ)」のように条件つきで残しましょう。
OL表示=「測定できていない」と誤解されがちですが、良好すぎて測れないだけ。 新築配線や乾燥したモーターではよくあることです。
- 0MΩ → 導通の可能性 → 即原因調査・通電禁止
- ∞(OL) → 高い絶縁状態 → 問題なし・正しく記録
- どちらも「条件メモ」と一緒に残すことで、次回の比較・経年変化の確認に役立ちます。
⛔ 絶縁抵抗測定で「やってはいけないこと」リスト
絶縁抵抗測定は高い直流電圧を一時的にかける試験です。
ここで紹介するNG行為は、感電・機器破損・火災・誤判定に直結します。初心者ほど「やらない理由」を理解し、代替行動までセットで覚えましょう。
🟠 通電中に測る/精密機器をつないだまま測る
- 印加電圧と商用電源が重なり予期せぬ電位となる。
- 短絡・アーク発生・感電の危険が大きい。
- 測定値の信頼性が著しく低下。
- インバータ・SMPS・LED電源などの半導体・コンデンサ・MOVを損傷する恐れ。
- EMIフィルタにより対地経路が形成され、低値に誤って見える。
- 停電・検電・表示札・施錠の4点セットを実施。
- 機器は原則切り離し。難しい場合は低レンジ(100〜125V)+短時間印加+代替測定(漏れ電流計など)。
- 記録に測定条件(切離し有無・印加電圧・湿度・温度)を残す。
🔵 測定ボタンをロックしたまま離れる
印加中に第三者が接触・対象が動く・クリップが外れる等で事故リスクが急上昇。 さらに不要な長時間印加で機器劣化の可能性も。
- 印加は手元保持で必要最小限の時間に限定。
- 離れる場合は必ず解除し、放電→無電圧確認。
- 周囲に立入禁止を明示(バリケード・表示札)。
🟣 放電を忘れる・周知せずに開始する
- ケーブル・コンデンサに残留電荷が溜まり、微小感電や部品劣化を招く。
- 次作業者が無防備に触れて事故になる恐れ。
- 第三者によるブレーカー投入・接触で事故。
- 工程の重複で誤操作・誤測定が発生。
- 印加終了 → 自動放電確認 → 必要に応じて手動短絡放電。
- 検電で無電圧を再確認。
- 周知・掲示:「作業中」「投入禁止」の表示札、必要に応じて施錠(ロックアウト)。
- 作業エリアはバリケードで境界設定、立会者の配置を検討。
- 作業後は復旧・原状回復(ブレーカー位置・表示札撤去・工具回収)。
🌍 アースがない場合の絶縁抵抗測定のやり方
絶縁抵抗測定は本来、接地(アース)が確保された状態で行うことが前提です。
しかし現場では「アース端子がない」「仮設現場で接地が未整備」というケースも少なくありません。
その場合は代替アースの確保とゼロチェックが特に重要となります。ここでは一般的に行われる方法を整理します。
⚡ 代替アースの取り方(盤筐体・水道管・接地棒)
金属筐体は接地に結ばれているケースが多く、最も手軽な代替アース。ただし接地が不十分な場合は抵抗値が安定せず、正しい値が得られないこともあります。
古い建物では水道管が接地されている場合があり、臨時の接地ポイントとして利用されることがあります。ただし近年は樹脂管も多く、導通確認が必須です。
最も確実な方法。
銅製やメッキ鋼の接地棒を地中に打ち込み、クランプで計器のアース端子へ接続します。湿った地面が望ましく、乾燥地では水を撒くなど工夫が必要です。
🛡️ 仮設アース時のゼロチェックと注意点
仮設アースを使用する場合、必ずゼロチェック(短絡試験)を行います。
これはメガーのリードを短絡させて0MΩ表示になるかを確認する手順です。アース側が不安定だと「0にならない/値が揺れる」などの異常が出ます。
また仮設アースは抜け・接触不良・抵抗の大きさに注意が必要です。
- 接地棒は湿った土壌に十分に打ち込む(乾燥地なら散水)。
- 接続ケーブル・クランプは緩みがないか確認。
- ゼロチェックで0MΩ表示を確認できない場合は、接地再施工または別のアースを探す。
- 測定中にアースが外れると誤測定や感電リスクがあるため固定を徹底。
- 測定記録には「仮設アースを使用」と必ず明記。
恒久的には必ず正式な接地工事を行い、測定は正規アース経由で行うのが基本です。
⚙️ モーターの絶縁抵抗測定の基本ポイント
モーターは絶縁不良が起きやすい機器の代表例です。巻線や結線方式の違い、周辺機器(特にインバータ)との接続状態によって測定結果が大きく変わります。
ここでは初心者が見落としやすいポイントに絞って整理します。
🔌 インバータは必ず切り離す理由
インバータは内部に半導体素子(IGBT・ダイオード)やコンデンサが多数組み込まれています。そのまま絶縁抵抗測定を行うと、直流高電圧が素子に印加されて破損するリスクが高いです。
さらに、ノイズフィルタやサージ吸収素子によって測定値が低く見える誤判定も発生します。
- 測定は必ずモーター単体で行う(インバータ側は切り離し)。
- 切り離しが難しい場合は、メーカー推奨の低電圧レンジや専用診断機器を使用。
- 測定後は接続復旧忘れ防止のため、チェックリストに記録。
🧩 相端子-枠間を測る/相間測定の注意(Y/Δ結線)
各相端子(U/V/W)とモーター筐体(金属枠)の間を測定。
絶縁破壊・湿気侵入の有無を直接確認できる最重要測定です。
Y結線:中性点が内部で接続されているため、測定値が相互に影響することがあります。
Δ結線:相間が直結されているため、対枠間測定を優先し、相間測定は補助的に活用します。
🛠️ 低値時の乾燥・清掃など回復アクション
モーターは使用環境によって絶縁抵抗が一時的に低下する場合があります。特に湿気・汚れ・油分の付着が原因で、数MΩ未満に落ち込むケースが典型です。
永久的な故障ではなく、処置によって回復することも多いです。
- 乾燥処置:ヒータや絶縁乾燥炉で温風乾燥。
- 清掃:端子部のホコリ・油分を除去し、リーク経路を遮断。
- 再測定:処置後は必ず再測定し、値が安定するか確認。
- 限界値未満なら交換検討:0.2MΩ未満など基準を下回る場合は使用中止が原則。
定期的な測定と記録、メーカー推奨メンテナンスが不可欠です。
🌦️ 季節・湿気・汚れがメガー値に与える影響
絶縁抵抗(メガー値)は季節・湿度・汚れに大きく左右されます。特に梅雨・降雨直後・冷暖房の切替時は 一時的に値が下がることが珍しくありません。ここでは現場で再現性の高い傾向と、数値の読み違いを避けるための実践コツをまとめます。
環境依存低下の可能性を無視しない。乾燥・清掃・時間置きで再測して傾向を見る。
測定票に温度・湿度・天候・清掃有無を固定項目で記録。比較が一気に楽に。
長尺ケーブルは初期充電電流で一瞬低く出ることがある。数秒待って安定値を読む。
🧭 雨天・結露・粉じん環境での測定コツ
- 盤扉を開けたらまず目視で水滴・湿り気を確認。
- 可能なら温風乾燥・除湿(安全配慮)→時間を置いてから再測。
- 屋外配線はジョイント部を重点チェック(吸湿しやすい)。
- 記録に「雨天」「湿度高」を必ず明記し、次回比較に備える。
- 朝イチ・暖機直後は結露リスク大。可能なら時間帯をずらす。
- 盤内を軽く予熱(ヒータ・ドライヤー等を安全距離で)し、水膜を除去。
- 金属面の水分は拭き取り+自然乾燥→再測。
- 清掃→測定が基本。端子・碍子・ケーブル外装の汚れを除去。
- 油分は脱脂(適合クリーナー)でリーク膜を切る。
- 塩害地域は防塩対策(シール材・定期洗浄)をセット運用。
- 「常に低め」なら推移監視で劣化と環境要因を切り分ける。
- リードは塗装面を避け、金属地に確実に噛ませる。
- 初期充電電流が落ちるまで2〜5秒待って表示を読む。
- 測定条件(温度・湿度・天候・清掃の有無)を必ず記録。
- 低値が続くときは配線単独化や機器切離しで原因を分離。
🗂️ 記録とトレーサビリティ:数値の推移で劣化を見抜く
絶縁抵抗は一回の合否だけでは不十分。時系列の推移を残すことで、湿気・汚れ・経年劣化の「兆し」を早期に捉えられます。ここではトレーサビリティ(追跡可能性)を担保するための記録設計と、現場で使いやすい測定シートの型を提案します。
「10MΩ→7MΩ→4MΩ」のように連続して低下したら要調査。単発の低下は環境要因かも。
温度・湿度・天候・清掃の有無・切離し有無・印加電圧を記録。条件が同じときの比較が信頼できます。
写真・動画・配線図・作業指示書番号・校正証明のリンク/番号を紐づけると監査に強い。
📝 測定シートの作り方と最低限の記録項目
- 現場名/設備名・回路ID(例:盤名、回路番号)
- 測定日・時刻/担当者・立会者
- 図面番号・作業指示書番号
- 印加電圧(125/250/500V等)・印加時間(読取り時点)
- 温度・湿度・天候(雨/晴)・盤内清掃の有無
- 機器切離し有無(インバータ/SMPS等)、対地/線間の別
- 機種名・製造番号
- 校正日・有効期限(証明書ID)
- ゼロチェック結果(OK/NG、実施時刻)
- 読取り値(例:対地 L-PE:12.5MΩ(250V))
- レンジ上限時は「≧1000MΩ(500V)」のように表記
- 基準との差(最低ライン・社内基準)/合否・所見
- 清掃・乾燥・切離し追加などの実施内容
- 再測結果(値の回復/不変)・復旧確認
- 写真・動画・報告書へのリンク/ID
シートの版(v1.2等)と改訂履歴をフッターに記載。誰がいつ何を変えたか追えるように。
数値はMΩの数値部のみを別列に持ち、グラフ化しやすくする。
OLは「上限値(例:1000)」に換算し、注記に「≧」と記録。
写真は測定点が分かる構図(端子名・回路ラベルが写るように)。ファイル名に回路ID_日付を含める。
- 基準適合を確認(最低ラインクリア)。
- 前回比で±20〜30%超の変動は要注目(環境差を注記で補正)。
- 3点以上の連続低下で原因調査(湿気・汚れ・接続機器・損傷)。
- 対策後再測で回復可否を確認(回復しない→故障/交換検討)。
📝 初心者がつまずきやすいポイントQ&A(簡単用語集付き)
絶縁抵抗測定を学び始めると、専門用語の多さに戸惑う初心者は少なくありません。 ここでは、よく出てくる単語をやさしく言い換えながら、現場での誤解を解消するためのQ&Aをまとめました。 簡単な用語集として活用できるように整理しています。
Q. 「メガー」ってなに?
A. 絶縁抵抗計のことを現場では「メガー」と呼びます。
家電で言う「テスター」のような役割で、電線や機器の絶縁状態をチェックします。
Q. 「印加電圧」ってむずかしい…
A. 測定中に電線へかけるテスト用の電圧のこと。
「お試しで流す電気」と考えると分かりやすいです。
「メガー」「印加電圧」「対地間」をやさしく言い換え
- ✅ 対地間:電線と地面(アース)の間を測る → 「漏電チェック」
- ✅ 線間:電線どうしの間を測る → 「誤配線チェック」
- ✅ ゼロチェック:計器が正しくゼロを示すか確認する → 「体温計のリセット」
よくある誤解と正しい理解
❌ 「絶縁抵抗が高ければ高いほどOK、無限大なら完全安全」
→ 正しくは:機器によって適正値があり、無限大でも接触不良や測定ミスの可能性があります。
❌ 「0MΩは必ず危険」
→ 正しくは:測定方法のエラー(リード未接続など)で出る場合もあります。原因切り分けが必要です。
現場で使える絶縁抵抗測定のやり方:手順別解説

実際の現場では、分電盤・コンセント・モーターなど測定対象ごとに注意点が異なります。
ここでは具体的な絶縁抵抗測定のやり方を手順別に解説し、初心者がつまずきやすいポイントやトラブル時の対応方法も詳しくまとめました。作業の流れを理解しておけば、安心して現場で実践できるようになります。
🔄 共通ステップ:準備→停電→ゼロチェック→測定→放電→復旧
絶縁抵抗測定は、どの現場でも共通する基本ステップがあります。 「準備・停電・ゼロチェック・測定・放電・復旧」という流れを守ることで、測定ミスや事故を防げます。 特に初心者は、この一連の流れを「ルーティン化」することが大切です。
作業前チェックリスト(持ち物・周知・危険予知)
- ✅ 絶縁抵抗計(メガー)の動作確認とゼロチェック
- ✅ 絶縁用手袋・ゴム靴・保護メガネの準備
- ✅ 作業エリアの表示札(「停電中・作業中」)を掲示
- ✅ 関係者への周知(誤ってブレーカーを入れないように)
- ✅ 測定対象機器の接続状態を確認(精密機器は切り離す)
放電の確実なやり方(自動放電)
最近のデジタルメガーは測定終了後に自動放電機能を持っています。 測定ボタンを離すと数秒かけて残留電荷を放出する仕組み。 ただし、古い機種では機能がないため、次の「手動短絡」が必須です。
放電の確実なやり方(手動短絡)
測定後に測定リード同士を短絡させる方法。 絶縁用手袋を着用し、金属棒や接地されたワイヤで数秒接触させ、電荷を安全に逃がします。 この作業を忘れると、次の人が感電する危険が残ります。
🔑 ポイント:
1. 測定前に必ず「持ち物・周知・危険予知」を確認
2. 測定後は自動放電 or 手動短絡で残留電荷をゼロにする
3. 復旧前にブレーカー投入の合図を徹底する
⚡ 分電盤での絶縁抵抗測定のやり方(回路ごとに確実に)
分電盤は家庭や工場の「電気の心臓部」。 ここで絶縁抵抗を測る際には主幹ブレーカーを切って安全を確保し、分岐回路ごとに正しく測定する必要があります。 手順を整理しておくことで、誤測定や危険を未然に防げます。
主幹OFF・分岐ごとの測定順序とポイント
- 主幹ブレーカーをOFFにし、停電を確認
- 分岐回路を1回路ずつONにして測定(他はOFFのまま)
- 測定が終わったらその回路を再びOFFにして次の回路へ
- 最後に全回路をONに戻し、主幹を復旧
🔑 ポイント:回路をまとめて測定すると「どこに異常があるか分からない」ため、必ず1回路ずつ。
対地間/線間の使い分けと値の目安
| 測定対象 | 目的 | 基準値の目安 |
|---|---|---|
| 対地間(線→アース) | 漏電の有無を確認 | 0.1MΩ以上(低圧回路) |
| 線間(線→線) | 短絡・誤配線チェック | 数MΩ以上が望ましい |
💡 正常な設備では「数MΩ~∞」が一般的。最低基準をクリアしていても、極端に低い場合は早めの点検が安心です。
異常値が出たら:ブレーカー単位の切り分け手順
- 🚨 分岐をすべてOFF → 主幹ON → 1回路ずつ測定し直す
- 🚨 異常値が出る回路を特定 → そのブレーカーをOFFのままにする
- 🚨 機器がつながっていれば切り離し → 回路単独で再測定
- 🚨 それでも低値なら → 絶縁劣化・配線損傷の可能性あり
👉 この「切り分け作業」を丁寧に行うことで、原因が機器側か配線側かをはっきりさせられます。
🔌 コンセント回路の絶縁抵抗測定のやり方(100V系)
コンセント回路(100V系)は、L(ライブ)・N(中性線)・PE(アース)の取り扱いを間違えやすい現場です。家電やテーブルタップが刺さったままだと誤判定・機器破損を招くため、測定前の切り離しと周知が重要です。
ここでは分岐ごと/口ごとに安全・確実に測れる手順をまとめます。
- 主幹OFF→対象分岐のみON→検電で無電圧確認(極性確認にもテスター併用)
- プラグ・テーブルタップ・家電を全て抜く(見落としがちな充電器・隠しコンセントも)
- メガーのレンジは原則125Vまたは250V(回路構成に応じて低レンジ優先)
- L-PE/N-PE(対地間)を測定 → 必要に応じてL-N(線間)を補助評価
- 数秒待って安定値を読む → 放電→測定票に条件と値を記録
- 口ごとに繰り返し → 最後に原状復旧(周知・表示札撤去・ブレーカー復帰)
L-アース/N-アースの測り方と注意
- 狙い:漏電の有無を確認(最重要)。
- 手順:メガー+側をL側スロット、−側をアース端子またはアース線へ。
- 注意:塗装面はNG。金属地に確実に噛ませる。
- 目安:正常なら数MΩ〜∞。最低ラインぎりぎり(0.1MΩなど)は再点検。
- 狙い:Nの誤接地・誤結線の検出。
- 手順:メガー+側をN側スロット、−側をアースへ。
- 注意:分電盤側の結線やN-PE結合の有無により値が影響。疑わしい場合は盤側で切り分け。
- 目安:正常なら高値(数MΩ以上)。極端に低い場合はNの誤接地や器具影響を疑う。
💡 極性の目視だけに頼らない。建物によってはL/Nが入れ替わっている例も。
測定前にテスターでL側(狭いスロット)に電位が無いこと、主幹OFF後の無電圧を必ず確認してください。
テーブルタップ・家電が刺さったままのNG例
内部のランプ・ノイズフィルタが対地経路を作り、低値に見える偽信号が出やすい。必ず抜く。
スイッチング電源・MOV・コンデンサが直流印加に弱い。故障リスク+誤判定。
内部電子回路が印加電圧で誤作動・破損の可能性。切り離し必須。
🔎 どうしても抜けない場合:分岐の他機器を全て外し、低レンジ(100〜125V)+短時間印加で安全側評価。代替として漏れ電流計で常時漏れを測定し、異常傾向の有無を確認。
- 対地間(L-PE/N-PE):通常は数MΩ〜∞。最低ラインぎりぎりは再点検。
- 線間(L-N):補助評価。異常に低い場合は誤配線・機器影響を疑う。
- 雨天・湿気・汚れで一時的に低下あり → 乾燥・清掃後に再測が鉄則。
💡 照明回路の絶縁抵抗測定のやり方(器具がある場合)
照明回路の絶縁抵抗測定は、コンセント回路や動力回路に比べて少し工夫が必要です。 理由は、照明器具自体に電子部品や安定器が組み込まれているケースが多いからです。 これらを無視して測定すると、誤った低値が出たり、器具を壊してしまう恐れがあります。
🔎 安定器・LED電源付き照明
蛍光灯やLED照明は内部に安定器や電源回路を含んでいます。 これを接続したまま測ると、内部回路が電圧を吸収して低抵抗を示すことがあるため、可能なら取り外し、もしくは片側配線を外すのが望ましいです。
⚠️ センサー付き照明
人感センサーや調光機能が組み込まれた器具では、内部電子回路に直接テスト電圧をかけると誤作動や故障を招きます。 測定前に必ず仕様書を確認し、必要に応じて器具を切り離す判断が必要です。
🔄 測定の流れ(器具がある場合):
1. 主幹ブレーカーをOFFにする
2. 照明回路を1回路だけONにする
3. 器具を外せない場合は対地間測定のみを行う
4. 線間測定は省略または回路切り離し後に実施
5. 測定後は必ず放電し、回路を復旧する
🚨 注意:照明回路は「電子部品の影響」で抵抗値が低く出ることがあります。 0.1MΩを下回らなくても、普段の記録値より低いときは湿気や器具劣化を疑うのが安全です。
🔧 モーター回路の絶縁抵抗測定のやり方(実践編)
モーター回路の絶縁抵抗測定は、負荷設備の中でも特に注意が必要です。 インバータや制御機器に直結しているケースが多く、誤ってそのまま測定すると電子回路を破損する恐れがあります。 そのため、事前に端子台での切り離し・ラベリングを行い、正しく500Vレンジで測定することが実務の基本です。
端子台での切り離し・名称ラベリングのコツ
- 🔌 測定前にインバータや制御盤との接続ケーブルを必ず外す。
- 📋 外したリード線には番号タグやマスキングテープでラベリングし、復旧時に迷わないようにする。
- ⚠️ U/V/Wの相順が入れ替わると逆転運転につながるため、結線順序はメモを残しておく。
- 🛠 測定対象は各相-枠間(対地間)と相間(U-V、V-W、W-U)を実施。
- 💡 Y結線では中性点、Δ結線では相間が特に重要。測定レンジ選択を誤らない。
500Vレンジの目安値と低下時の再測タイミング
モーター回路は低圧であっても500V印加レンジで測定するのが原則です。 絶縁抵抗値は以下を参考にすると分かりやすいです。
| 状態 | 目安値(500Vレンジ) | 対応の目安 |
|---|---|---|
| 正常 | 数MΩ~∞ | 記録して問題なし |
| 注意 | 0.5~1MΩ程度 | 湿気・汚れを疑い、乾燥後に再測 |
| 要対応 | 0.5MΩ未満 | 絶縁劣化や巻線損傷の可能性 → 点検・修理 |
💡 測定値が低い場合はすぐに「劣化」と決めつけず、乾燥・清掃・端子締め直し後に再測定するのが基本。 季節要因(梅雨時期や降雨直後)は数日後に回復することもあります。
⚙️ 配電盤・動力盤の絶縁抵抗測定のやり方(三相200/400V)
三相200Vや400Vの動力盤は、コンセントや単相100V回路と比べて回路規模が大きく、多くの機器が接続されているのが特徴です。 計器・リレー・インバータ・制御回路が混在しているため、誤って印加電圧をかけると高額機器を破損しかねません。
ここでは機器保護のための切り離し手順と、盤内の清掃や環境が測定値に与える影響について整理します。
計器・リレー・インバータ類の保護手順
- 🔌 インバータ・サーボアンプ:必ず入出力線を切り離す。直流回路や素子が高電圧に弱いため。
- 📟 計器(電流計・電圧計)やリレー:端子台で一旦外すか、測定回路から除外する。
- 🛡️ 制御回路(PLC・制御電源):機器ごとにブレーカーをOFFにし、二次側を外すのが安全。
- 💡 手順の工夫:「モーター系」「制御系」「計器系」とブロックごとに分けて測定すると復旧が容易。
盤内清掃と測定値の関係(汚れ・湿気)
動力盤・配電盤は粉じん・湿気・結露が溜まりやすく、これが絶縁抵抗値の低下要因になります。 とくに梅雨時や降雨直後は一時的に抵抗値が下がることが多く、乾燥や清掃後に再測することで正常値に戻るケースも少なくありません。
| 環境要因 | 影響 | 対応策 |
|---|---|---|
| 粉じん・ほこり | 湿気を吸い、リークパスとなる | ブロー清掃+ブラシで除去 |
| 湿気・結露 | 抵抗値が数MΩ→0.5MΩ台まで低下する例も | 送風・乾燥後に再測定 |
| 油・グリース汚れ | 表面リークや誤接触の原因 | 専用クリーナーで拭き取り |
💡 盤内を定期的に清掃するだけで測定値の安定化・誤報防止につながります。 測定値が「基準ぎりぎり」の場合はまず環境要因を疑いましょう。
📡 ケーブル・長尺配線の絶縁抵抗測定のやり方
長尺のケーブルや幹線配線は、絶縁抵抗測定の際にケーブル自体が持つ容量(静電容量)の影響を受けやすい特徴があります。 そのため、通常の短い回路と同じように測定すると抵抗値が一時的に低く出ることがあります。
ここでは、ケーブル長さ特有の「読み取りテクニック」と、端末処理や絶縁回復の工夫を整理します。
充電電流の影響と「数秒待つ」読み取りテク
長尺ケーブルは静電容量が大きいため、印加電圧をかけた直後は充電電流が流れます。 この時にすぐ読み取ると抵抗が低く見え、誤って「絶縁不良」と判断することがあります。
- 🔌 測定ボタンを押した直後は値が動く → 数秒〜十数秒待って安定値を確認する
- 📊 測定値がじわじわ上がるのは正常 → ケーブル容量が充電されているサイン
- ⚠️ 一定時間待っても上がらない場合 → 本当に絶縁が低下している可能性
端末開放・短絡・絶縁回復剤の使いどころ
ケーブルの両端や端子処理の状態によって、測定値が大きく変わる場合があります。 また、一時的に低下した絶縁抵抗を復活させる応急策も現場では使われています。
- 🔓 端末開放:末端の機器や負荷を必ず外し、ケーブル単独で測定する。
- 🔗 短絡保管:保管時は各相をまとめて短絡し、絶縁を均等に保つ方法が有効。
- 💧 湿気・結露:乾燥送風や絶縁回復スプレーを用い、再測定するのが実務的。
- 🛠️ 端子清掃:ほこり・油汚れの除去で値が数MΩ改善するケースもある。
⚡ 「絶縁不良はいくつオーム以上?」現場判断の実例
絶縁抵抗測定で「この値なら絶縁良好」「この値だと不良」と判断するのは、基準と現場感覚の両方が必要です。 電気設備技術基準では0.1MΩ〜0.4MΩが最低ラインと定められていますが、実際の保守・工事の現場では「最低限を超えている=安全」ではなく、さらに余裕を持った値が重視されます。
最低基準(0.1/0.2/0.4MΩ)と安全余裕の考え方
絶縁抵抗値の法的基準は電圧区分ごとに最低値が設定されています。 例えば、 ・100V回路 → 0.1MΩ以上 ・200V回路 → 0.2MΩ以上 ・400V回路 → 0.4MΩ以上 しかし、これは「これを下回れば違法」という基準であり、実務的にはもっと高い値が求められます。
経年劣化・湿気要因のときの再測・監視
ケーブルや機器は経年劣化や湿気・汚れで抵抗値が下がることがあります。 雨の日や結露時に低下しても、乾燥後に正常に戻るケースも多いため、一度の測定結果だけで「絶縁不良」とは断定できません。
- 📊 基準ギリギリの値が出た → 数時間後に再測定して傾向を見る
- 🌧️ 湿気環境 → 乾燥送風・清掃後に測り直しで改善する場合あり
- 📉 徐々に低下傾向 → 定期点検での記録比較により劣化を早期発見
🚨 「絶縁抵抗が0」と表示された時の対処のやり方
絶縁抵抗計で「0MΩ(導通状態)」が表示された場合、 これは絶縁不良の最も深刻なサインを意味します。 ただし原因は一つではなく、通電中の誤測定・短絡・内部機器の劣化など複数が考えられるため、 焦らず手順を踏んで切り分けることが大切です。
通電中誤測定/短絡の切り分けフローチャート
- 🔌 通電中でないか確認(ブレーカーOFF・検電)
- 📎 接続されている機器を外す(コンセント・安定器・インバータ等)
- 🔍 対象回路を分割 → 支線ごとに測定
- 📉 依然として0MΩなら短絡・断線の可能性大
- 🛠️ ケーブル・端子・機器を個別確認 → 焦げ跡・異臭・水分付着に注目
この手順を踏むことで「単なる誤測定」か「重大な短絡」かを見極めることができます。
どこまで分割して追う?実践的な分岐隔離手順
実際の現場では「どこまで細かく分割するか」が判断のポイントです。 分電盤→分岐ブレーカー→末端コンセント/機器という順で切り分け、最小単位まで追うことで原因箇所を確定できます。
- 🟢 分電盤単位で0MΩ → 幹線ケーブルや盤内部の問題の可能性
- 🟡 分岐ブレーカー単位で0MΩ → 特定回路のショートを疑う
- 🔴 末端機器を外すと回復 → 機器内部の絶縁不良が濃厚
✅ 「無限大(OL)」が出た時のやり方:確認・記録・復旧
絶縁抵抗計で「無限大(OL)」と表示された場合、 これは測定対象が十分に絶縁されていることを示しています。 ただし「安心だから終わり」ではなく、記録の残し方や復電時の安全確認を正しく行うことが、後々のトラブル防止につながります。
デジタル表示の読み方(>500MΩ等)と記録例
デジタルメガーの場合、数値が測定限界を超えると「OL」「∞」「>500MΩ」などと表示されます。 これは「非常に高い抵抗値=絶縁良好」を意味しますが、具体的な数値は不明となるため、記録には以下のように残すのが望ましいです。
- 📋 「500Vレンジ:>500MΩ」
- 📋 「200V回路:∞(OL表示)」
- 📋 「対地間測定:正常(限界値超過)」
直後の復電手順と最終安全確認
無限大の値が出た後はすぐに復電して良いわけではありません。 以下の手順を必ず踏むことで、残留電荷や誤動作を防ぎます。
- ⚡ 放電を必ず実施(自動放電付きメガー or 手動で短絡)
- 🔎 測定器を外す前に再度検電で無電圧を確認
- 🔄 盤や器具を復旧 → 配線・ブレーカーを元に戻す
- ✅ 最終安全確認(表示札を外す・周知)後に復電
⚡ 「印加電圧」の選び方のやり方:設備別の実践早見表
絶縁抵抗測定では、どの電圧レンジを使うかが正しい判定のカギです。 高すぎる電圧を印加すると精密機器を壊すリスクがあり、逆に低すぎると絶縁不良を見逃す可能性があります。 ここでは100V/200V/400Vの代表的な回路と、精密機器が混在するケースを想定した実践的な選び方をまとめます。
100V回路/200V回路/400V回路の推奨レンジ
| 回路電圧 | 推奨印加電圧 | 備考 |
|---|---|---|
| 100V回路 | DC 250V | 家庭用コンセント回路など。250Vレンジで測定するのが基本。 |
| 200V回路 | DC 500V | 動力盤やエアコン用。絶縁劣化を見逃さないため500Vレンジを使用。 |
| 400V回路 | DC 1000V | 高圧モーター・受電設備。1000Vレンジが基本だが、作業は有資格者限定。 |
精密機器・インバータ混在時の低レンジ運用
制御盤やオフィス配線では、精密機器やインバータが回路に接続されたままの場合があります。 これらは高い印加電圧をかけると破損・誤作動の恐れがあるため、以下の工夫が求められます。
- ⚠️ 機器はできる限り切り離して測定する
- 🔧 切り離し困難な場合は250Vレンジで測定し、参考値として扱う
- 📊 「低レンジで高抵抗値=安全」「低レンジで低下=要注意」と判断
🎯 「ゼロチェック」のやり方:確実に0MΩを出すコツ
絶縁抵抗測定を始める前に行うゼロチェックは、メガー本体とリード線の正常性を確認するための基本ステップです。 これを怠ると誤測定・見逃しにつながり、絶縁不良の発見が遅れるリスクがあります。 ここでは確実に「0MΩ」を出すためのポイントを整理します。
クリップ位置・塗装面回避・噛み込み確認
ゼロチェックはリード棒同士をショートさせた状態で「0MΩ」が出るかを確認します。 正しい手順を踏むには以下の点が重要です。
- 🔗 クリップは確実に金属同士を接触させる
- 🎨 塗装面や酸化皮膜は避け、導通が良い部分を選ぶ
- 🛠️ ワニ口クリップの噛み込み不足がないかチェック
リード不良・端子酸化の見抜き方
ゼロチェックで0MΩが出ない場合、メガー本体ではなくリード線や端子の不具合が原因のことが多いです。 以下の観点で確認すると、早期発見につながります。
- ⚡ リード線を曲げると抵抗値が変動する → 導体断線の兆候
- 🧪 プラグ・端子が黒ずみ・緑青している → 接触抵抗増加
- 🔄 別のリードに差し替えると0MΩになる → リード交換で解決
🌍 アースが取れない現場でのやり方:代替案と注意点
絶縁抵抗測定は正しい接地(アース)が前提ですが、 実際の現場では「近くにアース端子がない」「建設途中でまだ接地が引き込まれていない」といった状況も多くあります。 その場合は代替アースの取り方と誤った方法のリスクを理解して対応することが重要です。
盤筐体・金具・配管・仮設接地の優先順位
一時的にアースを取る場合は、以下の優先順位で検討します。 信頼性が高いものから順に選び、測定後は必ず復旧・安全確認を行うのが原則です。
- 📌 盤筐体や金属フレーム(確実に接地されている場合)
- 📎 建物の金属配管(接地工事済みか要確認)
- 🪛 仮設接地棒を打ち込み → 一時的にアースを確保
- 🚫 水道管を流用する場合は自治体や工事規則で禁止されていることも多いため要注意
中性線流用の是非とリスク理解
現場によっては「アースの代わりに中性線(N相)を使えるのでは?」という声があります。 しかし、これは原則として推奨されません。 中性線には微小電流が流れている場合があり、測定器や対象機器を壊す恐れがあります。
- ⚠️ 中性線は真の接地ではないため、測定誤差や誤判定の原因になる
- ⚡ 電流が流れている場合、メガー本体の故障や感電リスクが発生
- 📉 「一時的に代用できた」としても、正しい記録値が残せないためトレーサビリティが欠ける
🛠️ 初心者向けトラブルシュート:低値のよくある原因ベスト10
絶縁抵抗測定で「思ったより低い数値」が出ると不安になりますよね。 実は、すぐに機器故障や重大トラブルとは限らず、環境・接触・測定条件など多くの要因で一時的に低下することがあります。 ここでは初心者が現場で確認すべき原因ベスト10を整理しました。
- 💧 水濡れ・結露:雨天や湿気で値が下がる
- 🧹 汚れ・ほこり:端子や筐体の付着物がリーク経路に
- 🔌 機器が接続されたまま:LED電源やインバータが影響
- 🔩 ケーブル傷:被覆割れや摩耗で絶縁低下
- ⚡ 端子酸化:接触抵抗増加で不安定な測定
- 🛠️ リード線不良:内部断線やクリップ不良
- 🌡️ 高温環境:絶縁材の抵抗値が下がる
- 🪛 測定レンジミス:100V回路に500Vをかけ過ぎるなど
- 🧯 古い絶縁材:経年劣化で吸湿しやすい
- 📉 測定順序の誤り:対地間→線間の手順を守らない
水濡れ・結露・汚れ・ケーブル傷のチェック手順
- 🔎 ケーブル被覆を目視で点検 → ヒビ割れや擦れがないか確認
- 💧 配線盤・端子周辺を指でなぞって湿り気を確認
- 🧽 ほこりや汚れは乾いた布・エアブローで除去
- ⚠️ 水分が残る場合は送風乾燥やドライヤーを活用
乾燥・清掃・再測の正しい順番
「低値が出た=即故障」と決めつけず、段階的に改善アクションを取ることが大切です。
- 🧹 清掃:端子や盤内の汚れを除去
- 💨 乾燥:送風や時間経過で湿気を飛ばす
- 🔄 再測:条件を変えて再度測定し、値が改善するか確認
📑 記録・報告書のやり方:再発防止に効くドキュメント術
絶縁抵抗測定は「測って終わり」ではなく、どう記録し、どう報告するかが重要です。 正しく記録を残すことで、次回点検時に劣化の兆候を早期発見でき、トラブルの再発防止にもつながります。 ここでは現場で役立つドキュメント術を紹介します。
写真・回路図・数値推移のセット管理
数値だけを記録すると、後で「どこの回路だったのか」「どんな環境だったのか」が不明になりがちです。 再発防止のためには写真・回路図・数値の三点セットで記録するのが理想です。
- 📷 写真:測定位置・端子番号・湿気や汚れの状況を撮影
- 📜 回路図:測定箇所を図面にマークして残す
- 📊 数値推移:前回・今回の値を比較し、傾向を確認
合否だけにしない「要観察」運用
報告書を「合格/不合格」だけで終わらせると、軽度の劣化の見逃しにつながります。 そこで役立つのが「要観察」という評価区分です。
- ✅ 合格:基準値を十分上回り、問題なし
- ⚠️ 要観察:基準値はクリアしているが、前回より低下している
- ❌ 不合格:基準値未満で使用不可
✅ 現場で役立つチェックリスト付:絶縁抵抗測定のやり方総まとめ
ここまでのポイントを「持っていく→止める→測る→放電→記録→復旧」の流れで再整理。 初心者でも迷わないよう、3段階チェックと代替手段の判断をセットで掲載します。
作業前/測定中/測定後の3段階チェック
- 主幹OFF・検電・表示札/関係者周知
- メガーゼロチェック(0MΩ)・校正期限確認
- 印加電圧の選定(100V→250V/200V→500V/400V→1000V目安)
- 精密機器・インバータは切り離し or 低レンジ運用
- 写真・回路図・測定票を準備(温湿度記録欄あり)
- 対地間→必要に応じて線間(基本順序)
- 長尺配線は数秒待って安定値を読む
- 端子・クリップは塗装面回避/金属地に確実に噛ませる
- 異常値はその場で分岐隔離→機器切り離し→再測
- 「OL」表示はレンジ併記(例:500V:≥500MΩ)で記録
- 自動放電 or 手動短絡で確実に放電
- 配線・機器の原状復旧→相順・結線再確認
- 測定票に値/印加電圧/温湿度/切離し状況を記入
- 評価は「合格/要観察/不合格」の3区分
- 復電後、異音・異臭・発熱のモニタリング
代替手段(漏れ電流計・低電圧測定)の使いどころ
- 通電状態で常時漏れを監視できる(停止困難設備に有効)
- 回路ごとの比較で異常支線のあたり付けが可能
- 絶縁抵抗の代わりではなく補助指標として活用
- 精密機器・インバータ切り離し困難な時に使用
- まず125/250Vで確認→問題なしなら分割しつつ高レンジ再評価
- 低レンジで低値→機器影響 or 劣化の切り分けを先行
🧭 【まとめ】絶縁抵抗測定とやり方の要点チェックリスト
- 主幹OFF・検電・表示札・周知
- ゼロチェック(0MΩ)・校正期限OK
- 印加電圧は回路電圧×2〜5倍目安
- 精密機器・インバータは原則切り離し
- 対地間→必要に応じ線間の順
- 長尺は数秒待って安定値を読む
- 金属地へ確実にクリップ(塗装面回避)
- 「OL」はレンジ併記で記録
- 最低基準:0.1/0.2/0.4MΩ(電圧区分)
- 数MΩ〜∞が安心。基準ギリは「要観察」
- 低値時:清掃→乾燥→分割→再測の順
- 0MΩ表示:通電誤測定/短絡をフローで切り分け
- 写真・回路図・数値推移の三点セット
- 温度・湿度・天候・切離し有無を記録
- 評価は「合格/要観察/不合格」
- 復電後のモニタリング(音・臭い・温度)



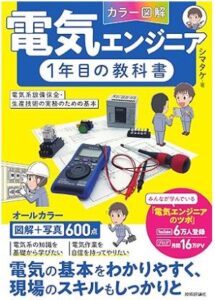
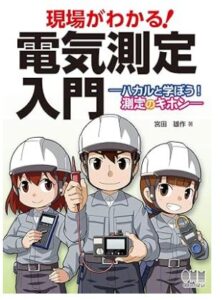
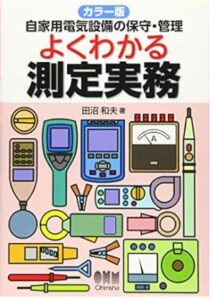


コメント