「絶縁抵抗測定って、試験でも現場でも本当に必要なの?」
――電気工事士を目指す人なら、一度はそんな疑問を抱いたことがあるはずです。
実はこの測定、配線の安全性を確認するうえで欠かせないだけでなく、試験でも毎年のように出題される“落とせない分野”です。
しかし、測定の仕組みや手順、数値の意味があやふやなままでは、筆記も実技も失点リスクが高まります。
「なぜブレーカーを落とすのか」
「なぜ負荷を外すのか」
など、つまずきやすいポイントも多数。
本記事では、絶縁抵抗測定と電気工事士試験の必須知識を、初心者でも理解できるよう徹底整理します。
これを読めば合格への道筋がはっきり見えてくるはずです。
記事のポイント
- 絶縁抵抗測定の基礎を理解
- メガーとレンジ選定の要点
- 対地間・線間の違いと手順
- 基準値0.1/0.2/0.4MΩを暗記
- 停電→検電→放電の安全手順
- 絶縁抵抗測定の基礎と電気工事士試験に出る重要ポイント
- 電気工事士試験で必ず出る!絶縁抵抗測定の攻略ポイントと実践テクニック
絶縁抵抗測定の基礎と電気工事士試験に出る重要ポイント

電気工事士を目指すうえで、「絶縁抵抗測定」は避けて通れない重要なテーマです。配線や機器が正常な絶縁状態を保っているかを確認するこの測定は、感電事故や漏電火災を防ぐための基本中の基本。試験でも頻出分野であり、原理から測定手順、安全確認まで幅広い知識が問われます。
ここでは、初心者でも理解しやすいように、絶縁抵抗測定の基本と試験で特に狙われやすいポイントを丁寧に整理していきます。
なぜ電気工事士にとって絶縁抵抗測定が必須なのか
絶縁抵抗測定の目的は、配線や機器が「電気を通してはいけない部分で電気を通していないか」を確かめること。 被覆の劣化・施工ミス・湿気や汚れによる沿面リークは、目視では気づきにくい代表例です。 測定で“数値”として可視化するから、事故の芽を事前に摘めます。
なお、国内の電気事故に占める絶縁不良の割合を特定する公的な最新統計は確認できません。 一般的には絶縁不良が主要因の一つであることは確かですが、 具体的割合の一次情報は現時点で信頼できる情報が見つかりません。 試験対策としては、「不良は見落とすと重大」という前提で、測定の必然性を理解しておくのが重要です。
⚠️ 測らないと何が起きる?主なリスク
- 被覆ダメージや湿気による漏電・感電を見逃す
- 微小リークでブレーカーの過感度動作や誤動作が増える
- 局所発熱からの発煙・火災リスクを高める
- 竣工検査で不合格→再工事→コスト増の悪循環
📝 試験で狙われる“理由と根拠”
電気工事士の筆記では、「なぜその手順が必要か」を問う設問が定番。 手順の丸暗記ではなく、根拠を理解しておくと失点しにくくなります。
- ブレーカーを落とす理由:メガーの高電圧が他回路・機器へ及ぶのを防ぎ、誤測定や機器破損を避ける。
- 線間測定で負荷を外す理由:負荷が並列経路となり抵抗値が低く出る/内部破損の恐れ。
- 基準値(0.1MΩ/0.2MΩ/0.4MΩ):対地電圧区分で最低値が決まり、漏れ電流を概ね1mA以下に抑える目安。
- レンジ選定の根拠:被測定回路の定格に合わせて印加電圧を設定(100V系は125/250V、低圧配電は500Vが通例 など)。
✅ 現場でも試験でも効く「最小セット」
- 測定前は停電・検電を徹底(ブレーカーOFF & 検電器)
- 線間測定では負荷(ランプ・家電・電子機器)を外す
- 回路に合わせてメガーのレンジを設定(低圧は500Vが標準的)
- 測定値は絶縁抵抗測定表に「○○MΩ以上」で記録(∞は使わない)
🚫 よくある誤解(試験でひっかけられる)
- 「通電状態でも測れる」→ 高電圧印加が機器破損の恐れ
- 「負荷があっても大丈夫」→ 測定値が低く出る/故障リスク
- 「∞は記録してOK」→ 公的様式では“最大値以上”の数値記載
絶縁抵抗測定の基本原理と「漏れ電流」を理解しよう
電気工事士試験だけでなく、現場でも頻出する用語に「漏れ電流」があります。 絶縁抵抗測定は、単なる「数字を測る作業」ではなく、この漏れ電流をオームの法則を使って見える化するためのものです。
ここでは、絶縁抵抗測定の基本メカニズムと、なぜ漏れ電流の考え方が重要なのかを、初心者にもわかるように整理していきます。
⚙️ 絶縁抵抗測定の基本原理:オームの法則がすべての基礎
絶縁抵抗計(メガー)は内部に高電圧直流電源(通常は125V・250V・500V・1000Vなど)を内蔵しており、 これを測定対象の回路に印加します。そして、その電圧によって絶縁物の表面や内部をわずかに流れる電流(=漏れ電流)を検出し、次の式で絶縁抵抗値を算出します:
例えば、500Vを印加したときに0.5mA(0.0005A)の漏れ電流が流れたとすると、絶縁抵抗は次のように求められます:
このように、絶縁抵抗の測定とは「漏れ電流を間接的に測っている」とも言えます。 値が大きいほど電流が流れにくく、絶縁状態が良好であることを意味します。逆に、抵抗値が低い場合は、絶縁劣化や施工不良の可能性が高くなります。
⚡ 「漏れ電流」とは何か?目に見えない危険信号
「漏れ電流」とは、本来絶縁されているべき電線や機器の外側を伝って流れる微弱な電流のことです。 絶縁材が劣化したり、表面に水分・ホコリ・油膜が付着すると、その経路を通って電流がわずかに漏れ出すことがあります。
📊 漏れ電流が引き起こす主なトラブル
- 微量でも人体が触れると感電事故につながる
- 分電盤の漏電遮断器が頻繁に作動する
- 機器内部での誤作動・電子機器の破損が起きる
- 長期的には熱劣化や火災のリスクも増大
特に、漏れ電流が1mAを超えると人体に感知できるレベルとなり、5mA前後になると危険域に入るとされています(※人体影響のしきい値については回路条件や接触時間によって異なります)。 電気工事士はこの「わずかな漏れ」を見逃さないために、絶縁抵抗測定で早期検知と予防を行うのです。
🔬 表面漏れ電流と体積漏れ電流の違いを知ろう
| 種類 | 発生要因 | 特徴・対策 |
|---|---|---|
| 表面漏れ電流 | 絶縁材の表面に付着した水分・塵埃・油膜 | 湿度や汚れで増加。清掃・乾燥・絶縁カバーが効果的。 |
| 体積漏れ電流 | 絶縁材内部の劣化・微細なクラック | 経年劣化や高温環境で増加。定期点検と交換が必要。 |
絶縁抵抗測定で検出される漏れ電流は、これら2種類の電流の合計です。 特に表面漏れは湿度や汚れといった環境要因で大きく変化するため、測定時のコンディション管理も重要なポイントになります。
💡 ポイントまとめ:絶縁抵抗測定は「漏れ電流を読む力」
絶縁抵抗測定の本質は、単なる数値チェックではなく、見えない漏れ電流を「数値」という言語で読み解くことです。 漏れ電流の正体と発生メカニズムを理解しておくと、数値の意味がより深くつかめ、試験問題の応用にも強くなります。 現場ではこの“読み解く力”こそが、安全で信頼性の高い施工につながります。
絶縁抵抗測定を行う前に必ず確認すべき安全手順
絶縁抵抗計(メガー)は直流の高電圧(125V/250V/500V/1000Vなど)を回路に印加します。 だからこそ、測定前の停電・切離し・確認・表示が命綱。ここを省くと、誤測定だけでなく機器破損や感電のリスクが一気に高まります。
以下では、試験・現場の両方で使える「ミスしない前準備」を、理由とセットで整理します。
✅ 最低限の個人防護具(PPE)
- 絶縁手袋・絶縁靴
- アイシールド/ヘルメット
- 検電器(非接触+接触式の併用が安全)
🧰 測定器の準備
- メガーのレンジ確認(回路電圧に適合)
- リードの被覆・ワニ口の摩耗点検
- ゼロ調整/バッテリー残量チェック
🚧 作業区画の可視化
- 立入禁止表示・バリケード
- 「試験中・送電禁止」の掲示
- 復電担当者の指名(ダブルチェック)
ブレーカーを落とす理由と通電中に測定してはいけない訳
絶縁抵抗測定では直流高電圧を回路に注入します。ブレーカーを落とさずに通電中で測ると、 メガーの高電圧が他回路や接続機器へ逆流し、電子機器や保護装置が故障する恐れがあります。
さらに、活線部が残ると誤って人体に電圧が印加される危険も。したがって「停電→検電→短絡・接地(必要時)」の順で確実に無電圧を確認します。
📌 具体的な手順(推奨)
- 対象回路の開閉器・遮断器をOFF、該当ブレーカーに復電禁止の札を掛ける
- 末端(コンセント・端子台等)で検電(L/Nともに無電圧)
- 必要に応じてキャパシタ等の残留電荷を放電(抵抗を介すかメーカー指定手順)
- メガーのレンジ・リード接続を確認し測定へ
| やること | 理由 |
|---|---|
| ブレーカーOFF・区画 | 高電圧の回り込み防止/他設備保護 |
| 検電(L/N/PE) | 無電圧の実確認。誤通電の排除 |
| 残留電荷の放電 | コンデンサ等に蓄電→感電・誤値防止 |
| 復電禁止表示 | 第三者の誤復電を防止(ロックアウト/タグアウト) |
線間絶縁抵抗測定で負荷を外す必要がある理由
L-NやU-Vなど線と線の間を測る「線間測定」では、ランプ・家電・電子機器・コンバータ・フィルタなどの負荷が 並列の導通経路となり、実際の絶縁よりも低い抵抗値を示します。
さらに、負荷内のコンデンサや半導体に直流高電圧がかかると、故障・発煙の恐れも。 よって線間測定は「全負荷外し」が原則です(プラグを抜く/照明はランプ取り外し)。
🧪 代表的な“低く出る”要因
- ランプ・ヒーター素子:フィラメント経由で導通
- ACアダプタ/スイッチング電源:入力フィルタのYコン等でリーク
- ノイズフィルタ・サージ吸収素子:RC/Varistorが直流を逃がす
- 電子安定器・インバータ:入力部に整流・容量性負荷あり
| やること(線間測定) | 理由 |
|---|---|
| 全てのプラグを抜く・機器を外す | 並列経路・内部素子で抵抗が下がるため |
| 照明はランプ取り外し | フィラメント経路で低値を示すのを防ぐ |
| 電子機器はタグ付け保管 | 紛失・誤復旧防止/復旧チェック容易 |
| 測定後は段階復旧(回路→機器) | 故障有無の切り分けがしやすい |
✅ 測定前チェックリスト(抜粋)
- 回路の停電・検電を確認した
- 線間測定の負荷はすべて取り外した
- レンジ設定は回路に適合している(低圧は500Vが一般的)
- 高容量回路は放電手順を事前確認
- 測定結果の記録様式(∞は「最大値以上」で記載)を準備
🚫 これをやるとアウト(試験でも減点)
- 活線のままメガーを接続(機器破損・感電の恐れ)
- 負荷を外さず線間測定(低値→誤判定)
- 復電禁止の表示なし(第三者の誤復電リスク)
- 放電抜け(火花・ショック・誤値)
メガーの選び方と測定レンジの考え方
絶縁抵抗計(メガー)は「印加電圧=レンジ」の選択がキモ。 回路電圧や接続機器の種類に合わないレンジを選ぶと、機器破損・誤測定の原因になります。
ここでは、試験でも現場でもそのまま使えるレンジ選定の考え方を、回路別の目安とともに整理します。
🔑 基本方針
- 被測定回路の定格(対地電圧)に見合う印加電圧を選ぶ
- 電子機器やフィルタ入り回路は指定試験電圧を最優先
- 迷ったら低いレンジから段階確認(保守的に開始)
📐 目安の捉え方
低圧配電(〜600V級)の一般配線は500Vレンジが標準的。 弱電・電子機器混在回路は125〜250Vレンジが無難。 高圧機器・特別高圧の絶縁診断は1kV以上が用いられることもあります(設備仕様に従う)。
⚠️ 情報の透明性
国内回路別の完全統一基準の一文は公表形態が多様で、現時点で単一の一次資料にまとめて示すことはできません。 以下の表は実務で一般的な目安であり、最終的には設備仕様書・メーカー指示に従ってください。
回路電圧ごとに選ぶ正しい測定電圧の目安
| 回路・用途 | 代表的な回路電圧 | 推奨メガーレンジ(印加電圧) | 補足・注意 |
|---|---|---|---|
| 住宅・小規模施設の一般配線 | 単相2線100V/単相3線100-200V | 500V(標準)、状況により250V | 電子機器が残る場合は250V以下から開始し、機器は可能な限り取り外す |
| 小形機器・制御盤の24V/48V系 | DC24V/DC48V | 125V(または50V/100Vクラスの低レンジ) | 半導体・コンデンサ多数。メーカー指定があれば厳守 |
| 三相動力・配電(低圧600V級) | 三相3線200V/低圧動力系 | 500V(一般的) | モータは端子開放で測定。大容量は放電手順を確認 |
| 通信・電話回路・弱電系 | 〜DC60V程度 | 50〜100V程度 | 機器側の絶縁仕様が低いことが多く、低レンジ必須 |
| 高圧機器の絶縁診断(専門) | 3.3kV/6.6kV等 | 1000V以上(1kV〜5kV級の絶縁抵抗計) | 法令・社内規程・メーカー手順に厳密に従う(試験範囲外のことも) |
125V・250V・500V・1000Vレンジの使い分け
🔹 125Vレンジ
弱電・低電圧制御や電子機器混在の予備確認に最適。 半導体・コンデンサを含む機器(PLC、SMPS、安定器等)に優しい。指定がなければ最初のスクリーニングとして有効。
🔹 250Vレンジ
100V/200V系の混在回路での無難な選択。 電子機器を外しにくい状況や、500Vでは過大ストレスが懸念される場合に用いる。
🟢 500Vレンジ
低圧配電(〜600V級)の標準。屋内配線・動力幹線など一般的な竣工・点検で広く使用。 ただし電子機器は取り外すか仕様確認の上で実施。
🟩 1000Vレンジ
高圧機器・特定設備の絶縁診断で使用(専門領域)。 電気工事士試験の範囲でも名称理解は必要だが、実施は手順書・資格要件に厳密に従う。
⚠️ よくある失敗(減点&事故のもと)
- 500V固定で何でも測る → 電子機器を破損させる
- 対地電圧を無視してレンジ選択 → 数値が過小/過大に出る
- 負荷を外さず線間測定 → 低値誤判定・フィルタ素子の損傷
- 放電忘れ → 火花・ショック・誤測定
🧭 実務フロー(安全寄り)
- 停電・検電・区画化(タグアウト)
- 電子機器・負荷の切離し(線間測定)
- 125V→250V→500Vの順で段階評価(仕様確認で省略可)
- 測定後は放電→復旧チェック→段階的に通電
- 記録は「○○MΩ以上」表記(∞は使わない)
🔬 絶縁抵抗測定の仕組みと内部構造のイメージ
絶縁抵抗測定の本質を理解するには、「なぜ電圧をかけると抵抗が測れるのか」「メガー内部はどう動いているのか」を知ることが欠かせません。試験では表面的な操作だけでなく、原理理解を問う設問も増えており、ここを押さえておくことで応用問題にも対応できるようになります。
ここでは、測定の基本原理から、オームの法則による仕組み、そして試験でもよく出題される「G端子(ガード端子)」を使った測定法まで、内部構造をイメージしながら解説していきます。
⚡ オームの法則で読み解く測定原理
絶縁抵抗測定は、「電圧(V)を印加し、流れる電流(I)を測定して抵抗値(R)を算出する」という、非常にシンプルな原理に基づいています。これは物理の基本式であるオームの法則(R = V ÷ I)そのものです。 絶縁が健全であれば流れる電流は非常に小さくなり、結果として抵抗値は高く表示されます。逆に絶縁不良があると電流が増え、抵抗値が低下します。
📊 具体例で理解する:
- 500V印加時に0.05mA(0.00005A)の電流 → R = 500 ÷ 0.00005 = 10MΩ
- 500V印加時に0.5mA(0.0005A)の電流 → R = 500 ÷ 0.0005 = 1MΩ
このように、同じ印加電圧でも流れる電流が大きくなるほど、絶縁状態が悪化していると判断できます。
測定器(メガー)の内部では、ハンドル式であれば発電機によって、電子式であればインバータ回路によって高電圧を発生させています。その電圧を回路に印加し、わずかに流れる漏れ電流を高感度で検出・換算して抵抗値として表示します。 実際の回路ではこの「漏れ電流」が感電や火災の原因となるため、測定は安全確認上欠かせない工程なのです。
🧪 G端子(ガード端子)を使った測定「G方式」とは
電気工事士試験でも頻出するのが、「G端子(ガード端子)」を用いた測定方式です。G方式とは、被測定物に付着した表面汚れや湿気による“表面リーク電流”を除去し、純粋な絶縁抵抗値だけを測定する手法です。 通常、絶縁抵抗は内部抵抗(R内部)と表面抵抗(R表面)が並列して存在し、表面経路があると実際の値より低く出てしまうことがあります。
📍 G方式の測定イメージ:
- 測定器の「LINE端子」と「EARTH端子」で通常の測定を行う。
- 表面経路が問題となる場合、G端子を表面部分に接続する。
- G端子が表面電流をバイパスし、内部抵抗のみを測定できる。
この方法は、湿度の高い現場や長期間使用された機器の測定などで特に有効です。G端子を活用すれば、より正確で信頼性の高い絶縁抵抗値が得られ、誤った判定を防ぐことができます。試験でも「G端子の役割」や「どのような場合に使うか」が選択肢としてよく出題されるため、仕組みと目的をしっかり押さえておきましょう。
📏 絶縁抵抗測定で出てくる数値の意味
絶縁抵抗測定で表示される「数値」は、単なる数字ではなく、電気設備の安全性を判断する非常に重要なサインです。数値の読み取り方次第で、「今すぐ修理が必要な危険な状態」か「正常で安全な状態」かが分かれます。
ここでは、試験や実務でよく出る「ゼロ」「無限大」といった特異な値の意味、そして合格・不合格を左右する基準値の考え方と覚え方を徹底的に整理します。
⚠️ ゼロ・無限大が示す異常と正常のサイン
絶縁抵抗測定では、通常「数MΩ〜数百MΩ」といった値が表示されますが、ときに「0Ω」や「∞(無限大)」という極端な値が出ることがあります。この2つは、試験でもよく問われる“特別なサイン”です。
🔎 状況別の読み取り方
| 測定値 | 意味 | 対処・解釈 |
|---|---|---|
| 0Ω(ゼロ) | ほぼ絶縁されていない(漏電・短絡状態) | すぐに原因調査と絶縁不良箇所の修理が必要 |
| ∞(無限大) | 完全に絶縁されており電流が流れない | 理想的な状態(ただし実務では数百MΩ程度が多い) |
ゼロは明確な異常サインであり、被覆破損・湿気浸入・接続ミスなどが疑われます。一方で無限大は「絶縁が非常に良好」な状態を示しますが、実務的には「∞に近い高抵抗(例えば100MΩ以上)」と表現されるケースが多く、必ずしも“無限”である必要はありません。
試験では「ゼロ=異常」「無限大=正常」と覚えておくだけでなく、その背後にある原因と対処法まで押さえると、応用問題にも強くなります。
📚 絶縁抵抗値の基準(0.1MΩ・0.2MΩ・0.4MΩ)の覚え方
絶縁抵抗測定では、法律(電気設備技術基準)で「これ以下なら危険」という明確な基準値が定められています。この数値は電圧区分によって異なり、試験でも頻出です。以下の表は暗記必須レベルなので、丸ごと覚えておきましょう。
| 回路の種類 | 測定電圧 | 絶縁抵抗の最低値 |
|---|---|---|
| 300V以下の低圧回路 | 500V | 0.1MΩ以上 |
| 300Vを超える低圧回路 | 500V | 0.2MΩ以上 |
| 高圧・特別高圧回路 | 1000V | 0.4MΩ以上 |
💡 語呂で覚える裏ワザ
- 0.1MΩ:「低圧なら 一安心」
- 0.2MΩ:「高めの低圧は 二重チェック」
- 0.4MΩ:「高圧には 四段階の安全」
語呂と用途をセットで覚えておくと、本番で一瞬で引き出せるようになります。
注意点として、これらは「最低限守るべき法的基準」であり、実務ではこの値を大きく上回っているのが一般的です。特に新設工事では数十MΩ〜数百MΩが普通で、逆にこの基準ギリギリしか出ない場合は、湿気や経年劣化、ケーブル損傷などの可能性を疑うべきです。
🔌 コンセントや照明回路での測定手順を具体的に解説
電気工事士試験や現場作業で最もよく登場するのが「コンセント」や「照明器具」などの末端機器の絶縁抵抗測定です。
ここでは、基本的な測定の流れを具体的な手順で整理するとともに、「対地間」と「線間」という2つの測定の違いや、実務上つまずきやすい注意点を徹底解説します。単なる操作手順だけでなく、“なぜその確認が必要なのか”まで理解しておくことが、試験合格と安全作業の鍵となります。
⚖️ 対地間測定と線間測定の違い
絶縁抵抗測定では、測定対象とする「電線の組み合わせ」によって2種類の測定が行われます。それが「対地間測定」と「線間測定」です。試験ではこの違いと目的がよく問われるため、明確に区別して覚えておきましょう。
📊 測定種別の比較表
| 種類 | 測定対象 | 主な目的 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 対地間測定 | 電線(L・N)と大地(アース) | 漏電・地絡が起きていないか確認 | L-アース / N-アース間で測定 |
| 線間測定 | 電線同士(LとNなど) | 相互絶縁の確認・機器内部の漏れ検知 | L-N / L-L / N-N間で測定 |
現場ではまず対地間測定で「大地への漏れ電流がないか」を確認し、その上で線間測定を行い「機器内部や配線間の絶縁状態」を調べるのが一般的です。照明器具やコンセントは金属部分が接地されているため、対地間測定は安全性の確認として特に重要なステップです。
🧰 実際の測定時に注意すべきポイント
実技試験や現場では「測定手順そのもの」よりも、「安全確認」と「正しい測定条件」が守られているかが評価ポイントになります。以下のような注意点は試験でもひっかけ問題として頻出です。
✅ 測定前のチェックリスト
- 電源を必ず遮断(ブレーカーOFF)し、感電・機器破損を防ぐ
- 測定対象の負荷機器(照明・コンセント)を取り外すか絶縁する
- 測定線の接続先(L/N/PE)を間違えないようラベル確認
- 接続部が緩んでいると正しい値が出ないため、確実な接触を確認
- 測定後は放電処理を忘れず行い、感電リスクを回避
📌 現場でよくあるミスと対策
- 負荷を外さず測定 → 機器が破損・内部ショートの原因に
- 照明スイッチがONのまま → 回路が閉じて誤った値になる
- 接地線と間違えてN線を測定 → 正常でも異常値に見える
特に照明回路は「スイッチの位置」と「負荷の有無」で値が大きく変わるため、スイッチが開状態で測定すること、蛍光灯器具などの電子部品は必ず取り外しておくことが基本です。これらを守らないと「本当は正常なのに異常判定」となり、試験でも減点対象となるため注意が必要です。
📝 絶縁抵抗測定表の正しい書き方と記録方法
電気工事士試験や現場実務では、絶縁抵抗測定そのものと同じくらい重要なのが「記録」です。測定結果を正しく書き残し、点検報告書や提出書類として整えることは、施工品質の証明であり、後々のトラブル防止にも直結します。特に「∞(無限大)」の扱いや測定表の記入ルールは試験で頻出ポイント。
ここでは、実際の記録例を交えながら、正しい記入方法と提出時の注意点を解説します。
♾️ 「∞(無限大)」の扱い方と正しい記録表記
絶縁抵抗測定では、測定値が「∞(無限大)」と表示されることがあります。これは「測定器が流れる電流を検出できないほど絶縁状態が良好」という意味で、理論上は非常に望ましい状態です。しかし、記録表にそのまま「∞」と書くのは誤りとされる場合があるため注意が必要です。
✅ 「∞」が出たときの正しい書き方
- 試験・報告書では「測定範囲以上」または「∞(無限大)」と併記するのが一般的。
- 「∞」だけでなく、「100MΩ以上」のように計器の最大レンジを明記するとより丁寧。
- 現場提出用では「測定限界値以上(例:>100MΩ)」と表記するケースが多い。
電気工事士試験では、「∞が出たときの記録方法として正しいものを選べ」という選択問題が出されることがあります。迷ったら「∞」「測定限界以上」「100MΩ以上」といった表現のいずれかを選ぶと安全です。
なお、現場では「∞」が出たからといって絶対に安全とは限らず、湿度や時間経過で値が変わることもあるため、記録はあくまで“その時点の測定値”として扱います。
📑 記録表のチェック項目と提出時の注意点
絶縁抵抗測定表は、単に測定値を書き込むだけでなく、「誰が・いつ・どの回路を・どんな条件で測定したか」を正確に記録することが求められます。以下のような基本項目を満たしていないと、試験では減点、現場では再提出になるケースもあります。
📋 測定表で必ず記載すべき項目
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 測定日 | 測定を行った日付 | 工事完了日や点検日と整合性があるか確認 |
| 測定者 | 作業担当者名 | 資格者であることを明記する |
| 測定箇所 | 回路名・盤名・分岐番号など | 「1F照明回路」など具体的に記載 |
| 測定条件 | 電源遮断・負荷取り外し等 | 条件が不明だと測定結果が無効になる恐れあり |
| 測定値 | MΩまたは∞ | 単位(MΩ)を忘れずに記入 |
📌 提出時の注意ポイント
- 空欄や記入漏れがあると再提出になる可能性がある
- 手書きの場合は判読可能な文字で記入し、訂正液はNG
- 電子データの場合はフォーマット指定(PDF・Excelなど)に従う
- 複数回路がある場合、測定順序と図面番号を対応させると評価が高い
記録表は「施工の安全性を証明する書類」であり、単なる事務作業ではありません。提出書類として完成度が高ければ、元請・検査機関からの評価も高くなり、施工会社の信頼性にもつながります。試験対策としても、測定値だけでなく「どう記録するか」までしっかり身につけておくことが合格への近道です。
電気工事士試験で必ず出る!絶縁抵抗測定の攻略ポイントと実践テクニック

筆記・実技のどちらの試験でも、絶縁抵抗測定に関する問題は高い確率で出題されます。単に測定値を覚えるだけでなく、「なぜその手順が必要なのか」「どのようなトラブルが起きやすいのか」といった理解が合否を分けるポイントです。
このパートでは、試験によく出る出題パターンから、実技での失敗防止策、現場でも役立つ応用知識まで、合格に直結する実践的な攻略法を解説します。
📚 試験によく出る絶縁抵抗測定の出題パターン
電気工事士試験では、「絶縁抵抗測定」そのものの操作を問うだけでなく、背後にある原理や用語の正確な理解、測定値の解釈などを問う問題が頻繁に出題されます。特に出題率が高いのが「対地電圧と絶縁抵抗値の関係」「線間測定と対地間測定の違い」といった応用知識です。
ここでは、実際の過去問傾向を踏まえて、出題されやすいパターンを押さえておきましょう。
⚡ 「対地電圧」と「絶縁抵抗値」の関係を理解する問題
絶縁抵抗測定の出題で定番なのが、「対地電圧が変わると、必要な絶縁抵抗値がどう変化するか」を問う問題です。これは単なる知識問題ではなく、実務的な安全基準を理解しているかどうかを測る狙いがあります。
📊 対地電圧と基準値の対応表(必ず暗記)
| 対地電圧 | 主な用途 | 最低絶縁抵抗値 | よく出る出題例 |
|---|---|---|---|
| 150V以下 | 単相100Vなど | 0.1MΩ以上 | 「100V回路の最低値は?」 |
| 150V超〜300V以下 | 三相200Vなど | 0.2MΩ以上 | 「200V系で不合格となる値は?」 |
| 300V超 | 高圧回路など | 0.4MΩ以上 | 「1000V印加時の最低値は?」 |
出題パターンの多くは「回路電圧から適切な絶縁抵抗値を選ばせる」形式で、選択肢は0.1MΩ・0.2MΩ・0.4MΩの3つで構成されます。
ここでは単に数値を暗記するだけでなく、「なぜ高電圧ほど大きな絶縁抵抗が必要なのか(漏れ電流が増えるため)」という背景まで理解しておくと、応用問題にも対応しやすくなります。
📏 「線間測定と対地間測定の違い」を問う問題
絶縁抵抗測定に関するもう一つの定番問題が、「線間測定と対地間測定の違い」を正しく理解しているかを確認する設問です。特に「どの組み合わせが正しいか」「どのような不良を見つけられるか」といった応用形式が多く出題されます。
📚 出題例パターン
- 「対地間測定の測定対象はどれか?」
- 「線間測定では何が確認できるか?」
- 「絶縁不良が大地漏れか線間漏れかを判定する測定はどれか?」
出題の意図は、「測定対象によって検出できる不良の種類が違う」点を理解しているかどうかです。 対地間測定では「大地への漏電(地絡)」を検出でき、線間測定では「相互間の絶縁不良(ショート・絶縁破壊)」を検出します。選択肢の中で「対地」「線間」の語を入れ替えてくるパターンが非常に多いため、意味と目的をセットで暗記しておくと正解率が一気に上がります。
✅ 試験対策ワンポイント
- 対地間=大地との絶縁 → 地絡・漏電をチェック
- 線間=導体同士の絶縁 → 絶縁破壊・短絡をチェック
- 出題では「どの測定で異常を発見できるか?」が頻出
これらの違いは試験だけでなく、実務でも非常に重要です。現場ではまず対地間測定で大きな事故要因を取り除き、次に線間測定で機器間の絶縁状態を確認する、というのが基本の流れです。問題文中のキーワード(「地絡」「相互絶縁」など)を読み取れるようにしておくと、選択肢問題も迷わず正解できます。
🧪 実技試験で失敗しないための測定ステップ
電気工事士の実技試験では、「正しい測定ができるかどうか」は合否を左右する重要な評価ポイントです。配線作業が完璧でも、絶縁抵抗測定の手順や安全確認でミスがあれば、大きな減点や不合格につながることもあります。
ここでは、試験本番でミスを防ぐための「作業前チェックリスト」と「測定中の落とし穴と対策」を、実務と試験の両方の視点から徹底解説します。
✅ 作業前チェックリストと安全確認ポイント
絶縁抵抗測定に入る前に、必ず確認しておくべき手順があります。これは安全のためだけでなく、試験では「正しい準備ができているか」自体が評価されるからです。下記のチェックリストは、実技試験前に声に出して確認するレベルで覚えておきましょう。
📋 作業前の必須チェック項目
- ① 電源を遮断:ブレーカーを必ずOFFにして通電状態を解除する
- ② 負荷機器の取り外し:照明・コンセント・電子機器を外して誤測定を防止
- ③ 測定箇所の確認:線間・対地間・端子位置をあらかじめチェック
- ④ 測定レンジの選定:使用するメガーが回路電圧に合っているか確認
- ⑤ 保護具の着用:絶縁手袋・絶縁靴など感電防止の準備
特に重要なのが「負荷の取り外し」です。試験では照明器具やコンセントが取り付けられた状態で課題が出ることもあり、これを外さずに測定すると機器の破損や誤った測定値につながります。実務でも基本中の基本なので、体で覚えておくと本番でも慌てず対応できます。
⚠️ 測定中によくあるミスとその回避策
測定自体は単純な作業に見えますが、実際の試験では焦りや思い込みでミスが起きやすいポイントが多く存在します。以下に、特に多い失敗例とその防止策を整理しました。
🚫 試験で多いミスと対策
| ミスの内容 | 起こりやすい原因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 負荷を外さず測定 | 時間短縮を急ぎ焦る | 測定前チェックリストを必ず声出し確認 |
| スイッチがONのまま | スイッチ位置の確認忘れ | 作業開始前に「開路状態」を確認 |
| 接続端子を間違える | L・N・E端子の位置把握不足 | ラベルや色コードを声に出して読み上げる |
| 放電処理を忘れる | 測定後すぐに次作業へ移行 | 「測定後=放電」の手順をルーティン化 |
この中で特に危険なのが「放電忘れ」です。測定後はケーブルや機器内部に電荷が残っている可能性があり、触れると感電事故につながります。実技試験では評価対象にもなっているため、測定終了後は必ずリード線を接地して放電してから片付けるようにしましょう。
💡 試験本番のコツ
- 「測定前・測定中・測定後」で作業を3フェーズに分けて考える
- 測定中は常に声出し確認でミスを防止する
- 手順が飛ばないようにメモやチェックシートを活用する
⚠️ 過去問に学ぶ「絶縁抵抗測定」頻出トラップ
絶縁抵抗測定は一見シンプルな作業に見えますが、電気工事士の筆記・実技試験では「ひっかけ」や「勘違い」を誘発する問題が頻出します。特に、測定レンジの選び方や負荷の取り外し有無に関する設問は、毎年多くの受験者が失点するポイントです。
ここでは、過去問で実際に出題された典型的な“トラップ”とその対策を、出題意図とともに解説します。
📉 測定レンジ選択ミスによる誤答例
過去問では、「使用電圧に対して誤った測定レンジを選ぶ」というミスが頻繁に問われます。例えば125V回路に対して500Vレンジを選ぶと、絶縁体の劣化や誤測定につながるだけでなく、選択理由を問う記述問題でも減点されるケースがあります。
🧪 過去問パターン(例)
| 問題文 | 誤答の例 | 正答・ポイント |
|---|---|---|
| 「AC100Vの回路を測定する場合の適切なレンジはどれか」 | 500Vレンジを選択 | 125Vレンジ(または250Vレンジ)を使用する |
| 「AC200V照明回路の絶縁測定で使用するレンジは?」 | 125Vレンジを選択 | 500Vレンジを使用する(250V以上が望ましい) |
ポイントは「測定電圧は回路電圧の1.25〜2倍を目安に選ぶ」という原則です。筆記試験では「数値暗記」ではなく「なぜそのレンジが適切か」を説明させる形式が増えており、根本原理を理解していないと選択肢問題で迷いやすくなります。
⚡ 「負荷を外さず測定」した場合の出題パターン
実技・筆記問わず定番なのが「負荷を外さずに絶縁抵抗測定を行った場合、どのような結果になるか」を問うパターンです。これは実務でも重大なミスであり、試験では“安全知識の確認”としてほぼ毎回出題されます。
💡 過去問での典型的な出題例
- 「照明器具を接続したまま測定すると、指示値はどうなるか?」 → 正解:「負荷を通じて電流が流れ、誤って低い抵抗値が表示される」
- 「コンセント機器を接続したまま絶縁測定を行った場合の結果として正しいものはどれか?」 → 正解:「機器が破損する恐れがある」
- 「負荷を外さず測定した場合の誤った判定を防ぐ方法として正しいのは?」 → 正解:「負荷を取り外してから測定する」
特に注意すべきは、「誤って低い値が出る=絶縁不良と誤判定」になる点です。これにより実務では機器交換など無駄なコストが発生する可能性があり、試験では“絶縁測定は負荷を切り離して行う”という基本の徹底が問われています。
✅ 対策ポイント(試験用)
- 設問に「負荷あり」と書かれていたら測定値が異常に低くなる選択肢を選ぶ
- 「誤判定・破損」というキーワードを見つけたら安全知識の確認問題と考える
- 実技では「負荷を外す動作」を省略すると減点対象になるため注意
🧭 試験合格のために覚えておきたい法令・基準値
電気工事士の筆記・実技では、法令名・用語・数値を正しく覚えているかが合否を分けます。特に「電気設備技術基準」とその解釈に基づく 絶縁抵抗の最低値は頻出。ここでは、出題されやすい条項と数字、そして数字の背景にある安全上の意味を、試験で迷わない形で整理します。
「電気設備技術基準」における絶縁抵抗の規定
低圧〜高圧の電路は、対地電圧に応じて「最低絶縁抵抗値」が定められています。試験では数字の丸暗記に加え、 印加電圧(メガーのレンジ)の典型値もセットで問われがちです。
| 区分(代表例) | 対地電圧の目安 | 最低絶縁抵抗値 | 典型的な印加電圧(メガー) | 試験での着目点 |
|---|---|---|---|---|
| 低圧(150V以下)…単相100V 等 | ≤150V | 0.1MΩ以上 | 主に500V(弱電は125/250V) | 最低値の数字とレンジの組合せ |
| 低圧(150V超〜300V以下)…三相200V 等 | 150–300V | 0.2MΩ以上 | 主に500V | 200V系で0.2MΩを即答 |
| 高圧・特別高圧(概要) | >300V | 0.4MΩ以上 | 主に1000V(専用計器) | 数字は0.4MΩで固定と覚える |
絶縁不良と感電・火災の関係性
絶縁不良は最終的に「漏れ電流の増加」として現れます。人体に流れれば感電、導体間や表面で発熱・アークが起これば火災につながります。 試験で問われる数字(0.1MΩ/0.2MΩ/0.4MΩ)は、回路電圧に対して概ね漏れ電流を1mA程度以下に抑える目安になるよう設計されている、と考えられます(下表参照)。
| 対地電圧の例 | 最低絶縁抵抗 | オームの法則から推定される漏れ電流 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 100V | 0.1MΩ | I ≒ 100V / 100kΩ = 1mA | わずかな感知レベルまで抑制が期待 |
| 200V | 0.2MΩ | I ≒ 200V / 200kΩ = 1mA | 電圧が上がっても概ね同レベルに抑制 |
| 400V相当 | 0.4MΩ | I ≒ 400V / 400kΩ = 1mA | 高電圧ほどより高い抵抗が必要な理由 |
👤 感電リスクの見方
人体影響のしきい値は条件により幅があります。一般には1mA前後で知覚、数mAで苦痛・離脱困難域に近づくとされますが、 余裕のある絶縁を確保する運用が前提です。
🔥 火災リスクの見方
絶縁不良部でのジュール発熱(I²R)、炭化トラッキング、アークが着火源となり得ます。 漏電遮断器(一般に30mA感度が多い)が動作する前の小リークでも、長期的な劣化・局所発熱は起こり得るため、 定期点検で絶縁抵抗のトレンド低下を早期に把握するのが有効です。
🛠️ 電気工事士が現場で活かせる絶縁抵抗測定の応用知識
資格試験で問われるのは「原理・手順・基準値」ですが、実務ではそれだけでは不十分です。現場では、配線の劣化診断・予防保全・定期点検といった応用スキルが求められます。 ここでは、経験豊富な電気工事士が意識している「試験を超えた実践知識」と、日常点検に役立つ測定のコツを解説します。
📊 定期点検・年次点検における測定のポイント
建築物や工場設備では、年1回以上の絶縁抵抗測定が電気事業法・労働安全衛生規則などによって義務づけられています。 このとき重要なのは、単に「基準値以上」かどうかを見るだけでなく、前回との比較(トレンド)や経年劣化の兆候を把握することです。
✅ 点検時にチェックすべき5つのポイント
- 前回測定値との比較(1年で大きく低下していないか)
- 湿度・気温条件を記録(絶縁値に影響するため)
- 絶縁抵抗値が「基準以上でも低下傾向」なら注意
- 高抵抗でも負荷・周囲環境の変化に注目
- 絶縁抵抗値の“単位”や“桁”の見落としに注意
特に高齢設備では、抵抗値が毎年少しずつ低下する傾向が見られます。これは必ずしも「不良」ではありませんが、0.5MΩ→0.3MΩ→0.2MΩと年々減少している場合は、 絶縁物の劣化・湿気・導体の表面汚染が進行しているサインと考えられます。
🔍 劣化診断・予防保全としての活用法
絶縁抵抗測定は「異常が起きたときのチェック」だけでなく、劣化診断・予防保全にも活用できます。現場では次のような応用的な使い方が行われています。
📉 絶縁値の低下トレンドで予防交換
毎年の点検データをグラフ化し、抵抗値の低下傾向を監視します。基準値を下回る前にケーブル・機器を交換することで、突発的な事故を防止できます。
🪛 高湿度・結露環境での早期検出
湿気や結露による絶縁劣化は短期間で進行します。季節の変わり目や梅雨時期にスポット測定を行うことで、事故を未然に防げます。
⚡ 局所絶縁不良の早期切り分け
分岐ごと・機器単位で測定を行うことで、異常箇所を特定しやすくなります。分岐のどこかが劣化している場合、全体測定だけでは発見できないこともあります。
また、電気工事士が行う絶縁測定の記録は、劣化予兆の早期検出だけでなく、保険・点検報告・設備管理台帳などでも重要な資料になります。 試験対策だけでなく、現場での信頼性向上にも大きく貢献すると考えられます。
🧩 【まとめ】絶縁抵抗測定と電気工事士試験で押さえるべき最重要ポイント
本記事の要点を「数値」「手順」「出題トラップ」の3軸で一気に総復習。
電気工事士の本番では、数式の暗記よりも安全手順の必然性と数値の意味を説明できるかが合否を分けます。
① 覚える数字はこれだけ:0.1MΩ/0.2MΩ/0.4MΩ と 125/250/500/1000V
📏 最低絶縁抵抗(回路区分)
- ≤150V(100V系):0.1MΩ以上
- 150–300V(200V系):0.2MΩ以上
- >300V(高圧含む):0.4MΩ以上
⚙️ 典型メガーレンジ
- 弱電・電子機器混在:125/250Vから開始
- 低圧配電の一般配線:500Vが標準
- 高圧機器の診断:1000V(専用計器)
🧠 語呂&原理で固定
100→0.1/200→0.2/高圧→0.4で暗記。
根拠は R=V/I(オームの法則):各区分で漏れ電流をおおむね1mA程度まで抑制。
② 測定は停電→検電→負荷外し→レンジ選定→放電の一直線
表面リークが疑わしいときはG端子(ガード)で表面経路をバイパス。
③ 本番で落としがちな3つのミス
→ 回路電圧と対地電圧区分から選ぶ。
→ 機器外しが原則。
→ >100MΩ等の数値表現+単位MΩ。
④ 試験直前の「30秒チェックリスト」
- ブレーカーOFF・検電OK・札掛けOK
- 線間は負荷外し(照明ランプ・電子機器)
- レンジ=回路に適合(弱電125/250V・一般500V)
- 測定後は放電→段階復旧
- 記録は「MΩ」単位/∞は>最大値で記載
⑤ 合格後に差がつく現場運用:記録=資産、数字=トレンド
「0.1/0.2/0.4MΩ」「125/250/500/1000V」「停電→検電→負荷外し→レンジ→放電」の3セットを体に叩き込みましょう。

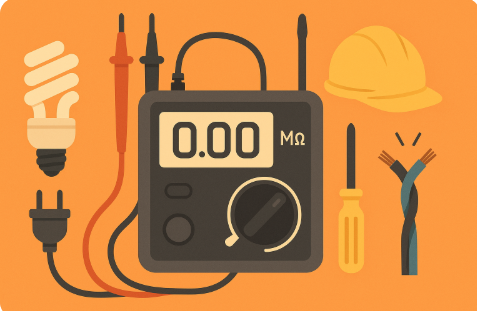
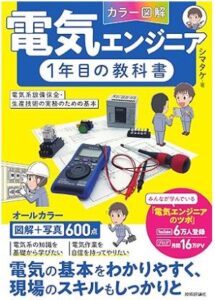
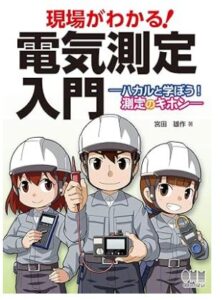
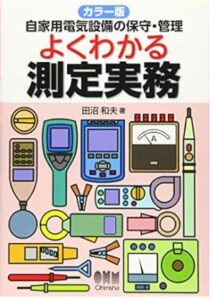


コメント