給与所得控除 × 2025 × 改正
【今すぐ確認!】給与所得控除2025改正で損しないためのポイントをわかりやすく紹介
「給与所得控除の2025年改正って、結局いつから変わるの?」——そんな疑問を持つ人が増えています。
ニュースで聞いたけど自分に関係あるのか分からない、年末調整で何をすればいいのか不安…という声も少なくありません。
特にパートやアルバイト、共働き家庭では、この「改正」が手取りや扶養範囲に直結する大きなポイントになります。
本記事では、給与所得控除2025改正の施行時期、対象者、年末調整への具体的な影響をわかりやすく解説します。
これを読めば、「いつから」「誰が」「どんな準備をすべきか」がスッキリ理解できるはずです。
2025年の年末を迎える前に、いま知っておきたい改正ポイントを一緒に整理していきましょう。
記事のポイント
- 2025年から控除額が引き上げ
- 年末調整で自動的に反映される
- 103万円→123万円が実質ライン
- 住民税は2026年度から反映
- パート・学生・主婦に影響大
- 給与所得控除2025改正はいつから?変更点をわかりやすく解説
- 給与所得控除2025改正で年末調整・扶養・住民税はどう変わる?
給与所得控除2025改正はいつから?変更点をわかりやすく解説

2025年は、働く人すべてに関係する「給与所得控除」の大きな転換点となります。
これまで「103万円の壁」と呼ばれてきた非課税ラインが引き上げられ、基礎控除の拡大とあわせて手取りが増える人も出てきます。
本章では、改正の施行時期(いつから適用されるのか)や引き上げ後の控除額、そして主婦・パート・学生に与える影響までをわかりやすく整理します。
「いったい自分はどのタイミングで変わるの?」という疑問を、ここでしっかり解消しましょう。
給与所得控除2025改正の概要と背景をやさしく説明
① 控除の底上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円にアップ。低〜中所得者の課税が軽くなります。
② 基礎控除も連動
基礎控除も48万円→58万円に引き上げ+所得に応じた上乗せ特例あり。セットで見ると節税効果が大きくなります。
③ 「壁」を上にずらす
2つの控除が上がることで、これまで103万円で止めていた働き方をもう少し増やしても大丈夫になる設計です。
※「123万円までOK」「160万円まで非課税になる」という数字には若干のブレがあります。これは ①所得税で見るか ②住民税で見るか ③扶養控除の要件で見るかによって説明が分かれるためです。信頼できる一次情報(財務省・国税庁・令和7年度税制改正大綱)の公開前後では数字が変わる可能性もあるため、 「現時点で公開されている情報をもとにした目安です」。
そもそも給与所得控除とは何か?
給与所得控除は、会社員・パート・アルバイトなどの「給与をもらって働く人のための一括経費」のようなものです。個人事業主のように領収書を集めて経費を出すのではなく、国が「年収がこれくらいなら仕事にこれくらいお金を使っているはず」とあらかじめ決めておき、その分を自動で差し引いてくれます。だから会社員はふだん意識しなくても、年末調整のときにもう控除が入っているわけです。
🔁 給与で働く人の税金計算の流れ(シンプル版)
- 1年間の給与収入を合計する
- 給与所得控除を差し引いて「給与所得」を出す
- さらに基礎控除・扶養控除・配偶者控除などを差し引く
- 残った金額に税率をかけて所得税を計算
2025年改正の目的は「物価高対応」と「働き方支援」
今回の改正は、単なる「控除を増やすだけ」の話ではなく、政府がここ数年ずっと課題にしてきた 「人手不足・就業抑制・物価高での手取り目減り」を一気にテコ入れするためのパッケージの一部です。
特にパートタイム比率が高い小売・外食・介護では、103万円の壁がシフト調整のブレーキになっていたため、「もうちょっと上まで働いても損しないようにしよう」というメッセージ性があります。
① 物価高へのピンポイント対応
同じ年収でも生活コストが上がっているので、課税のスタート地点を少し下げてあげる=控除を増やす、という考え方です。
② 働きたい人を止めない
「103万円を超えると税金や社会保険が…」という就業調整を減らし、人手不足の現場に回ってもらいたいという政策的な狙いがあります。
⚠ 注記
住民税側の具体的な控除額の上げ方や、一部の自治体での適用タイミングについては、「最新の自治体広報・税務課の案内を確認してください」。
給与所得控除2025改正はいつから施行されるのか
📅 施行タイミングの結論
国税庁が公開している令和7年度(2025年度)の案内では、改正は原則「2025年12月1日施行」で、2025年分の所得税から適用と明示されています。つまり、2025年12月に行う年末調整から新ルールになる、という理解でOKです。
⚠ 所得税と住民税はズレます
所得税は2025年分からですが、住民税は1年遅れの2026年度(令和8年度)から反映という自治体が基本です。
適用開始は2025年12月から
国税庁の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」では、明確に 「これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。」 と書かれています。つまり「2025年中に稼いだお金」について、年末(12月)にまとめて新ルールで計算し直す、というイメージです。
✅ ここがポイント
- 2025年の途中(1〜11月)で「新しい控除額」に自動で切り替わるわけではない
- 12月の年末調整という1か所のイベントでガッと切り替えるから、会社側の処理負担が増えない
- 「2025年分の所得税に適用」なので、確定申告をする人も2026年の確定申告でこの改正を使うことになる
住民税への反映は2026年度からスタート
所得税での改正が2025年12月からなのに対し、個人住民税(市県民税)は1年遅れて2026年度から反映という形をとります。これは住民税が「前年の所得」をもとに翌年課税する仕組みだからです。つまり、 2025年中(1月〜12月)に得た給与を、新しい給与所得控除で計算して、2026年度の住民税として課税するという流れです。
📝 住民税だけ1年ズレる理由
- 住民税は「前年の所得」をベースにする後追い方式
- 2025年に改正された所得(給与)を、2026年度の住民税として市区町村が計算する
- 市区町村ごとに条例改正やシステム対応が必要なため、すべての自治体で同じタイミングで周知が出るとは限らない
※一部自治体の公式ページではすでに「令和8年度(2026年度)から給与所得控除の最低額を65万円に」と明示されており、国の改正と足並みをそろえています。
ただし、住民税は自治体が条例で定める部分もあるため、全自治体分を網羅した最新一覧は現時点で公開されていません。このためお住まいの市区町村の2026年度個人住民税のお知らせをご確認ください。
なぜ年末調整のタイミングで反映されるのか
「それなら2025年1月からもう新しい控除額で給料を計算してくれればいいのに?」と思うかもしれません。これをやらないのは、企業側の給与計算システムや源泉徴収の事務負担を最小限にするためです。国税庁の案内でも、 「令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません)」 と明示されています。
企業側の事情(実務)
- 源泉徴収簿・扶養控除申告書などを年の途中で変えると混乱しやすい
- 給与計算ソフト・クラウド給与の改修が1回で済む
- パート・アルバイトが多い事業所でも説明を12月1回に集約できる
税法側の事情
- 所得税は「1年間の所得」を年末に確定させる仕組みになっている
- 途中月の給与で細かく対応するより、年末にまとめたほうが過不足を調整しやすい
- 多くの改正を「年末調整で一括適用」するのが日本の実務慣行
さらに、今回の2025年改正では、基礎控除の段階的引き上げ・特定親族特別控除の創設・給与所得控除の最低額アップがセットになっているため、途中の月だけ新システムにしてしまうと「1〜11月は旧ルール、12月だけ新ルール」という非常に読みにくい明細になります。これを避けるために、 「年末調整で一気に新ルールに寄せる」方式が採られていると考えられます(制度設計上の合理性からの推測です)。
※2025年11月までの源泉徴収実務には変更が生じない、という点は国税庁資料が一次情報です。もし「ウチの会社は1〜11月も変わると言っている」などのケースの場合、その会社が独自に前倒し対応しているか、給与システムの都合で先行テストしている可能性もあります。
給与所得控除2025改正で「103万円の壁」はどう変わる?
2025年の給与所得控除の改正は、長年の課題であった「103万円の壁」に直接メスを入れる内容です。 パートや学生アルバイトが「税金がかかるから働きすぎないように調整する」――そんな状況を少しでも改善するため、非課税ラインそのものが引き上げられます。
ここでは、「新しい非課税ラインの金額」、「学生アルバイトへの影響」、そして「主婦・学生が得られる実質的メリット」を順に解説します。
新しい非課税ラインは123万円に
これまで多くの家庭やパート労働者が気にしていた「103万円の壁」とは、所得税がかからない上限額(=課税最低限)のこと。 2025年からは、給与所得控除と基礎控除の両方が引き上げられることで、この非課税ラインが103万円 → 123万円に拡大します。
この引き上げにより、パート主婦や学生アルバイトでも「もう少し働ける」ようになります。 また、企業側もシフト調整に悩まされにくくなり、労働力確保の面でもプラスに働くと考えられます。 ただし、非課税になる金額は「所得税」での話であり、住民税は自治体によってズレが出る点には注意が必要です(現時点で一部自治体の情報は未発表です)。
学生アルバイトは150万円まで扶養範囲に
これまで、大学生などの扶養親族に関する「特定扶養控除」は、親の所得控除を受けられる条件として学生本人の年収103万円以下が目安でした。 2025年改正では、この要件が見直され、150万円まで親の扶養に残れる方向で決定されています。
🎓 学生控除の拡大イメージ
- 19〜22歳の大学生が対象(特定扶養親族)
- 親の扶養控除を受けられる年収上限:103万円 → 150万円
- 学生自身も「勤労学生控除」の対象なら追加で税負担軽減あり
※この150万円ラインは、政府税制改正大綱(2024年12月発表)で「2025年分の所得税から適用」とされており、詳細な所得計算方法は国税庁の年末調整マニュアルで確定予定です。 現時点では「親の扶養控除の枠内でアルバイト時間を増やせる」という程度の理解で問題ありません。
この改正は、特に学生の就業機会を広げる狙いがあります。 人手不足が続く飲食・小売・観光業では、「学生バイトがシフトを抑えざるを得ない問題」が大きな痛点でした。 改正により、学生が学費や生活費のためにもう少し働いても親の扶養から外れにくくなるため、家計・企業双方にメリットがあります。
パート・主婦・学生への実質的メリット
👩🦰 パート主婦のケース
- 年収120万円台まで所得税がかからない
- 扶養のまま働ける時間を増やしやすくなる
- 夫の配偶者控除も維持しやすい(合計所得58万円基準)
🎓 学生アルバイトのケース
- 150万円まで親の扶養範囲に残れる
- 社会保険料の発生を避けつつ学費をカバーしやすくなる
- 企業側も学生の労働時間を増やしやすくなり人手不足解消に貢献
🏢 企業側のメリット
- シフト調整が柔軟になり、急な欠員対応がしやすくなる
- 「壁」を理由に勤務を断られるリスクが減少
- 年末繁忙期に人手を確保しやすくなる
⚠ 注意と補足
- 社会保険(130万円・106万円の壁)は別ルールなので混同注意。
- 住民税非課税の基準は自治体によって微調整がある。
- 2025年12月の年末調整で一気に反映されるため、企業は給与システム更新が必要。
なお、政府資料では「年収123万円まで課税なし」「学生は150万円まで扶養内」とされていますが、住民税や保険加入要件を考慮すると一律ではありません。 現時点で信頼できる情報が揃わない自治体もあり、詳細は確定申告期(2026年2月〜3月)に正式に確認することが望ましいです。
💡 2025年改正後の「160万円の壁」や働き方の影響については、
【学生・副業必見】給与所得控除2025改正後の160万円の壁とは?扶養・バイトの新ルールまとめ で詳しく整理しています。
基礎控除の引き上げとセットで見るべき理由
💡 なぜ「給与所得控除」だけ見ちゃダメなの?
2025年は給与所得控除が55万円→65万円に上がるだけでなく、同じタイミングで基礎控除も48万円→58万円に上がります。つまり「控除が2段重ねで増える」ので、103万円の壁が123万円・場合によっては160万円付近まで広がるわけです。片方だけを見ると「思ったほど増えない」ので、必ずセットで説明する必要があります。
📌 ポイントは「物価高対応+就業調整の解消」
財務省の2025(令和7)年度税制改正大綱では、物価高で負担が重くなっている層を支えることと、パートが103万円で働き控える問題を減らすことが狙いとされています。だから「給与所得控除+基礎控除」を同時に10万円ずつ上げる構造になっています。
基礎控除も2025年に48万円→58万円へ
2025年(令和7年)分の所得税から、すべての納税者が最初に引ける基礎控除の金額が、これまでの48万円 → 58万円に引き上げられます。これは財務省の税制改正大綱と国税庁の「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」で明示されています。
さらに、国税庁が出している年末調整の解説では「令和8年1月支給分以降の源泉徴収税額表も対応させる」とされています。これは、給与計算システムが2025年12月に一度に変わるのを避け、2026年1月からの支給にも対応できるようにするための措置です。
所得によって控除額が変動する「基礎控除特例」とは
2025年の特徴は、単に「全員10万円アップ」ではなく、所得が低い人ほどさらに上乗せされる特例(段階的拡大)が入ったことです。会計・給与ソフトの解説でも「2025〜2026年は58万円〜95万円の範囲で控除される暫定措置」と説明されています。
📝 基礎控除特例(2025〜2026年の暫定イメージ)
- 通常の基礎控除:58万円(合計所得2,350万円以下)
- 一定の条件に該当する人:58万円に+5万〜最大37万円の上乗せ → 最大95万円まで拡大
- 上乗せの幅は「所得の多寡」と「扶養の有無」によって変わる
- 2027年以降は基本的に58万円で安定させる方向と紹介している解説もある(暫定措置のため)。
※特例の細かい要件(どの所得層まで95万円にするか、何年まで暫定にするか)は、2025年11月ごろに出る国税庁の「年末調整のしかた」で最終版が示されるのが通常です。現時点(2025年11月1日)では、一部資料で表現がズレているため、「現時点で信頼できる情報がすべて揃っているわけではありません。最新の国税庁資料を確認してください」。
この「基礎控除特例」が入ることで、もともと課税最低限ギリギリだった人(パート・年金生活者・子育て世帯の片働きなど)ほど得をしやすい構造になります。 一方、年収が高くなると従来と同じように控除が削られていくので、「お金持ち優遇では?」という批判にも配慮したつくりになっています。
給与所得控除とのダブル効果で節税幅が拡大
ここが今回いちばん重要なポイントです。 2025年改正は 「給与所得控除が+10万円」 + 「基礎控除が+10万円(+特例)」 という2段の控除アップなので、合計すると最低でも20万円分、非課税にできる額が増えることになります。 この2つが同時に上がるからこそ、「103万円の壁が123万円になった」と説明できるわけです。
① 給与所得控除の引き上げ
55万円 → 65万円 → 給与で働く人の「みなし経費」が増える → 最初に引ける額が増える
② 基礎控除の引き上げ
48万円 → 58万円(+特例で最大95万円) → 誰でも使える「最低限の非課税枠」が拡大 → 住民税の非課税ラインにも影響
③ 合算して「壁」が上にずれる
①+②で20万円以上の控除増 → 103万円→123万円〜160万円に拡大 → パート・学生が「もう1〜2万円働く」を選びやすくなる
⚠ 注記
- 所得税の「壁」は2025年分から上がるが、住民税の「壁」は2026年度からになる。
- 自治体の条例改正が遅れると「所得税は非課税なのに住民税だけかかる」年が発生する。
- この部分については、お住まいの自治体の令和8年度(2026年度)住民税案内を確認してください。
💡 併用メリットをもっと深く知りたい方はこちらの記事▼▼▼
【初心者向け】給与所得控除と基礎控除の違い・併用メリットをやさしく解説
「どれだけ節税できる?」「併用の注意点は?」といった実践的なポイントを知りたい場合はこちらへ。
給与所得控除の金額表と計算式(2025年版)
2025年分から、給与所得控除の最低保障額が65万円に引き上げられるという大きな変更があります。 それだけでなく、給与収入別の控除額や計算式にも“適用範囲”の整理が入っており、パート・アルバイトの人・主婦・学生・人事担当者にとっては押さえておきたい内容です。
ここでは、最低控除額65万円の意味、収入別の早見表、具体的な計算例を順に解説します。
最低控除額65万円の復活とは?
2025年分所得税から、給与所得控除の最低保障額がこれまでの55万円から65万円に引き上げられました。これは、収入が比較的少ない給与所得者の税負担を軽くするためです。
🔍 補足ポイント
- この“65万円”は主に給与収入が約190万円以下の人向けのラインです。
- 190万円を超える給与収入の場合、従来どおり「収入×30%+8万円」などの速算式が適用されます。
- この変更により、「働きを控える必要が出ていた収入帯」の人にも余裕が生まれる可能性があります。)
給与収入別の早見表で見る控除額の違い
以下は改正後(2025年分以後)における給与所得控除の代表的な収入帯と控除額の目安です。あくまで「少額収入者向け」の枠組みで、収入が高い場合には旧方式が継続されることに注意してください。
※ここで「1,625,000円」等の数字は改正前の速算式で使われていたもので、一部情報では「1,900,000円以下まで」という表記もあります。実務上は給与収入が190万円程度までで最低保障の65万円が適用されるという説明が多いです。
パートやアルバイトの人が確認すべき計算例
以下は、給与収入が少ないパート・アルバイトの方が2025年改正後に確認すべき“控除後の金額”のざっくり計算例です。年末調整や扶養の判定などで「自分はどれくらい控除を使えるのか」をイメージするのに役立ちます。
🧮 計算例
- 年収 1,000,000円 → 控除額65万円 → 控除後給与所得35万円
- 年収 1,230,000円 → 控除額65万円 → 控除後給与所得58万円(さらに基礎控除+〜特例適用で課税所得0円可能)
- 年収 1,600,000円 → 控除額65万円 → 控除後給与所得95万円 → 基礎控除95万円(特例)を適用すれば課税所得=0円も視野に)
ただし、上記は「控除以外に医療費控除・配偶者控除など他の控除がない」ことを前提としたシンプルな例です。実際には社会保険料控除・配偶者控除・扶養控除・特定支出控除などの影響も受けるため、「控除後所得=0円」と書かれていても、住民税・健康保険・年金などの負担がゼロになるわけではありません。特に住民税・社会保険の壁は別ルールなので注意が必要です。
「そもそもの基礎」「年末調整の実務」「手取りの変化」「160万の壁の具体例」を知りたい方は、下の記事もチェックしてみてください。
給与所得控除2025改正のポイントまとめ(前半の整理)
ここまで紹介してきた内容を整理すると、2025年の給与所得控除改正は「控除額の引き上げ」「非課税ラインの緩和」「年末調整での適用タイミング」という3つの柱で構成されています。 特に、103万円→123万円ラインへの変更は多くの人に影響する重要な転換点です。
以下では、改正の要点をわかりやすく振り返ります。
いつから・どんな人が・どの程度変わるのか
- 施行時期:2025年分(令和7年分)の所得税から適用され、2025年12月の年末調整で反映。
- 対象者:給与所得者すべてが対象(正社員・パート・アルバイト・派遣などを含む)。
- 改正内容:最低控除額が55万円→65万円に、非課税ラインが103万円→123万円に引き上げ。
- 目的:物価高による実質可処分所得の減少を緩和し、「働き損」を軽減するため。
💡 ポイントまとめ
- 2025年12月の年末調整から自動的に反映される。
- 全給与所得者に適用され、特にパート・学生・主婦層に恩恵が大きい。
- 控除額引き上げにより、所得税だけでなく住民税の負担も軽くなる可能性がある。
103万円→123万円のライン引き上げの意味を再確認
今回の給与所得控除2025改正で注目されるのが、長年変わらなかった「103万円の壁」の引き上げです。 これは単なる数字の変更ではなく、「働き方の制限をなくす」という政策的な意味合いを持っています。
📌 補足解説:
かつては「103万円を超えると扶養から外れる」とされていたため、多くの家庭では“働きすぎない調整”が行われていました。 しかし、今回の改正で123万円まで非課税枠が拡大されることにより、「もう少し働いても損しない」層が増えると考えられます。 これにより、家庭の可処分所得増加と人手不足対策の両立が期待されています。
ただし、社会保険の壁(106万円・130万円など)は別ルールであり、今回の改正では対象外です。 所得税や住民税が軽くなる一方で、保険料負担の発生ラインは変わらないため、「税金の壁」と「保険の壁」を分けて理解しておく必要があります。
給与所得控除2025改正で年末調整・扶養・住民税はどう変わる?

給与所得控除の改正は、「いつから」だけでなくどのように家計へ影響するのかが最も気になるところです。特に2025年改正では、年末調整の書類や計算方式、扶養・配偶者控除、住民税にも関係する変更が行われます。
この章では、企業の人事担当者が押さえるべき実務ポイントから、主婦・パート・学生が知っておきたい「扶養範囲」「非課税ライン」の変化までを一挙に解説。
最後には、給与所得控除2025改正の全体像をまとめて理解できる総整理も紹介します。
給与所得控除2025改正が年末調整に与える影響
給与所得控除の改正は、単に「控除額が増える」だけでなく、年末調整や給与計算の仕組みに直接影響します。 特に2025年改正では、源泉徴収票の記載内容や控除申告書の様式にも変更が生じる見込みで、企業・個人ともに事前準備が欠かせません。
以下では、実務担当者・従業員双方の視点から、改正が及ぼす具体的な影響を解説します。
源泉徴収票・控除申告書の様式が変更に
給与所得控除額が変更されると、それに連動して源泉徴収票や給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記載欄も見直されます。 2025年12月の年末調整分から新しい様式が導入される見込みで、国税庁から正式なフォーマットが公表され次第、企業は順次対応を進める必要があります。
📄 主な変更が想定される項目:
- 「給与所得控除後の金額」欄の自動計算式の変更
- 「所得控除の合計額」欄の再配置(基礎控除引き上げへの対応)
- 電子申告フォーマット(e-Tax)へのデータ項目追加
現時点(2025年11月時点)では、国税庁公式サイトで詳細な書式変更案は公表されていませんが、 2020年の改正時と同様に、「給与所得控除後の金額」や「所得金額調整控除」の記載欄が整理される可能性が高いと考えられます。
給与計算システムの更新が必要になるケース
企業で利用されている給与計算ソフト(弥生給与、freee、マネーフォワード、PCAなど)は、改正に伴う新しい控除額・計算式へ対応する必要があります。 とくに社内システムを独自構築している企業では、控除テーブルの修正や年末調整モジュールの更新を怠ると、誤差が生じる可能性があります。
⚙️ 更新が必要になる主なケース:
- 給与所得控除額が旧制度(55万円)で固定されている
- 控除計算式を年収に応じて自動反映している
- 給与明細や年末調整書類に「控除後金額」を表示している
- 源泉徴収票フォーマットを独自に運用している
クラウド型の給与計算システムの場合、多くは自動アップデートにより新制度へ対応しますが、 社内カスタマイズしているExcelベースの給与台帳や自社ERPの場合は手動対応が必要です。 年末調整時期(11〜12月)に混乱を避けるため、夏〜秋の段階でシステムチェックを行うのが理想です。
企業の人事担当者が注意すべき3つの変更点
📌 実務上のチェックポイント
- 年末調整マニュアルの更新 → 改正内容を踏まえ、控除計算式・源泉徴収票記載例を最新化。
- 従業員説明会・社内通知の実施 → 非課税ライン引き上げによる所得税軽減の周知。
- 人事システム・会計ソフトの検証 → 年末調整シミュレーションを実施し、反映漏れを防止。
また、2025年改正では「基礎控除」の引き上げもセットで実施されるため、 控除の二重適用や自動計算のずれが起きないよう、社内チェックリストの更新が重要になります。 特に中小企業では「給与ソフトが古いまま」「担当者が交代したばかり」などの理由で、 年末調整ミスが生じやすいため、早めの情報共有と準備がカギです。
✅ ポイントまとめ:
給与所得控除2025改正は、年末調整の事務手続き・システム設計・従業員周知のすべてに影響を与える改正です。 「自動で変わるから大丈夫」と油断せず、早期のフォーマット確認と社内対応を進めておきましょう。
👉 詳しい書き方や実務の流れは、こちらの記事で解説▼▼▼
【完全版】給与所得控除2025改正で変わる年末調整の書き方|源泉徴収票・控除申告書の新ルールを解説
扶養控除・配偶者控除の基準変更に注意
給与所得控除2025改正に連動して、扶養控除・配偶者控除の所得基準も引き上げられます。 これにより、「配偶者が少し多く働いても扶養のまま維持できる」ケースが増え、特に共働き世帯・学生扶養家庭にとっては大きな朗報です。
ただし、税金・社会保険・手当の判定基準はそれぞれ異なるため、制度ごとに整理して理解しておくことが重要です。
配偶者・扶養親族の所得要件が48万円→58万円に
2025年改正では、配偶者控除・扶養控除における「合計所得金額の上限」が48万円から58万円へ引き上げられます。 この変更は、基礎控除と同じく10万円の増額で、物価高や働き方の多様化に対応する目的があります。
この改正により、配偶者がパートなどで働いている場合、年間123万円までは配偶者控除の対象になります。 これまで「103万円を超えると扶養から外れる」として働き方を抑えていた層にも、就業調整の見直しが広がると考えられます。
学生扶養の特例は150万円までに拡大
一般扶養親族の所得要件に加え、「特定扶養親族(16歳〜23歳の学生など)」の特例も改正されます。 2025年からは、学生アルバイトの年収150万円まで非課税対象となり、勉学と両立する学生の負担軽減が図られます。
🎓 学生アルバイトの注意ポイント:
- 所得150万円以下であれば、親の扶養控除が維持可能。
- ただし、社会保険の被扶養者基準(130万円)は別ルール。
- 年末調整・確定申告で「勤労学生控除(最大27万円)」も併用可能。
この制度拡大により、「働きながら学ぶ学生」がより柔軟にアルバイト収入を得られるようになります。 また、企業側も雇用調整を行いやすくなるため、学生アルバイトの確保にもプラス効果が見込まれます。
夫婦共働き世帯の税金シミュレーション例
配偶者控除・扶養控除の引き上げにより、共働き世帯では税額がどの程度軽減されるのかを、簡易的にシミュレーションしてみましょう。
このように、同じ世帯所得でも妻(または夫)の収入増により、家計全体での実質可処分所得が増加します。 改正は「働き控えの抑制」と「労働参加の促進」を両立させる狙いがあるため、今後も段階的な見直しが続くと考えられます。
✅ ポイントまとめ:
2025年の給与所得控除改正では、配偶者控除・扶養控除・学生特例の3点セットで所得基準が引き上げられます。 「103万円の壁」だけでなく、「扶養48万円ライン」も見直されることで、より柔軟な働き方と節税が可能になります。
給与所得控除2025改正後の住民税はどうなる?
給与所得控除の改正は、所得税だけでなく住民税(市県民税)にも大きく関係します。 ただし、住民税は「前年の所得」を基に計算されるため、実際の反映は1年遅れとなります。 この時間差により、2026年度分の住民税から新しい控除額が適用される見込みです。
以下では、その仕組みと影響を具体的に解説します。
住民税への反映は1年遅れ(2026年度分から)
所得税と住民税は計算基準年度が異なります。 所得税は「当年の所得」に対して課税されるのに対し、住民税は「前年の所得」をもとに課税されるため、1年のタイムラグが発生します。
📅 反映スケジュールのイメージ:
- 2025年(令和7年)所得税:改正後の控除を即時適用(年末調整で反映)
- 2026年度(令和8年度)住民税:2025年分の所得をもとに算出 → 改正内容が反映
したがって、2025年に給与所得控除が引き上げられても、住民税の軽減を実感できるのは2026年6月以降からとなります。 これは給与明細の「住民税天引き額」で確認できるはずです。
非課税世帯の範囲が広がる可能性も
給与所得控除と基礎控除の引き上げにより、課税所得がゼロになる人が増加します。 結果として、住民税の「非課税世帯」に該当する層が広がると考えられます。
💡 非課税世帯の条件(一般例):
- 単身者:所得金額が45万円以下(年収約100万円以下)
- 夫婦+子1人:所得金額が100万円前後まで非課税対象
控除が増えることで、これまでわずかに課税対象だった家庭が「住民税非課税」になる可能性があります。 その結果、国民健康保険料・介護保険料の減額、就学支援金・保育料の軽減など、連動する行政サービスの負担が減るケースも期待されます。
⚠️ 注意:
一方で、非課税世帯の拡大は自治体財政への影響もあり、所得制限を伴う給付金制度の再調整が行われる可能性もあります。 詳細は2025年末の「地方税法改正」によって確定すると見込まれます。
自治体ごとの影響と注意点
住民税は全国一律ではなく、各自治体(市区町村+都道府県)が条例で細部を定めています。 給与所得控除の引き上げは国の制度変更ですが、課税方式や減免制度の細部は地域ごとに差があります。
🏛️ 自治体別に確認すべきポイント:
- 均等割・所得割の減免基準(自治体独自の非課税基準)
- 住民税非課税世帯支援金・給付金の適用条件
- ふるさと納税の控除上限への影響(所得控除増により枠が変化)
特に、2026年度の住民税決定通知(毎年6月送付)で「前年との比較」を確認することが重要です。 給与明細や源泉徴収票と照らし合わせ、所得税・住民税の両方で控除が反映されているかを確認しましょう。
✅ ポイントまとめ:
給与所得控除2025改正は、所得税よりも1年遅れて住民税に反映されます。 2026年度以降、非課税世帯の拡大や自治体支援制度への影響が見込まれるため、早めにお住まいの自治体HPで基準を確認しておきましょう。
▶ 住民税の詳しい解説はこちらの関連記事へ▼▼▼
ふるさと納税や副業への影響はある?
給与所得控除の改正は、ふるさと納税や副業収入のある人にも間接的な影響を与えます。 控除額の増加によって手取りが増える一方で、所得控除の上限や確定申告の取り扱いに注意が必要です。
以下では、寄附金控除・副業・確定申告の3つの観点から、2025年改正の影響を整理します。
寄附金控除の上限は変わらないが手取りが増える
給与所得控除2025改正によって所得税・住民税の課税所得が減少するため、手取りが増加する効果が見込まれます。 ただし、ふるさと納税の寄附金控除の上限額(=所得に応じた自己負担2,000円で済む寄附額)は、基本的に変わりません。
控除上限額は「所得」に連動するため、課税所得が減れば寄附上限も若干減少しますが、 一方で税負担が軽くなることで実質的な手取りは増える傾向にあります。 そのため、ふるさと納税を活用しても家計負担はほとんど変わりません。
副業収入がある人は控除額を自分で確認する必要あり
2025年改正後も、副業や兼業で複数の収入源がある場合は、給与所得控除はそれぞれの勤務先で個別に適用されます。 ただし、最終的な課税所得の合算は確定申告で行うため、控除の重複や過少申告に注意が必要です。
💼 副業収入がある人のチェックリスト:
- 複数の源泉徴収票をすべて合算して確定申告を行う。
- 給与所得控除は各社ごとに自動計算されるが、最終的な税金は合算ベース。
- 副業が雑所得・事業所得扱いの場合は、別途経費計上も可能。
- ふるさと納税の控除上限は、合計所得を基に計算される点に注意。
特にフリーランスや副業収入がある人は、給与所得控除の計算式を確認し、 「給与所得控除後の金額」を自分で正確に把握することが大切です。 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば自動計算が可能です。
確定申告時に注意すべきポイント
2025年改正後の確定申告では、控除額や非課税ラインが変わるため、前年の申告内容をそのまま流用すると誤りが生じる可能性があります。 特にふるさと納税や副業をしている人は、控除額の適用条件をよく確認しておきましょう。
📘 確定申告での注意点まとめ:
- 2025年分の確定申告は2026年2月〜3月に提出。
- 新しい控除額(最低65万円)を自動反映する申告書様式が使用される見込み。
- ふるさと納税の寄附金受領証明書を正しく添付(e-Taxの場合は自動反映可)。
- 副業がある場合は源泉徴収票をすべて合算し、雑所得・事業所得も漏れなく記載。
改正後初年度の申告では、国税庁サイトや市区町村の税務課による説明資料を確認することが推奨されます。 とくに、給与所得控除・基礎控除・ふるさと納税控除の3つが重なる人は、申告書の入力ミスが起きやすいため注意が必要です。
✅ ポイントまとめ:
給与所得控除2025改正によって、ふるさと納税・副業ともに手取り増・控除の整理がポイントになります。 控除の自動計算に頼らず、自分の所得と控除の関係を理解することが、2026年以降の節税対策につながります。
給与所得控除2025改正による手取り額の変化例
2025年の税制改正により、実際にどのくらい手取り額が変わるのか——年収100万円、120万円、150万円の3つのケースを使って具体的に比較します。
各ケースはあくまで「給与収入のみ・他の控除なし」というシンプルなモデルですので、実際には社会保険料・扶養控除・住民税等も加味する必要がありますが、全体のイメージを掴むのに役立ちます。 ※改正内容:給与所得控除最低保障額55万円 → 65万円に引き上げ。
年収100万円・120万円・150万円のケース別比較
※控除額合計は「給与所得控除+基礎控除」の合算値としています。他の控除(社会保険料控除・扶養控除等)は考慮していません。 この比較から、特に「年収120万円前後」の人にとって、改正による恩恵が大きいことが読み取れます。実際には住民税・社会保険料・手当等の影響も出るため、「手取りが○万円増える」という断定は避け、あくまで目安として提示しています。
どのくらい税負担が軽くなるのか具体例で解説
例えば年収150万円の場合、改正前は控除額103万円 → 課税所得47万円 → 所得税(5%前提)=約2.35万円。 改正後は控除額123万円 → 課税所得27万円 → 所得税=約1.35万円。 よって、概算で年約1万円強の税負担軽減効果が出る可能性があります。 拡大した基礎控除特例を含めたケースでは、さらに数万円の軽減もあり得ます。
この額は所得税のみの試算であり、住民税・社会保険料・手当の変化を含んだ「手取り増加額」ではもう少し変動します。 ただ、120万円〜150万円あたりの年収の人にとっては、税制改正の影響を実感しやすい範囲に入っています。
会社員・パート・学生アルバイトで違う実感
税制改正による効果は「立場」によって感じ方が変わります。以下のような違いが出やすいです。
🏢 会社員(フルタイム)
- 給与が大きめのため、控除アップの影響は比較的小さい
- 配偶者控除・扶養控除の改正と合わせてトータルで考える必要あり
👩💼 パート・アルバイト
- 年収100〜150万円あたりの人が最も恩恵を受けやすい
- 「もう少し働いても大丈夫」のラインが上がるため、就業時間を増やしやすくなる
🎓 学生アルバイト
- 扶養の対象となる年収上限の引き上げとあわせて、収入を増やしやすくなる
- 学費や生活費のためアルバイト時間を増やしても、税金や親の扶養への影響が減少
結論として、「年収120〜150万円」のパート・アルバイト層がもっとも“実感”を持ちやすいと言えます。会社員で年収400万円以上の人では控除アップ分の影響は相対的に小さくなります。 ただし、社会保険料の加入状況・扶養・住民税の非課税判定なども絡むため、手取りがどれだけ増えるかは人によって変わることを覚えておきましょう。
✅ ポイントまとめ:
給与所得控除2025改正では、控除額アップにより年収100万円〜150万円の働き手にとって目に見える手取り増加が期待できます。 特にパート・アルバイト・学生層は「もう少し働いても大丈夫」という安心感が生まれ、働き方の選択肢が広がるでしょう。
一方で会社員・高年収層では影響が小さめなので、全体像を把握した上で労働・税金のバランスを考えることが大切です。
👉 詳しくは 【年収別比較】給与所得控除2025改正で手取りはいくら変わる? で、年収100万・120万・150万円の実例シミュレーションをチェック!
給与所得控除2025改正と基礎控除の特例をセットで理解しよう
2025年の税制改正で、<給与所得控除の最低保障額引き上げ>と<基礎控除の引き上げ・特例創設>が同時に行われました。 この2つを単独で理解するのではなく、“セットで活かす”ことで節税効果を最大化できます。
ここでは、両者を併せて使うメリットと、年末調整時に気をつけるべきチェックリストを解説します。
両方の控除を活かすことで節税効果を最大化
2025年改正では、以下のように2つの控除がそれぞれ引き上げられています:
- 給与所得控除:最低保障額 55万円 → 65万円
- 基礎控除:48万円 → 58万円+所得に応じた上乗せ特例あり
このため、給与収入が少なめの人であれば「65万円+58万円=123万円分」控除ができるところが、さらに上乗せ特例があれば「95万円+65万円=160万円分以上」控除できるという構図も出てきています。つまり、“控除が二重に効く”ことで、働き手にとって節税メリットが大きくなるのが改正の肝です。
💡 実践メモ:
- 年収120万円あたりのパート・アルバイト層が最も恩恵を受けやすい。
- 住民税・社会保険料・扶養控除など他制度とあわせて設計すること。
- 控除額が多めになったからといって「収入をむやみに増やす=手取りアップ」ではなく、全体のバランスを見ることが重要です。
年末調整時に意識すべきチェックリスト
年末調整の実務で漏れてしまいやすいポイントを整理します。人事・総務担当者も、働く方自身も必ず確認しておきましょう。
📝 チェックリスト:
- 給与所得控除と基礎控除、両方の引き上げが反映されているか?
- 基礎控除の「上乗せ特例」が自分の所得(合計所得金額)に当てはまる範囲か確認。
- 年末調整用の書類(扶養控除等申告書・控除申告書)に新しい要件・金額が記載されているか。
- 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除額」が改正後の計算になっているか。
- ふるさと納税や配偶者控除・扶養控除など、他の控除との兼ね合いを整理しているか。
- 住民税や社会保険の影響(1年遅れの反映など)が、翌年にどう変わるかを理解しているか。
これらのチェックを「11月〜12月の年末調整準備期」に行えば、企業・個人ともにミスを防ぎやすくなります。 給与システムの早期改修・社内通知・個人の働き方見直しなど、“改正を前提に早めの対応”が鍵となります。
✅ ポイントまとめ:
「給与所得控除」と「基礎控除(特例含む)」をセットで理解することで、
① 控除額の底上げによる節税効果の増加
② 年末調整・確定申告での手続きミス回避 が期待できます。 2025年改正を最大限に“活かす”ために、今のうちからチェックリストを用いて準備を進めましょう。
給与が2か所以上ある方や副業収入がある方は、
2025年以降は確定申告が必要になるケースが増えます。
損せず正しく申告するポイントをまとめています👇
まとめ:給与所得控除2025改正で知っておくべきポイント総整理
ここまで見てきたように、2025年の給与所得控除改正は「物価高対策」「働き方支援」「税負担の公平化」を目的に、働くすべての人に影響を与える重要な制度変更です。
最後に、改正内容の要点と実務でのチェックポイントを整理し、2025年以降に備えるための指針をまとめます。
いつから・誰が・何に気をつけるべきか
- 施行時期:2025年12月の年末調整から適用。住民税は2026年度分から反映。
- 対象者:すべての給与所得者(会社員・パート・アルバイト・学生を含む)。
- 注意点:扶養・配偶者控除の基準も58万円に変更されるため、世帯単位での見直しが必要。
特に年収120〜150万円前後の層では、手取り額や扶養判定に大きな変化が生じるため、 早めに勤務先や税理士へ相談し、年末調整書類の記入を誤らないようにしましょう。
控除拡大で働き方の選択肢が広がる
👩💼 パート・主婦層
103万円→123万円の非課税ライン引き上げにより、「もう少し働ける」安心感が広がる。 時間延長・副業・ダブルワークを検討しやすくなります。
🎓 学生アルバイト
学生扶養特例が150万円まで拡大。学費や生活費を賄うためのアルバイト時間を増やしても扶養範囲内に収まるケースが増えます。
🏢 会社員・フルタイム層
控除アップの影響は相対的に小さいが、配偶者控除・基礎控除特例との併用で世帯全体の手取りが改善します。
これらの変化は単なる税制上の改正にとどまらず、「働く選択肢の自由化」につながります。 政府が目指す「柔軟な就労環境」と「家計支援」の両立に向けた大きな一歩といえるでしょう。
給与所得控除2025改正の全体像を一目で理解する
| 項目 | 改正前 | 2025年改正後 | 主な影響 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 | 最低55万円 | 65万円へ引き上げ | 低所得層の課税回避範囲が拡大 |
| 基礎控除 | 48万円 | 58万円+所得連動特例 | 高所得層の段階的縮小を明確化 |
| 非課税ライン | 103万円 | 123万円(新基準) | パート・学生がより働きやすく |
| 住民税反映 | 2025年度 | 2026年度 | 1年遅れで自治体課税へ反映 |
以上をまとめると、今回の改正は「低〜中所得層への実質的な支援策」であり、同時に「働き方の柔軟化」を促す政策的な意味合いが強いと考えられます。 今後の税制改正や社会保険料制度とも連動していくため、年末調整・確定申告時に最新の制度情報を確認することが重要です。
✅ 最終まとめ:
・改正の施行は2025年12月、住民税反映は翌2026年。
・給与所得控除+基礎控除特例で最大123万円〜160万円の控除効果。
・特にパート・アルバイト・学生層に大きな恩恵。
・世帯単位での税金・扶養バランス見直しが必要。
・制度を正しく理解し、年末調整・確定申告の準備を早めに進めよう。
🔁 【関連記事】給与所得控除の基本や仕組みをもっと詳しく知りたい方は、
👉 【保存版】給与所得控除とは?初心者向けにわかりやすく説明 もあわせてご覧ください。

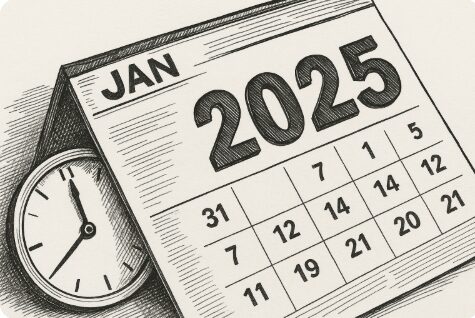
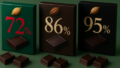

コメント