【簡単まとめ】給与所得控除2025改正と住民税の反映時期をサクッと理解
「給与所得控除の改正って、住民税にはいつから効いてくるの?」 そんなギモンを、反映される年度のズレと98万円→108万円ラインを軸に、 パート・アルバイト・学生・フリーランスまでわかりやすく整理します。
「給与所得控除が2025年に変わるらしいけど、住民税っていつから変わるの?」──多くの人がここでつまずきます。
ニュースを見ても仕組みが複雑で、結局「自分の住民税はいくらになるの?」がわからないまま不安だけが残りがちです。
特にパート・アルバイト・学生の方は、年収のちょっとした差で手取りが大きく変わるので、この“タイミングのズレ”がかなり気になりますよね。
実は、給与所得控除の改正と住民税は同じ年に動くわけではなく、自治体ごとの反映時期にも特徴があります。
知らずにいると「思ったより住民税が高い…」と後から驚くことも。
この記事では、改正内容が住民税にいつ反映されるのかを、自治体ごとの流れまで含めてやさしく整理。
モヤモヤした不安をスッキリ解消し、手取りを最適化できる判断材料をまるごとお届けします。
■ 記事のポイント
- 給与所得控除2025改正の概要
- 住民税へ反映される年を解説
- 98万→108万円ラインの整理
- 働き方別の住民税の注意点
- ムダな住民税を防ぐチェック
【関連記事】まず基本を確認したい方へ▼▼▼
給与所得控除の仕組みから2025改正の全体像まで、基礎をまとめた解説はこちら
ここから下の解説では主に「住民税への反映タイミングと非課税ライン」にしぼって解説しています。
- ① 給与所得控除2025改正と住民税の関係をやさしく整理
- 復習 基礎解説の復習:給与所得控除の意味を一言でおさらい
- POINT 2025年の給与所得控除改正は何が変わる?初心者向けざっくり解説
- Q2 住民税の給与所得控除額はいくら?所得税との違いを整理
- Q3 住民税の「給与所得控除後の金額」とは?源泉徴収票とのつながり
- Q4 基礎控除と住民税の関係:43万円+給与所得控除で決まる土台
- Q5 「98万円の壁」は本当に合っている?住民税非課税ラインの正体
- Q6 2025年改正後は「108万円の壁」に?住民税非課税ラインの変化
- Q7 県民税と市民税で給与所得控除の計算は違う?仕組みをかんたん整理
- Q8 住民税と所得税の給与所得控除を比較:どこが同じでどこが違う?
- Q9 給与控除と住民税の関係を一言でまとめるとどうなる?
- ②住民税に給与所得控除が反映されるタイミングと注意点
- Q10 住民税は前年の所得で決まる仕組みをやさしく解説
- Q11 給与所得控除2025改正が住民税に反映されるのはいつから?
- Q12 主要都市別スケジュール:東京・大阪・名古屋・福岡の住民税の流れ
- Q13 給与収入98万円だと住民税はいくら?具体例でイメージする
- Q14 給与所得控除改正後の「108万円前後」の住民税をざっくりシミュレーション
- Q15 住民税の給与所得控除計算をステップで確認【初心者向け】
- Q16 住民税は年末調整で返ってくる?よくある誤解と正しい理解
- Q17 パート・アルバイト・学生・フリーランス別:住民税で気をつけたいポイント
- Q18 《まとめ》給与所得控除と住民税の反映・非課税ラインを総整理
① 給与所得控除2025改正と住民税の関係をやさしく整理

2025年の給与所得控除の改正は、ニュースやSNSでも大きな話題になっています。
しかし「住民税にはいつ反映されるの?」「結局いくらまで稼ぐと非課税なの?」という点は、意外と分かりにくくて混乱しやすい部分です。
この章では、給与所得控除の基本から、住民税とどうつながるのか、2025年改正で何がどう変わるのかを初心者でも理解できるようにやさしく整理していきます。
まずは「給与所得控除ってそもそも何?」というポイントから確認していきましょう。
- 給与所得控除を「一言で説明するとこうなる」というイメージ
- サラリーマン・パート・アルバイトにとって何がうれしい仕組みなのか
- 細かい制度の中身を知りたいとき、どのページを読めばいいか
復習 基礎解説の復習:給与所得控除の意味を一言でおさらい
「給料からの自動の引き算=みなし経費」というイメージだけ押さえる
給与所得控除を一言でいうと、 「サラリーマン・パート・アルバイトのために、国が自動で引いてくれる“みなし経費”」 のようなイメージです。
実際に働くときは、
- 通勤にかかる交通費(定期代以外の細かい出費など)
- 仕事用のスーツ・かばん・靴などの購入費
- 自宅での下調べや勉強にかかる時間やコスト
…といったお金や手間が本当はいろいろかかっています。でも、それを 1つ1つ領収書で申告するのは現実的ではありません。 そこで国が「だいたいこれくらいは仕事のための経費だよね」という金額をあらかじめ決めておき、 お給料から自動的に“経費分”を引いてくれる仕組みが、給与所得控除です。
💡 一言まとめ
「お給料 - 給与所得控除 = 税金の計算に使う“所得”」 くらいのイメージでOKです。
「税金をかける前に、あらかじめ一定額を引いてくれている仕組み」と覚えておくと、あとで住民税の話もスッと理解しやすくなります。
詳しい仕組みは基礎解説ページへ:読み進め方ガイド
給与所得控除のルール自体は、年収に応じて細かい計算式や段階的な表が決まっています。 「2025年の改正で、どの年収帯がいくら変わるのか」まで追いかけると、どうしても専門的な内容になってしまいます。
そこでこのページでは、“イメージの理解”に集中し、 もっと詳しく知りたい方向けには、別の基礎解説ページでじっくり読めるようにしています。
- 年収ごとの給与所得控除額の一覧・早見表をチェックしたい
- 2020年・2025年の税制改正で何がどう変わったか知りたい
- 自営業との違い(実費の経費 vs 給与所得控除)を詳しく比較したい
- 給与所得控除と基礎控除・扶養控除などの全体像を整理して理解したい
おすすめの読み方
- まずはこのページで「給与所得控除=自動の引き算」というイメージをつかむ
- もっと詳しい制度の中身は、給与所得控除の基礎解説ページで確認する
- 年収別の手取りや“壁”の影響は、シミュレーション用の記事をあわせて読む
【保存版】給与所得控除とは?初心者向けにわかりやすく説明
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除は「お給料から自動で引いてくれる、みなし経費のようなもの」
- 「お給料 − 給与所得控除 = 税金計算に使う所得」というイメージが持てればOK
- 細かい金額や計算式・改正の歴史は、基礎解説ページでじっくり確認すれば十分
POINT 2025年の給与所得控除改正は何が変わる?初心者向けざっくり解説
2025年の税制改正では、「給与所得控除が10万円アップする」という点が大きな話題になっています。 ただ、「自分の年収だとどう影響するの?」「住民税はいつから変わるの?」といったところまでは、ニュースではなかなか深掘りされません。
ここでは、細かい計算式は一旦おいておき、 「最低控除額が55万円→65万円になるってどういうことか」と 「なぜ所得税と住民税で反映されるタイミングがズレるのか」を、イメージ重視でかんたんに整理していきます。
最低控除額が55万円→65万円になる範囲とは?
給与所得控除には、年収に応じた計算式のほかに、「これ以下にはならない」という最低ラインが設定されています。 現行制度ではこの最低額がおおむね55万円ですが、2025年以降は65万円に引き上げられる方向で議論されています。
📊 「最低控除額」が上がるイメージ
| 制度 | 最低控除額 |
|---|---|
| 改正前(〜2024年分) | 55万円 |
| 改正後(2025年分〜) | 65万円 |
ポイントは、この「最低額」に引っかかるゾーンの人ほど影響が出やすいということです。 年収が低めのパート・アルバイト・学生バイトなどでは、 「お給料から引いてもらえるみなし経費が10万円分増える」イメージになり、 その分だけ税金の土台になる金額が小さくなる方向に働きます。
具体的にどの年収までが「最低65万円」の対象になるかは、最終的には国の告示や最新の速算表で確認する必要があります。 現時点では、「低〜中所得層を中心に、負担をやわらげるための見直しが入る」と理解しておくとイメージしやすいです。
💡 結論:最低控除額が55→65万円に上がる=「税金をかける前の引き算」が大きくなる → 特に年収がそれほど高くない人ほど、所得税・住民税の負担が少し軽くなる方向に働きます。
所得税と住民税で「いつから」がズレる理由
給与所得控除の改正自体は同じタイミングで行われますが、 実際に税金の額が変わる「年」は、所得税と住民税でズレて見えます。 これは、それぞれの税金の「計算の基準となる年」が違うからです。
🕒 ざっくりタイムライン
- 所得税:その年の収入に対する税金を、その年の年末調整・確定申告で精算 (例:2025年の給与 → 2025年の年末調整で反映)
- 住民税:前年の所得をもとに、翌年6月から1年間かけて徴収 (例:2025年の所得 → 2026年6月〜2027年5月頃までの住民税に反映)
| 税金の種類 | 給与所得控除改正の反映タイミング |
|---|---|
| 所得税 | 2025年分の給与から新しい控除額で計算 → 2025年の年末調整・確定申告で反映 |
| 住民税 | 2025年の所得をもとに2026年度分の住民税を計算 → 2026年6月以降の住民税(給与からの天引きや納付書)に反映 |
このズレのせいで、「ニュースでは2025年から軽くなると言っていたのに、手元の住民税はすぐには変わらない」 という感覚が生まれやすくなります。 仕組みとしては、 「所得税は当年」「住民税は翌年」と覚えておけばOKです。
💡 まとめ: 給与所得控除が増えても、「所得税はすぐ」「住民税は1年後」に効いてくるイメージです。 通知書や給与明細を見るときは、「これは前年の所得に対する住民税かどうか?」を意識して確認すると、モヤモヤが減ります。
✅ このパートのまとめ
- 2025年改正では、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられる方向になっている。
- 最低控除額が上がるほど、「税金をかける前の引き算」が大きくなり、特に年収が高くない人の負担を軽くする効果が期待できる。
- 所得税はその年の年末調整・確定申告、住民税は翌年度の6月以降に反映されるため、「いつから変わるのか」がズレて見える点に注意。
Q2 住民税の給与所得控除額はいくら?所得税との違いを整理
「給与所得控除が増えると聞いたけれど、住民税のほうではいくら控除されているの?」 「所得税の計算と同じなのか、それとも別のルールがあるのか?」と気になっている方も多いと思います。
実は、住民税の給与所得控除は基本的に所得税と同じ計算式をベースにしています。 ただし、住民税には税率の決め方や“均等割”という独自の部分もあり、 「控除の考え方そのものはほぼ同じだけれど、最終的な税額の出方はちょっと違う」というイメージを持っておくのが大切です。
「住民税の給与所得控除」は基本的に所得税と同じ計算式
まず押さえておきたいのは、住民税だけ特別な「給与所得控除額」があるわけではないという点です。 多くの自治体では、所得税の給与所得控除と同じ速算表・計算式をもとに、住民税の計算にも同じ控除額を使っています。
📌 イメージ:同じ「給与所得控除額」を2つの税金で共通利用
- ① 給与収入(年収)から、給与所得控除を引いて「給与所得」を出す
- ② その給与所得をもとに、所得税の金額を計算
- ③ 同じ給与所得をもとに、住民税の金額も計算
つまり、「住民税の給与所得控除額はいくらですか?」という質問に対しては、 基本的には「所得税の給与所得控除額と同じ額です」と答えるのがイメージとして近いと考えられます。
ただし、実際には自治体ごとの条例で細かい扱いが定められているため、 「◯◯市だけ独自の計算式がある」といった例外がまったくないとまでは言い切れません。 現時点で広く公表されている情報ベースでは、 多くの自治体が国の給与所得控除のルールに沿って住民税も計算していると考えられます。
⚠️ 注意: 具体的な速算表や条例の文言は自治体ごとに定められているため、
「自分の自治体の住民税について正確な金額を知りたい場合」は、
市区町村のホームページやしおりで最新情報を確認するのが安全です。
住民税だけで見るときの注意点:税率・控除の考え方のちがい
給与所得控除そのものは所得税と共通でも、住民税は「税率の決め方」と「控除の反映のされ方」が少し違うため、 「同じ給与所得でも、所得税と住民税の金額はかなり感覚が違うな」と感じることがよくあります。
🧾 所得税と住民税のざっくり構造の違い
| 項目 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 税率のイメージ | 超過累進税率 所得が増えるほど税率も段階的にアップ | 多くの自治体で一律10%程度(都道府県+市区町村の合計) + 均等割(一定の定額部分) |
| 控除の使われ方 | 給与所得控除+基礎控除などを引いたあと、 残りの所得にその人の税率をかける | 基本は所得税と同じ控除をベースにしつつ、 一律に近い税率で税額を計算する |
| 非課税ライン | 国のルールに基づき、 所得税がかからないゾーンが決まる | 自治体の条例で、住民税の非課税条件が細かく定められている |
このように、「どの控除をいくら使うか」という大枠は所得税と似ているものの、 住民税は税率がほぼ一定+均等割ありという特徴があるため、 同じ給与所得控除額でも「税額への効き方」が所得税とは少し違うと感じる場面が出てきます。
💡 ポイント: 住民税を考えるときは、「給与所得控除そのもの」よりも、
「その結果として出てくる所得金額に一律に近い税率をかける税金」だというイメージを持つと整理しやすくなります。
✅ このパートのまとめ
- 住民税の給与所得控除額は、基本的に所得税と同じ計算式・金額をベースにしていると考えてよい。
- 同じ給与所得控除額を使っていても、税率の仕組み(所得税は累進・住民税はほぼ一律+均等割)が違うため、税額の出方は変わる。
- 「自分の住民税の控除や非課税条件を正確に知りたい」場合は、住んでいる自治体の最新情報を確認するのが安心。
Q3 住民税の「給与所得控除後の金額」とは?源泉徴収票とのつながり
住民税は「前年の所得」をもとに計算されますが、そのスタート地点になるのが 「給与所得控除後の金額」= 給与所得です。 この金額は源泉徴収票にも書かれており、住民税とのつながりを理解すると「住民税がどう決まっているのか」が一気に見やすくなります。
ここでは、給与収入から住民税の課税額が算定されるまでの流れと、源泉徴収票で確認すべき箇所を初心者向けに整理します。
給与収入→給与所得控除→給与所得→住民税の課税対象までの流れ
住民税の計算は“給与収入のまま”行われるのではなく、いったん 給与所得控除によって「働くための必要経費」を引いた金額=給与所得 に変換されたうえで計算されます。
📘 給与から住民税の課税対象までのシンプルな流れ
- ① 給与収入(年収)
- ↓ 給与所得控除(年収に応じた自動の引き算)
- ② 給与所得(=給与所得控除後の金額)
- ↓ 基礎控除・扶養控除など住民税用の控除を反映
- ③ 住民税の課税所得 → この金額に税率(10%前後)+均等割を適用
この「② 給与所得(給与所得控除後の金額)」が、住民税計算の“入口”となるため、 この数字を正しく理解しておくと、翌年の住民税金額が予測しやすくなるというメリットがあります。
💡 コツ: 住民税は「給与所得控除後の金額」→「住民税の所得控除」→「課税所得」という3ステップで決まるため、 “控除がどれだけ効いているか”を見るのがポイントです。
源泉徴収票で住民税に関係する数字はどこに書かれている?
住民税の計算で使われる「給与所得控除後の金額」は、じつは 源泉徴収票の中にしっかり記載されています。 ただ、名前がそのまま「給与所得控除後の金額」とは書かれていないため、見落としやすいポイントです。
📄 源泉徴収票でチェックするべき欄(よく使う2か所)
- ①「給与所得控除後の金額」欄
住民税の計算で使う「給与所得」の数字がそのまま記載されている欄。 - ②「所得控除の額の合計額」欄
基礎控除・扶養控除など、住民税でも使う控除の合計額がここに反映される。
住民税は前年の源泉徴収票の数字をもとに計算されるため、 自分がどこに該当しているかを知りたい場合、まずは源泉徴収票を見るのが一番早い方法です。
💡 ポイント: 住民税の課税額は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」+「各種所得控除」で決まるため、 源泉徴収票の確認が「翌年の住民税を予測するための基礎資料」になります。
✅ このパートのまとめ
- 「給与所得控除後の金額」は住民税計算の最初の基礎となる金額(=給与所得)。
- 源泉徴収票では専用の欄に数字が記載されており、住民税の算定に直結している。
- 自分の住民税の金額を予測したいときは、まず源泉徴収票の該当欄をチェックするのが最速。
Q4 基礎控除と住民税の関係:43万円+給与所得控除で決まる土台
住民税は「前年の所得」をもとに計算されますが、その最初の大きなハードルになるのが 基礎控除(住民税は43万円)です。 そして、ここに給与所得控除が加わることで、「どこから住民税がかかるか」が決まります。
ここでは、住民税の基礎控除と、所得税とのちがい・よくある勘違いを初心者向けに整理していきます。
住民税の基礎控除はいくら?所得税との金額差をやさしく解説
実は、基礎控除は「所得税」と「住民税」で金額が違うという点が、よく混乱されるポイントです。
| 種類 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 所得税 | 48万円(2025年は58万円へ拡大) |
| 住民税 | 43万円(2025年は53万円へ拡大) |
このように、住民税の基礎控除は所得税より5万円低いのが基本ルールです。
そのため、たとえば「所得税はかからないのに住民税だけかかる」というケースが起きるのは、 この控除額の差(5万円)が理由のひとつです。
⚠️ ポイント 住民税のほうが控除額が低いため、 「実質的な非課税ラインが所得税より厳しめ」という特徴があります。
「基礎控除と住民税」でよくある勘違いと確認ポイント
基礎控除はシンプルに見えて、実際は勘違いが多い項目です。 特に「所得税で非課税なら住民税もゼロ」と思ってしまうのは注意が必要です。
❌ よくある勘違い
- 「所得税がゼロなら住民税もゼロになる」 → 基礎控除額が違うため、住民税だけ課税されるケースは普通にあります。
- 「住民税の基礎控除は全国で同額」 → 基本は同じですが、条例で細かい適用条件が異なる自治体もあります。
- 「基礎控除さえあれば非課税になる」 → 実際には「均等割」「所得割」の2種類があり、後者にだけ影響します。
また、住民税は「前年所得」で計算され、「均等割(定額部分)」と「所得割(所得に応じた部分)」で構成されているため、 基礎控除は所得割にしか直接影響しないという点も忘れがちです。
💡 確認ポイント: 住民税を正しく理解するには、 「基礎控除43万円」+「給与所得控除」+「住民税の税率(10%前後)」 という3つのセットで考えるとスッキリ整理できます。
✅ このパートのまとめ
- 住民税の基礎控除は43万円(2025年は53万円)で、所得税より5万円低い。
- 「住民税だけ課税される」現象は、基礎控除の差が主な理由。
- 基礎控除だけで非課税になるわけではなく、均等割と所得割の2種類で住民税が決まる点を理解しておくことが重要。
Q5 「98万円の壁」は本当に合っている?住民税非課税ラインの正体
SNSや解説記事でよく登場する「98万円の壁」。 これは住民税がかからなくなるラインとして広く知られていますが、 「本当に98万円で合っているの?」という疑問を持つ方も多いポイントです。
この98万円という数字の正体は、住民税の基礎控除43万円と 給与所得控除55万円を合計した控除の合計額から生まれています。 ただし、すべての人に等しく当てはまるわけではありません。
給与所得控除55万円+基礎控除43万円=98万円になる理由
住民税には最初から控除される2つの金額があります。
- 給与所得控除:55万円
- 基礎控除:43万円
この2つを合計すると、 55万円+43万円=98万円 となり、これが一般に言われる 「住民税非課税になる収入の目安」 となります。
つまり、給与収入が98万円以下なら「給与所得」が0円になるため、 「所得割(住民税の“所得に応じた部分”)」がかからないという仕組みです。
⚠️ 注意: 住民税は「均等割(定額部分)」があるため、 正確には「所得割がゼロになるライン」の話になります。
「住民税 98万円の壁」はどんな人に当てはまるのか
実は「住民税の98万円ライン」は、 すべての人に共通ではありません。 当てはまるのは主に以下のケースです。
✔ 当てはまりやすい人の特徴
- 扶養に入っている学生・パートの方
- アルバイトの給与収入が年間100万円未満の方
- 働く時間をコントロールしている主婦(夫)
- 住民税の所得割だけをゼロにしたい人
❗ よくある勘違い
- 「98万円以下なら住民税は完全にゼロ」 → 実際には均等割(定額)がかかる可能性があり。
- 「扶養に入っていれば自動で非課税」 → 扶養の有無は住民税非課税ラインとは直接関係しません。
また、自治体によっては独自に非課税基準を上乗せしている場合もあります。 自治体の「非課税」説明ページをチェックすることが最も確実です。
✅ このパートのまとめ
- 「98万円の壁」は給与所得控除55万円+基礎控除43万円の合計が根拠。
- このラインで住民税の所得割がゼロになる。
- ただし、均等割は別で、完全にゼロになるとは限らない。
Q6 2025年改正後は「108万円の壁」に?住民税非課税ラインの変化
2025年以降、給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられる見込みであることから、 「住民税の非課税ラインが約108万円になる」という計算式も見かけるようになりました。
ただし、実際には自治体ごとに扱いが異なったり、非課税となる“基準”が複数あるため、 この108万円という数字はあくまで「ざっくり目安」として理解しておくのが安全です。
給与所得控除65万円+基礎控除43万円でどこまで非課税になる?
改正後において、給与収入が主な収入源の人が“住民税の所得割がゼロになる目安”として、 給与所得控除65万円+基礎控除43万円=108万円という数式が紹介されていることがあります。
つまり、年間の給与収入が「おおむね108万円以下であれば」、 その年の翌年分の住民税(所得割部分)について、非課税となる可能性が高いという計算例です。
ただし、この計算には“他の所得がない”“控除が基礎控除だけ”という前提が含まれており、 交通費・副収入・扶養の状況・自治体ルールによっては該当しないこともあります。
⚠️ 注意: 「108万円以下で絶対非課税」ではありません。 実際には扶養・勤労学生控除・自治体ごとの非課税要件が影響します。
「給与所得控除と住民税非課税」について
「給与所得控除と住民税非課税」との関係については次のような項目を押さえておきましょう:
- その年の給与収入がいくらまでなら住民税の所得割がかからないか
- 給与所得控除65万円がいつから適用されるか
- 住民税の非課税判定に扶養・勤労学生控除などがどう影響するか
- どの自治体でも「108万円」が当てはまるかどうか(地域差)
- 住民税以外に「均等割」もあることの意味と課税される可能性
これらのポイントを押さえておくことで、簡単に「自分は今年これ以上働いたら住民税が発生しそうか?」という目安が持てます。
💡 確認ポイント: 年収を確認したときには、「給与収入−給与所得控除65万円−基礎控除43万円」という計算式を使って、 おおまかに「住民税の所得割が出るかどうか」を判断できるようになります。
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除65万円+基礎控除43万円=約108万円という「住民税の所得割ゼロの目安」が紹介されています。
- ただし、住民税の課税には均等割・扶養・自治体ルールなどが関わるため、 必ずしも108万円以下で“完全に非課税”になるわけではありません.
- わからない時は、住んでいる自治体の税務課または公式サイトで「住民税非課税要件」を確認するのがおすすめです。
「住民税がゼロの人がいる世帯=非課税世帯」ではなく、
世帯全員が非課税になる条件や、年金世帯・パート収入がある場合の考え方などを、 やさしく図解でまとめています。
Q7 県民税と市民税で給与所得控除の計算は違う?仕組みをかんたん整理
「県民税と市民税で給与所得控除の計算って違うの?」という質問はとても多いのですが、 結論からいえば給与所得控除のルールは全国で統一されています。
一方で、税額そのものは自治体ごとに少し違うため、「計算が違うように見える」ことがあります。 その理由は、控除ではなく均等割と税率にあります。
県民税・市民税とも「給与所得控除のルールは全国共通」
給与所得控除は、国税庁が定めた国の統一ルールです。 そのため、
- 北海道でも沖縄でも同じ控除額
- 県民税・市民税とも同じ計算式を使用
- 会社の年末調整でも日本全国共通
給与所得控除が自治体ごとに変わることは一切ありません。 そのため、「県民税だけ計算式が違う?」という心配は不要です。
違いが出るのは控除ではなく「均等割」と「税率」の部分
自治体ごとに違いが生じるのは、給与所得控除ではなく下記の部分です:
- 均等割(住民税の「定額部分」) → 500円〜1000円程度の違いが自治体で発生。
- 税率(住民税の10%部分) → 基本は全国同じ10%(市民税6%・県民税4%)だが、 一部で条例加算がある自治体も。
💡 ポイント: 「給与所得控除が違うように見える」= 実際には税率と均等割の差が理由で、控除計算は全国同じです。
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除は全国どこでも同じルール。
- 自治体で変わるのは「均等割」「税率」などの住民税独自部分。
- 「計算が違うように見える」のは控除ではなく税額の違いが原因。
Q8 住民税と所得税の給与所得控除を比較:どこが同じでどこが違う?
「住民税と所得税の給与所得控除って本当に同じなの?」という質問はとても多く、 初心者が混乱しやすいポイントの一つです。 結論だけ言うと給与所得控除の“計算式”そのものは完全に同じです。
ただし、税金の仕組み全体で見ると控除以外の部分に違いがあり、 そこで「金額がズレる」ように見えるケースが出ます。
「住民税 所得税 給与所得控除」のよくある疑問を整理
多くの人がつまずくポイントを整理すると次の3つになります。
- 給与所得控除の計算式は同じなのに税額は違う
- 住民税のほうが控除額が低いと思い込んでしまう
- 「非課税ライン」が所得税と住民税でズレる理由がわからない
実際には、給与所得控除は国が定める統一ルールなので違いはありません。 では、何が違うのか? → その答えが右側です。
控除の仕組みは同じでも、基礎控除や税率が違う点に注意
給与所得控除は同じでも、次の項目が違うため結果に差が出ます。
- 基礎控除額 ─ 所得税は48万円(2025年改正で58万円)、住民税は43万円(自治体による)
- 税率 ─ 所得税は5%〜45%、住民税は一律10%(均等割を除く)
- 非課税ライン ─ 控除の組み合わせで所得税と住民税の「税金ゼロ」の境目が変わる
💡 結論: 給与所得控除は同じでも、基礎控除・税率・非課税ラインが違うため、 「住民税のほうが税金が高い/安い」という現象が起こります。
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除の“計算式”は所得税も住民税も全国共通。
- 違いが出るのは基礎控除・税率・非課税ラインの部分。
- この差が「住民税だけ金額が違う」ように感じる原因になる。
Q9 給与控除と住民税の関係を一言でまとめるとどうなる?
給与所得控除と住民税の関係を一言でいうと、 「控除が大きいほど、住民税にかかる“課税対象”が小さくなる」 というシンプルな構造です。
つまり、給与所得控除が増えるほど住民税の負担が軽くなり、 最終的には手取りが増える方向に働きます。 この流れを図解イメージでわかりやすく整理します。
給与控除が大きくなるほど、住民税の課税所得は小さくなる
給与所得控除は「収入から差し引けるみなし経費」です。 控除が増えると、住民税の計算に使う課税所得が小さくなります。
給与収入
↓(給与所得控除)
給与所得(住民税の計算の土台)
↓(基礎控除ほか)
住民税の課税所得
この課税所得が小さくなるほど、住民税が減るため、 給与所得控除の引き上げ(2025改正)は多くの人に恩恵があります。
「住民税の負担が軽くなる=手取りが増える」までのつながり
給与所得控除が増える → 課税所得が下がる → 住民税が軽くなる この連鎖が最終的に手取りアップにつながります。
💡 つながりイメージ:
控除↑ → 課税所得↓ → 住民税↓ → 手取り↑
特に年収100万〜150万円のゾーンでは、少しの控除差で手取りが大きく変わることも。 2025年改正はこの層にとってメリットが大きいと考えられます。
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除が大きいほど住民税の課税所得は小さくなる。
- 課税所得が小さい=住民税が軽くなる仕組み。
- 結果として「控除アップ→手取りアップ」の流れが成り立つ。
※全体像をおさえたい方はこちらの関連記事へ▼▼▼
②住民税に給与所得控除が反映されるタイミングと注意点

住民税は“その年の収入”ではなく、“前年の所得”をもとに決まる仕組みです。
そのため、2025年の給与所得控除の改正も、実際に住民税へ反映されるのは翌年以降になります。このタイムラグがあるせいで、「反映はいつ?」「私の住民税はどう変わるの?」と迷う人も多いはず。
この章では、2025年改正が住民税に反映される具体的なタイミングや、東京・大阪・名古屋・福岡など主要都市のスケジュール、さらに98万円→108万円の非課税ラインの変化について、実例を交えて分かりやすく解説します。
Q10 住民税は前年の所得で決まる仕組みをやさしく解説
一見すると「給与所得控除が変わったのに、住民税がすぐ変わらない…?」と 不思議に感じてしまうかもしれません。 でもこれ、仕組みを理解するととてもシンプルで、 住民税は“前年の所得”をもとに計算されるためです。
給与所得控除が変わる年と、住民税が変わる年がズレる理由
給与所得控除は給与を受け取った年の所得税の計算にすぐ反映されます。 一方で住民税は、各自治体が翌年にまとめて計算するため、次のような“タイムラグ”が発生します。
- 給与所得控除は「その年の所得税」に即反映
- 住民税は「前年の所得」で次年度にまとめて計算
- そのため控除改正 → 住民税反映まで1年ズレる
この仕組みが、2025年の給与所得控除改正が2026年度の住民税に反映される理由です。
「2025年の給料→2026年度の住民税」という基本の流れ
タイムラグのイメージがもっとわかりやすくなるように、 「給与を受け取る年」と「住民税が決まる年」をシンプルに整理します。
📌 時系列の基本:
2025年の給与 →(年末調整)→ 2025年の所得税に反映
↓
翌年の6月から始まる 2026年度住民税 に反映
✅ ポイントまとめ:基本の流れを押さえれば迷わない
- 住民税は前年の所得をもとに自治体が翌年に一括計算。
- 給与所得控除が変わる年と住民税が変わる年は必ず1年ズレる。
- 「2025年の給料→2026年度の住民税」という流れが基本。
Q11 給与所得控除2025改正が住民税に反映されるのはいつから?
給与所得控除の2025年改正は、働く人すべてに影響する大きな変更です。 ただし、所得税と住民税では反映されるタイミングが異なります。 どちらの税金にいつ影響が出るのか、ここで明確に整理しておきましょう。
所得税は2025年分から、住民税は2026年度分からスタート
給与所得控除は2025年1月〜12月に受け取る給与から新ルールが適用されます。 そのため、所得税への影響は2025年の年末調整で反映されます。
🗓 反映タイミング
・所得税 → 2025年の年末調整で反映
・住民税 → 2026年6月スタートの住民税から反映
住民税は「前年の所得で決まる」仕組みのため、必ず1年遅れで反映される点がポイントです。
「給与所得控除と住民税」 改正で押さえるべき年の見方
「いつの給与が、どの年の住民税に影響するのか?」 よくある混乱ポイントを、シンプルな“セットの法則”にまとめました。
📌 押さえるべきセットの法則
・2025年の給与 → 2025年の所得税 → 2026年度の住民税
・2024年の給与 → 2024年の所得税 → 2025年度の住民税
このように、住民税は必ず翌年の6月から反映されるのがポイントです。
そのため、「給与所得控除と住民税 」で迷いやすい “何年→何年”の対応関係をしっかり把握しておくことが大切です。
✅ このパートのまとめ
- 給与所得控除の改正は2025年の給与から適用。
- 所得税は2025年分、住民税は2026年度分から反映。
- 「前年の所得で住民税が決まる」仕組みを理解すれば迷わない。
Q12 主要都市別スケジュール:東京・大阪・名古屋・福岡の住民税の流れ
住民税は「前年の所得で決まる」「6月〜翌年5月に納める」という全国共通ルールで動いています。 とはいえ、主要都市では通知のタイミングや案内の出し方に細かな違いがあります。 ここでは東京・大阪・名古屋・福岡を例に、その流れを整理していきます。
東京都・政令市に多い「翌年6月から給与天引き」が基本パターン
東京23区や政令指定都市では、住民税は翌年の6月から翌々年5月までを1年度として、 給与からの特別徴収(天引き)で支払う構造が一般的です。
📌 基本の流れ(東京・大阪などの政令市)
・前年の給与で税額が決まる
・6月に「住民税決定通知書」が会社へ届く
・6月給与から天引きスタート
主要都市ではこの仕組みが定着しており、会社員であれば特別な手続きをする必要はありません。
東京23区・大阪市・名古屋市・福岡市の通知タイミングの違い
住民税の開始時期は全国同じ「6月」ですが、通知書の発送タイミングには自治体ごとに少しズレがあります。 主要都市で比較すると、次のような特徴があります。
| 都市 | 通知時期の傾向 |
|---|---|
| 東京23区 | 5月下旬〜6月上旬に企業へ通知 |
| 大阪市 | 5月末ごろが多い |
| 名古屋市 | 年によって前後するが概ね5月下旬 |
| 福岡市 | 6月頭に届くケースが比較的多い |
いずれも6月スタートという点は変わらないため、通知が多少前後しても税額そのものには影響しません。
自治体によって違うのは「スケジュール」よりも「お知らせ方法」
実は違いが出やすいのはスケジュールではなく、 通知書の送り方・名称・会社と本人のどちらに届くかといった“運用面”です。 とくに政令指定都市は会社宛てに「特別徴収税額決定通知書」をまとめて送る方式が多く、 本人へ届くタイミングが都市ごとに微妙に異なります。
Q13 給与収入98万円だと住民税はいくら?具体例でイメージする
「給与収入が98万円だと、住民税はどうなるの?」という疑問は非常に多いです。 この金額には、実は“住民税がかかる・かからない”の分かれ目という重要な意味があります。 初心者でも流れがつかみやすいように、計算の仕組みを具体例で整理していきます。
98万円のときの給与所得控除・基礎控除・課税所得の流れ
給与収入98万円という金額は、次のように「控除の合計=98万円」とほぼ一致するため、 課税所得が0円になり、住民税が非課税になる可能性が高いラインです。
【給与収入98万円の計算の流れ(住民税)】
- 給与収入:98万円
- 給与所得控除:55万円(※2024年度基準)
- 基礎控除:43万円(住民税の基礎控除)
- 98万円 −(55万円+43万円)= 0円 → 課税所得ゼロ
そのため、ほとんどの自治体では住民税が非課税(所得割なし)となります。
所得割ゼロ・均等割だけ、というケースの考え方
課税所得が0円になると、所得割(税率がかかる部分)は0円になります。 ただし、住民税にはもう一つ「均等割」があり、こちらは自治体ごとに独立して課税されます。
均等割は「住民税の基本料金」のようなイメージで、 所得に関係なく決まった金額が発生します。
※ただし、非課税条件を満たしていれば均等割も0円になります。
収入や世帯状況によっては均等割も免除されるため、 98万円付近は「所得割も均等割も0円になるライン」として重要です。
住民税の金額は自治体ごとの均等割で変わる点に注意
「98万円なら住民税は一律で〇円」というわけではありません。 自治体が独自に設定する均等割額が違うため、最終的な住民税額にも差が出ます。
| 自治体例 | 均等割(市+県) |
|---|---|
| 東京都23区 | 5,000円前後 |
| 大阪市 | 5,000〜6,000円程度 |
| 地方都市の一例 | 4,000〜6,500円程度と幅がある |
均等割は市区町村と都道府県で別々に決めるため、 「同じ98万円」でも住民税額が異なる点は覚えておくと安心です。
Q14 給与所得控除改正後の「108万円前後」の住民税をざっくりシミュレーション
2025年の給与所得控除が「55万円 → 65万円」に引き上げられることで、 住民税がかからなくなるラインは98万円 → 108万円前後へと上がる可能性があります。 ここでは「108万円前後で住民税はどうなるの?」をシンプルにイメージできるように、 初心者向けにざっくりシミュレーションします。
108万円のときに住民税の所得割は発生するのか?
まず、改正後の控除額を使って「108万円」で計算するとどうなるかを整理します。
【108万円の場合の住民税計算(2025改正後)】
- 給与収入:108万円
- 給与所得控除:65万円(改正後)
- 基礎控除:43万円(住民税)
- 108万円 −(65万円+43万円)= 0円
改正後はちょうど108万円付近までは課税所得が0円となり、 所得割(税率のかかる住民税)はゼロ円になるケースが多くなります。 ただし、均等割の非課税条件は自治体によって微妙に基準が違うため、 情報が不足している自治体もあり、一部では108万円でも均等割が発生する可能性があります。
100万・110万あたりで「手取り感」がどう変わるかの目安
「100万円と110万円で、手取りはどう違うの?」という質問もよくあります。 ここでは住民税の影響だけに絞って、ざっくり比較します。
| 給与収入 | 住民税(所得割) | 均等割の可能性 | 手取りの感覚 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | ほぼ0円 | 非課税になる自治体も多い | 住民税はほぼかからず手取りは最大化 |
| 108万円 | 0円(改正後ライン) | 均等割は条件次第で発生も | 手取りはまだ高い水準 |
| 110万円 | わずかに発生し始める可能性 | 自治体により均等割も発生 | 手取りは微減だが急落ではない |
住民税は「発生するときは数千円単位でじわっと増える」ため、 手取りが急に大きく減るわけではありません。 ただ、扶養や社会保険ライン(106万・130万など)は別の仕組みなので、 年収を調整したい人は住民税のラインだけを見ないことも大切です。
Q15 住民税の給与所得控除計算をステップで確認【初心者向け】
「住民税ってどうやって計算しているの?」 そう聞かれると、多くの人は「会社が勝手にやってくれている」と答えると思います。 ですがざっくり4ステップで流れを知っておくだけで、 給与所得控除や非課税ラインのイメージが一気につかみやすくなります。
ステップ1:年間の給与収入を合計する
まずは1年間(1月〜12月)にもらった給与の合計を出します。 給料明細の「支給総額」や「総支給額」を月ごとに足したイメージです。
- 基本給+残業代+各種手当などの合計
- 賞与(ボーナス)も含めて「1年トータル」で見る
- 源泉徴収票の「支払金額」が、この年間の給与収入にあたる
ステップ2:給与所得控除額の早見表で「給与所得」を出す
次に、ステップ1で出した給与収入に対して、 国が決めている「給与所得控除の早見表(または計算式)」を使い、 実際に税金計算に使う「給与所得」を求めます。
イメージ:
給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得(住民税の土台になる所得)
この「給与所得」は、所得税と住民税で共通して使うベースの数字になります。
ステップ3:基礎控除などの所得控除を引いて「課税所得」を出す
続いて、給与所得から各種の「所得控除」を差し引きます。 代表的なのは次のような控除です。
- 基礎控除(住民税は43万円など)
- 社会保険料控除(健康保険・厚生年金など)
- 扶養控除・配偶者控除 など
計算の形はこうなります。
給与所得 − 所得控除の合計 = 課税所得
この課税所得に対して、次のステップで住民税の税率をかけていきます。
ステップ4:住民税の所得割・均等割をかけて税額を求める
最後に、ステップ3で求めた課税所得をもとに、住民税の金額を計算します。 住民税は大きく分けて次の2つで構成されています。
- 所得割:課税所得 × 約10%(市民税+県民税の合計)
- 均等割:一律いくら、という「基本料金」のような部分
最終的なイメージは、
住民税 = 所得割(パーセント部分)+ 均等割(定額部分)
この全体の流れを知っておくと、 「給与所得控除が増えると、どこで税金が減るのか」がとても見えやすくなります。
Q16 住民税は年末調整で返ってくる?よくある誤解と正しい理解
「年末調整でお金が返ってきた=住民税も安くなった?」 こう考える人はとても多いのですが、これは完全な誤解です。 年末調整はあくまで “所得税の精算” のための手続きで、 住民税は市区町村が翌年に独自計算する別の仕組みで動いています。 初心者向けに、できるだけシンプルに整理していきます。
年末調整で精算されるのは「所得税」だけという基本ルール
年末調整は、会社が1年間の所得税を正しく計算し直す作業のことです。 つまり、以下のように “所得税専用” の仕組みです。
- 源泉徴収で払いすぎていた → 還付される(返ってくる)
- 逆に足りなかった → 追加で徴収される
- 対象はあくまで所得税のみ
この時点では住民税には一切触れられません。 ここを勘違いしてしまうと「住民税も安くなったはずなのに…?」という混乱につながります。
住民税は市区町村があとから計算して通知する仕組み
住民税は翌年の6月に通知される税金で、 市区町村があなたの前年の所得データをもとに計算する仕組みです。 この計算は国税とは完全に独立して行われます。
📌 住民税の決まり方(会社員の場合)
・年末調整 → 所得税だけ精算
・翌年1~5月 → 市区町村が前年所得を集計
・6月 → 住民税決定通知書が会社(または本人)へ届く
・6月給与から天引きがスタート
このように、住民税は「後追い」で決まるため、 年末調整の結果が住民税に直接影響するわけではありません。
住民税を減らしたいなら「前年中の所得と控除のつけ方」がポイント
年末調整では住民税が動かないため、 住民税の金額を減らしたい場合は前年の12月までに何をしたかが重要になります。
- ふるさと納税(住民税控除の代表例)
- 医療費控除や社会保険料控除などの控除を正確に申告
- 副業の収入・必要経費の申告漏れに注意
- 収入を調整したい場合は12月までに見直す
住民税は「前年の所得がすべて」なので、 翌年になってから変えられる部分はほとんどありません。 まずは「いつの所得が翌年の住民税になるか」を押さえておくと安心です。
Q17 パート・アルバイト・学生・フリーランス別:住民税で気をつけたいポイント
住民税は「前年の所得」で決まるため、働き方が違えば注意すべきポイントも変わります。 パート・学生・副業会社員・フリーランスなど、立場ごとに“気をつけるライン”が異なるため、 ここではわかりやすく整理してお伝えします。 とくに「非課税ライン」「扶養」「給与所得控除の有無」が大きく関係してきます。
パート・アルバイト:住民税非課税ラインとシフト調整の考え方
パート・アルバイトの人が気をつけたいのは、 住民税の非課税ラインが「98万円 → 108万円(2025改正後)」になる可能性があるという点です。
- 98万円(現行):給与所得控除55万円+基礎控除43万円
- 108万円(2025以降):65万円+43万円の見込み
シフトを入れすぎて非課税ラインを越えると、 翌年6月から住民税が発生→手取りが一気に下がる というケースが多いため、 年末に向けて収入を調整する人が増えています。
学生バイト:親の扶養と住民税の両方を意識したいライン
学生の場合は、住民税よりも「親の扶養から外れるかどうか」が大きなポイントです。 2025年改正により「学生特例」は150万円までOKが維持される見込みですが、 住民税の非課税ライン(98万→108万)は別枠で存在します。
- 住民税の非課税ライン:98万 or 108万円
- 親の扶養のライン:学生は150万円までOK(勤労学生控除)
- 所得税ゼロのライン:給与所得控除+基礎控除で決まる
つまり学生は、 「扶養150万」+「住民税非課税ライン(98〜108万)」 の2つをセットで意識するとミスを防ぎやすくなります。
フリーランス+給与あり:給与所得控除がない所得とのバランス
給与とフリーランス収入の両方がある人は、 「給与所得控除」が使えるのは給与だけという点に注意が必要です。 事業所得には給与所得控除がないため、 住民税の課税所得が増えやすい構造になっています。
📌 給与+事業所得の人が気をつけること ・給与部分 → 給与所得控除が使える ・事業部分 → 必要経費を自分で積み上げるしかない ・結果的に所得が合算される=住民税が上がりやすい
副業フリーランスの人は、経費計上の漏れがあると住民税が一気に上がるため、 年間を通してレシート管理・帳簿管理をすることがとても重要です。
Q18 《まとめ》給与所得控除と住民税の反映・非課税ラインを総整理
ここまで「給与所得控除2025改正」と「住民税」の関係を細かく解説してきました。 働く人の多くが気にする非課税ラインや、反映される年度のズレなど、 わかりにくいポイントが一気に整理できるよう、最後に重要事項をまとめます。 これを押さえておけば、ムダな税金を払わずに済む判断がしやすくなります。
給与所得控除2025改正が住民税に反映される年とポイントをおさらい
給与所得控除が2025年に引き上げられても、 住民税が変わるのは1年後の「2026年度」からという点が最大のポイントです。 所得税は2025年分からすぐに変わるので、年度の違いに注意しましょう。
- 所得税:2025年1月〜12月の給与に適用
- 住民税:2026年6月から天引き額に反映
- ズレる理由:住民税は「前年の所得」で決まるから
98万円の壁から108万円の壁へ:住民税の非課税ラインの考え方
現行の非課税ラインは給与所得控除55万円+基礎控除43万円=98万円ですが、 2025年改正後は65万円+43万円=108万円になる見込みです。 これにより、パート主婦や学生アルバイトの “非課税で働ける幅” が広がります。
| 項目 | 現行(〜2024) | 2025改正後 |
|---|---|---|
| 給与所得控除 | 55万円 | 65万円 |
| 基礎控除(住民税) | 43万円 | 43万円(変更なし) |
| 非課税ライン | 98万円 | 108万円 |
パート・学生の方は「年収108万円以下なら翌年の住民税がゼロになる目安」と覚えておくと便利です。
給与所得控除と住民税の関係を理解して、ムダな税金を払わない工夫をしよう
給与所得控除は「税金を計算する前の大きな引き算」で、 住民税の金額に直接影響する重要な仕組みです。 反映される年度がズレることを理解しておけば、 「気づいたら住民税が高くなっていた…」といった失敗を避けられます。
- 住民税は翌年6月からスタートする“後追い型”の税金
- 非課税ラインは98万円 → 108万円(見込み)へ拡大
- パート主婦・学生バイトに有利な変更が多い
- 副業や複数収入がある場合は控除の使われ方に注意
- 年末までの収入管理と控除の使い方が住民税を左右する
ぜひ、働き方や収入計画を立てるときに今回のまとめを役立ててください。 正しく仕組みを知ることで、不要な税負担を避け、手取りを最大化できます。
▶ 給与所得控除と住民税まわりをもっと深く知りたい方へ
【2025年改正の全体像をつかみたい方はこちら】
- 【今すぐ確認!】給与所得控除2025改正はいつから?年末調整・扶養・住民税への影響まとめ 施行時期・103万円→123万円ライン・扶養や年末調整への影響をざっくり一望したい方向け。
【ケース別にもっと具体的に知りたい方はこちら】
- 【完全版】給与所得控除2025改正で変わる年末調整の書き方|源泉徴収票・控除申告書の新ルールを解説 人事・経理や副業勢など、「実際の書類の書き方」まで知りたいときに便利な実務ガイド。
- 【2025新ルール】給与所得控除と基礎控除の併用メリットと注意点 所得税・住民税の両方で効いてくる「基礎控除×給与所得控除」のダブル効果を整理したいときに。
- 【保存版】給与所得控除2025改正後の確定申告ガイド|複数勤務先・副業がある人の注意点給与所得控除と確定申告の関係を整理して手取りを最大化。複数収入のある方向け。

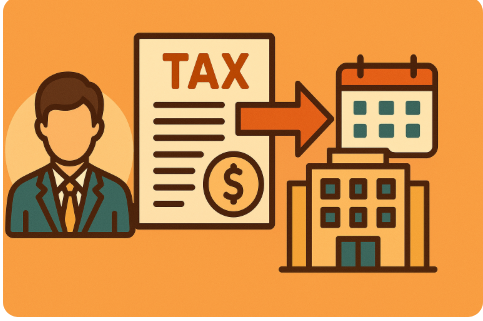


コメント