マイナンバーカードと運転免許証がついに1枚に――2025年3月、話題の「マイナ免許証」制度がスタートしました。
とはいえ、「便利そうだけど本当に切り替えるべき?」「そもそもメリットって何?」と、よくわからないまま様子見している人も多いのではないでしょうか。
確かに、制度の詳細は少し複雑で、判断に迷うポイントもあります。でも実は、講習のオンライン化・手続きの簡素化・費用の削減など、マイナ免許証には想像以上に多くのメリットがあるんです。
この記事では、初心者にもわかりやすく、マイナ免許証の“5大メリット”を徹底的に解説していきます。読めば、あなたにとって最適な選択肢がきっと見えてくるはずです!
マイナ免許証は身分証を1枚に集約可能
住所変更が市区町村だけで完結できる
講習がオンライン化され利便性が向上
更新費用が従来よりも大幅に安くなる
他県でも即日更新が可能で柔軟に対応
マイナ免許証の5大メリットをわかりやすく解説!

2025年3月、ついにスタートした「マイナ免許証制度」。これは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を可能にする画期的な仕組みです。この章では、特に初心者にもわかりやすく、5つの主なメリットを一つずつ解説していきます。まずは一番身近な「身分証明」の利便性から見ていきましょう。
①身分証明書が1枚に!マイナンバーと免許証の一体化メリット
✔ 1枚で二役!日常の身分証明がスムーズに
マイナ免許証は、マイナンバーカードと運転免許証の両機能を1枚に集約しています。これにより、これまで2枚持ち歩いていた人にとっては、持ち物の削減と管理の簡素化が実現されました。
- 市役所での手続き時にマイナンバーカードとして
- レンタカーや本人確認時に免許証として
- 病院や金融機関での本人確認も一枚で完結
カードを1枚にまとめることで、財布の中もスッキリし、日常的な身分証提示の場面での混乱を防げる点が多くの利用者に評価されています。
✔ マイナンバーとの紐づけで本人確認も簡単に
マイナ免許証では、マイナンバー制度との連携により、本人確認がこれまで以上に正確・迅速になります。特に公的機関や医療・福祉分野での活用が期待されており、次のようなメリットがあります:
- 本人確認書類としての信頼性向上
- ICチップ内の情報でなりすまし防止が可能
- 官公庁での手続きがデジタル連携で簡略化
たとえば、年金や保険の確認手続きの際も、1枚提示するだけでマイナンバーと運転資格の両方が証明されるため、手続きがスピーディーになります。
補足:現在(2025年3月26日時点)においても、マイナ免許証は任意取得制であり、切り替え義務はありません。従来通りの免許証とマイナンバーカードを別々に保持することも可能です。
②住所変更が楽に!市区町村だけで手続き完了

マイナ免許証を利用する最大のメリットのひとつが「住所変更手続きの簡略化」です。
これまで、引っ越しなどで住所が変わった場合、市区町村役場と警察署の2カ所で手続きを行う必要がありました。
しかし、マイナ免許証を「一体化のみ」で利用している人に限り、市区町村での届出だけで免許証の情報も更新されるようになりました。
📌 2カ所手続きが1カ所に減る理由とは?
従来の運転免許証とマイナンバーカードは別々に管理されていたため、住所変更時はそれぞれの所管窓口で個別に手続きが必要でした。
– マイナンバーカード:市区町村役場で変更手続き
– 運転免許証:警察署または運転免許センターで変更手続き
しかし、マイナ免許証(完全一体化)の場合は、運転免許情報がマイナンバーカードのICチップ内に格納されており、住所情報も連携される仕組みになっています。
| 免許証の形式 | 住所変更手続き先 | 手続き内容 |
|---|---|---|
| 従来の免許証 | 市区町村 + 警察署 | 両方で個別申請が必要 |
| マイナ免許証(一体型) | 市区町村のみ | 警察署での手続き不要 |
この制度により、引っ越し時の手続き負担が大幅に軽減され、「つい免許証の住所変更を忘れてしまう」という事態も防ぎやすくなります。
⚠ 2枚持ちだとワンストップにならないので注意
マイナ免許証と従来の免許証を2枚持ちしている場合、つまり「マイナンバーカードに免許情報を紐づけた上で、従来型の免許証も保持している」ケースでは、住所変更のワンストップ手続きが適用されません。
この場合は、以下のように市区町村と警察署の双方で届け出が必要になります:
- 市区町村:マイナンバーカードの住所変更
- 警察署:従来型運転免許証の住所変更
なぜなら、従来免許証は物理カードであり、券面に住所が印刷されているため、その内容を更新しなければ正しい身分証として使えないからです。
したがって、住所変更手続きを簡略化したい場合は、完全にマイナ免許証へ統合することが重要です。
注意:住所変更のワンストップが適用されるのは「マイナ免許証を単体利用している場合のみ」です。2枚持ちのままでは、警察署での手続きは依然として必要になります。
③講習がオンラインに!スマホで好きな時間に受講可能

2025年3月から開始されたマイナ免許証制度では、免許更新時の講習がオンラインで受けられるようになりました。特に仕事や育児で忙しい人にとっては「いつでも・どこでも」受けられるのは大きな魅力。ここでは対象者や費用、注意点などを詳しく解説します。
✅ 対象は優良・一般講習、講習料も安くなる
オンライン講習を受けられるのは、「優良講習」または「一般講習」の対象者です。
対象になるかどうかは、前回更新時からの違反歴などによって決まります。
| 講習区分 | オンライン対応 | 講習時間 | 講習手数料 |
|---|---|---|---|
| 優良講習(ゴールド) | ◯ 対応可 | 30分程度 | 200円 |
| 一般講習(ブルー) | ◯ 対応可 | 30分〜40分程度 | 200円 |
| 違反・初回講習 | × オンライン不可 | 2時間以上 | 1,400円前後 |
オンライン講習の魅力は、24時間いつでも自宅やカフェ、通勤中などに受講可能な点です。スマートフォンやパソコンがあれば特別なアプリは不要で、ウェブブラウザから視聴可能です。
また、対面講習よりも講習料が圧倒的に安く、優良・一般講習ともに一律200円で受けられる点も経済的メリットとなっています。
🔍 受講後の視力検査は免許センターで実施
オンライン講習を受けたからといって、すべての手続きが完了するわけではありません。
講習後には必ず、運転免許センターまたは警察署で「視力検査」や「顔写真撮影」が必要です。
- 免許証のICチップへの更新情報書き込み
- 顔写真の更新(必要な場合)
- 視力検査(運転適性の確認)
特に視力に不安がある人は、事前に眼鏡やコンタクトを準備しておくのがおすすめです。
また、視力検査をパスできなかった場合は更新保留や再検査となる可能性もあるため、軽視せずに臨む必要があります。
補足(2025年3月26日時点):
マイナ免許証を取得している場合のみ、オンライン講習の利用が可能です。
従来型の免許証のみ保持している人はオンライン受講対象外となります。講習対象者には、事前にマイナポータルや郵送での案内が届く仕組みになっています。
④更新手数料が安い!従来免許よりお得な理由

マイナ免許証への移行によって、運転免許証の更新にかかる手数料が引き下げられています。
加えて、オンライン講習の導入により講習料も大幅に低下。ここでは、更新時に実際に支払う費用がどのくらい変わるのか、従来型との比較も含めて詳細に解説します。
💰 更新手数料・講習費を合算するとどれくらい違う?
2025年3月時点の制度において、更新時にかかる費用は以下の2つに分類されます:
- 更新手数料(免許証の更新そのものにかかる費用)
- 講習手数料(区分に応じた法定講習費)
マイナ免許証への統合によって、更新手数料と講習費の両方が安くなるケースが多数あります。以下に具体的な金額を表でまとめました。
| 免許証の種別 | 更新手数料 | 講習手数料(優良/一般) | 合計費用 |
|---|---|---|---|
| マイナ免許証(完全統合) | 2,100円 | 200円(オンライン) | 2,300円 |
| 従来型免許証のみ | 2,850円 | 500円(優良)〜800円(一般) | 3,350〜3,650円 |
結果として、優良講習対象者であれば1,000円以上安くなる場合もあり、費用面のメリットは無視できません。
📊 2枚持ち・通常免許との費用比較
マイナ免許証は「完全統合型」と「2枚持ち(マイナンバーカード+従来型免許証)」の2パターンから選べますが、更新手数料には明確な差があります。
| 利用形態 | 更新手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| マイナ免許証(完全統合) | 2,100円 | カード1枚、最安 |
| 2枚持ち(統合+免許証も保持) | 2,950円 | 更新手続きは簡易化されるが割高 |
| 従来免許証のみ | 2,850円 | 講習も対面、住所変更も非効率 |
2枚持ちを選ぶと従来型より約100円高くなりますが、その分、マイナポータル連携や一部オンライン手続きの恩恵も受けられます。ただし、住所変更時に警察署での手続きも必要となるため、完全にワンストップで手続きしたいなら完全統合型が最もお得です。
補足(2025年3月26日時点):
これらの金額は警察庁・デジタル庁が公表している標準手数料に基づいており、各都道府県によって若干の違いがある可能性があります。また、講習区分によって受講可否や料金に変動があるため、最新情報は事前に公式サイト等で確認することを推奨します。
⑤他県でも即日更新!柔軟な更新制度に進化

これまで運転免許証の更新は「住所地を管轄する都道府県でしか手続きができない」「更新完了まで日数がかかる」という制約がありました。
しかし、2025年のマイナ免許証制度導入により、他県での免許更新が即日完了するなど、制度が大きく進化しました。特に引っ越しや転勤が多い人にとって、これは非常に実用的なメリットです。
🚗 経由更新でも即日交付、期間も最終日までOK
経由更新とは、本来の住所地とは異なる都道府県で免許更新の手続きを行うことを指します。従来は、経由更新の場合、その場で免許証を受け取れず、後日郵送されるなど、やや不便な対応となっていました。
ところが、マイナ免許証(統合型)を利用している場合、この経由更新でも即日交付が可能になります。以下は、従来制度とマイナ免許証制度の違いを表にまとめたものです。
| 制度 | 他県での更新 | 交付までの所要時間 |
|---|---|---|
| 従来の免許証 | 可能(制限あり) | 後日郵送(最大2週間) |
| マイナ免許証(統合型) | 可能(即日対応) | その場で即時交付 |
また、更新可能な期間についても改善されています。これまで「誕生日の1か月前から誕生日まで」という短い期間でしたが、現在は有効期限の最終日まで更新が可能です。これにより、急な出張や予定変更にも柔軟に対応できるようになりました。
🧳 転勤や引っ越しの多い人にぴったりの制度
マイナ免許証の柔軟な更新制度は、転勤族や大学進学・就職で県外に移動する人にとって非常に利便性が高い仕組みです。
- 一時的に住んでいる地域でも問題なく更新できる
- 本人確認がマイナンバーで一括管理されているため、書類準備が簡単
- 即日交付されるため、手続き当日から運転可
従来の制度では、他県での更新には多くの制約があり、更新のタイミングがズレたり、運転できない空白期間が発生したりすることもありました。しかしマイナ免許証なら、場所・期間・交付スピードの全てにおいて柔軟になっており、多忙な現代人のライフスタイルにフィットした運用が可能です。
補足(2025年3月26日時点):
経由更新による即日交付は、マイナ免許証(完全統合型)の利用者のみ対象です。2枚持ちや従来型免許証のみの人は、原則として即日交付は行われず、後日郵送になるケースがあります。更新場所が限られている都道府県もあるため、事前の確認が必要です。
マイナ免許証の注意点と2枚持ちとの違いもチェック!
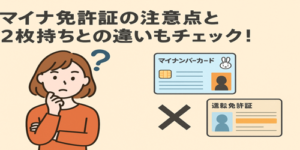
マイナ免許証の利便性が注目される一方で、「2枚持ち」による柔軟な選択肢も用意されています。
本セクションでは、マイナ免許証に完全統合する場合と、マイナンバーカードと運転免許証を別々に保持する「2枚持ち」のメリット・リスク・デジタル活用度の違いについて、実用面から詳しく比較します。
マイナ免許証と2枚持ちのメリットを比較
🧩 紛失時のリスク分散を考えると2枚持ちもアリ?
マイナ免許証(完全統合型)では、マイナンバーカードに運転免許の機能が内蔵されるため、1枚のカードが本人確認と運転資格の両方を担うことになります。これは管理が楽になる一方で、カード紛失時のリスクも一極集中する点に注意が必要です。
対して、2枚持ち(別々保持)には以下のようなメリットがあります:
- どちらかを紛失しても身分証明機能の一部は維持可能
- 再発行時のリスクが完全停止を防ぐ「冗長性」になる
- 用途別にカードの持ち運びを分けられる
特に高齢者やIT操作に不安がある層にとっては、従来どおりの免許証保持の安心感が重要視されるケースもあります。
📱 デジタル機能の恩恵を最大限に受けるには統合が有利
一方で、デジタル化の恩恵を最大限活かしたい場合は、マイナ免許証への完全統合が圧倒的に有利です。
統合によって得られる機能的なメリット:
- オンライン講習の利用(2枚持ちは対象外)
- マイナポータルと自動連携で住所変更や情報確認が簡単に
- 将来的なスマホ連携型デジタル免許証への対応可能性が高い
現在のところ、2枚持ちではマイナンバーカード側のICチップに免許情報が反映されていても、従来型免許証の保持により一部機能制限が生じるケースがあります(例:オンライン講習非対応、住所変更手続きの重複など)。
また、将来導入が検討されている「スマートフォン内での免許証提示」や「顔認証による本人確認」などの機能も、マイナ免許証への統合を前提に設計されていると見られ、今後の利便性拡張においても統合型が優位と考えられます。
補足(2025年3月26日現在):
マイナ免許証への統合は任意であり、2枚持ちも正式に認められています。ただし、手続きの重複・講習非対応など、中途半端なデジタル化による運用コストの発生もあるため、自身のライフスタイルに応じた選択が求められます。
マイナンバーカードで免許証を取得したらどうなる?

2025年3月現在、マイナンバーカードに運転免許証機能を統合する「マイナ免許証制度」が全国で本格導入されています。この制度では、マイナンバーカードを取得した後、希望者は運転免許証の情報をそのカードに統合することが可能となります。
ここでは、統合後の仕組みやカードの見た目、運用上の注意点について詳しく解説していきます。
💾 ICチップに免許情報が登録される仕組み
マイナンバーカードと免許証を一体化すると、運転免許証に関する情報はマイナンバーカードのICチップに内蔵される形となります。これは物理的にカード1枚で二つの役割を果たす画期的な仕組みです。
登録される主な免許情報は以下のとおりです:
- 免許証番号
- 有効期限
- 取得している運転区分(例:中型、準中型、二種など)
- 交通違反歴に基づく講習区分(優良・一般・違反)
この情報はカード表面には印字されず、ICチップ内に格納されており、読み取り機やスマートフォンアプリ(読み取り対応端末のみ)で確認が可能です。
セキュリティ保護の観点から、ICチップへのアクセスには暗証番号(マイナンバー利用者証明用パスワード等)が必要です。万が一カードを紛失しても、データの不正取得は困難とされており、安全性にも配慮されています。
⚠ 物理カードに免許情報が記載されない注意点
マイナ免許証(統合型)に切り替えると、カードの見た目は従来のマイナンバーカードのままになります。つまり、表面上には運転免許証としての記載(番号・区分・有効期限など)は一切表示されません。
この仕様によって発生する注意点は以下のとおりです:
- 警察の路上チェックやレンタカー受付で「免許証を提示してください」と言われた際に誤解されやすい
- ICチップ読み取り端末のない場所では免許保持者であることを即座に証明できない
- 公共機関や施設で「運転免許証が必要」とされている場面で拒否される可能性もゼロではない
そのため、デジタル前提の仕組みである一方で、利用環境によっては一部で不便が生じるリスクもあります。こうした事例に備えて、マイナポータルのアプリ画面を提示するか、従来の免許証を予備的に所持する「2枚持ち」を選ぶ人も少なくありません。
補足:2025年3月現在、警察庁・デジタル庁は「マイナ免許証単体でも法的に有効な運転免許証」として認めているとしていますが、現場対応や民間事業者の認識が追いついていない例も一部報告されています。「見た目に免許証と分からない」という仕様上の誤解には注意が必要です。
マイナ免許証のデメリットも押さえておこう
マイナ免許証は多くのメリットを備えた革新的な制度ですが、すべての人にとって万能とは言い切れません。
ここでは、特に見落としがちな実用面でのデメリットや制限事項について詳しく解説します。制度の全体像を正しく理解し、後悔のない選択をするためにも、デメリットの側面にも目を向けることが重要です。
📵 スマホで完全代用は不可/不携帯は依然として違反
マイナ免許証に切り替えても、スマートフォンでの完全な代用は現時点では不可能です(2025年3月現在)。
理由は以下の通りです:
- 運転中の提示義務は「物理カード」によってのみ満たされる
- スマホアプリはあくまでICチップ情報の閲覧補助であり、法的効力を持たない
- ICチップ内情報を読み取るには専用アプリ+マイナポータル連携が必要
つまり、たとえスマホに免許証の情報が表示されても、運転中に物理カードを持っていなければ「免許証不携帯違反」として処罰の対象になります。
補足:今後、スマホへの「運転免許証搭載」や「モバイル免許証」構想も検討されていますが、導入時期・仕様ともに未確定です。現段階では、マイナ免許証でも物理カードの携帯が絶対条件であることを忘れてはいけません。
🚫 一部のレンタカー業者では非対応の例も
マイナ免許証は法的には正式な運転免許証とされていますが、一部のレンタカー業者・カーシェアリングサービスではまだ非対応のケースが確認されています。
特に地方の小規模業者では、以下のような理由から対応が遅れている可能性があります:
- 免許情報をICチップから読み取る設備が未導入
- スタッフが制度自体を把握していない
- 券面記載のない免許証は本人確認書類として認めていない
実際、「マイナ免許証を提示したが、対応できずにレンタルを断られた」「別の本人確認書類を求められた」といった声もSNS上で散見されており、制度の周知と現場整備にはまだ課題が残っていると考えられます。
対応策:
・予約前に「マイナ免許証対応可否」を必ず確認
・場合によっては2枚持ちでの対応も検討する
・不安がある場合は従来型免許証のままにしておく選択も有効
マイナ免許証とスマホの連携でできること

マイナ免許証は物理カードとしての役割だけでなく、スマートフォンとの連携によって新たな活用法が広がりつつあります。ここでは、現時点(2025年3月)で可能なスマホ連携機能と、今後想定される「モバイル免許化」について詳しく解説します。
📱 読み取りアプリで自分の免許情報を確認
マイナ免許証は、スマートフォンのNFC機能(おサイフケータイ等)を使って、専用アプリでICチップ内の免許情報を読み取ることが可能です。
代表的な読み取り対応アプリ(2025年3月現在):
- マイナポータルアプリ(デジタル庁公式)
- JPKI利用者ソフト(ICチップの電子証明書確認)
- 運転免許証閲覧専用アプリ(一部自治体提供)
これらのアプリを使えば、自分の免許証番号・有効期限・運転区分などがいつでもスマホ上で確認できます。特に更新時期が近づいた際のセルフチェックや、情報に誤りがないかの確認に活用できます。
注意:読み取りにはNFC対応端末とICカード読み取り対応のスマホが必要です。iPhoneの場合はiOS 13以降、Androidは機種によって非対応の場合があるため、事前の確認が推奨されます。
🚀 将来的なモバイル免許化はどうなる?
「スマートフォン自体に免許証情報を格納し、提示・更新まで行える」という“モバイル免許証”構想は、現在デジタル庁と警察庁が共同で検討を進めている将来的な制度です。
2025年3月時点で明らかになっている情報(※推測を含みます):
- 2026年度を目標に限定的な実証実験が開始される可能性あり
- マイナンバーカードのスマホ搭載化(Android対応済/iPhoneは2025年度対応予定)と連動
- 法改正を伴う必要があるため全国展開には時間を要する
現状では、「スマホで免許証提示が可能になる=免許証の不携帯が解消される」わけではありません。法的な効力や本人確認手段としての信頼性確保のため、警察・民間事業者の現場での運用ルール策定が今後の課題です。
現時点での結論:
スマホで免許証を「確認」することはできても、「代用」することはできない。
将来的なモバイル免許証の正式導入までは、物理カードの所持は必須であることを理解しておく必要があります。
マイナ免許証の視力検査はどうなる?
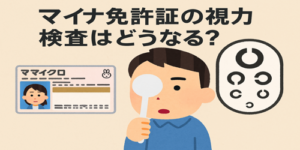
オンライン化が進むマイナ免許証制度ですが、すべての手続きがスマホだけで完結するわけではありません。その中でも重要なのが「視力検査」。運転適性の確認という観点から、現地での視力検査は依然として必須となっています。ここではその理由と、手続き上の注意点をわかりやすく解説します。
👁 講習だけでなく検査も必要な理由
マイナ免許証の更新では、オンライン講習を受けることが可能ですが、これは講義部分のみのデジタル化にとどまります。免許更新には講習に加えて、視力検査などの「身体的適性確認」が必須条件です。
視力検査が求められる背景には以下のような理由があります:
- 運転に必要な最低限の視力基準(片目0.3以上、両目0.7以上)が法律で定められている
- 病歴や矯正状態の変化が発見されることもある
- 本人が自覚していない視力の低下を客観的に確認する手段である
よって、どれだけ講習がオンラインで済んでも、視力検査をスキップすることはできません。視力が更新基準を下回っていた場合、更新手続きそのものが保留となる可能性があります。
⚖ オンラインと現地手続きのバランスに注意
マイナ免許証の更新は「オンライン+対面」のハイブリッド方式が基本となっています。
講習をオンラインで受講できても、視力検査や顔写真の撮影、ICチップ書き換えなどは指定の窓口(免許センター・警察署)での手続きが必要です。
具体的な流れは以下のようになります:
- マイナポータルなどでオンライン講習を受講
- 事前予約のうえ、免許センターまたは指定警察署へ来庁
- 現地で視力検査・顔写真撮影・ICチップ更新を実施
- その場で新しいマイナ免許証が交付される(即日または後日)
このように、オンライン講習が主流になったとはいえ、更新の完全非対面化は実現していないのが現状です。特に視力に不安がある人は、事前に眼鏡やコンタクトレンズを調整するなどの準備をおすすめします。
補足:
高齢者講習や違反講習の場合は、そもそもオンライン講習対象外となるため、すべての手続きが現地で行われます。対象区分を確認のうえ、手続き方法を選択しましょう。
(まとめ)マイナ免許証のメリットを最大限に活かすために
ここまで紹介してきたように、マイナ免許証はデジタル行政の進化を象徴する新制度であり、多くのメリットを持つ一方で、現時点では運用上の注意点も存在します。
制度のメリットをフルに享受するには、自分の生活スタイルやリスク許容度をふまえたうえで、賢く選択・活用していくことが大切です。
🎯 自分に合った運用方法を選ぶポイント
マイナ免許証を最大限活用するためには、「完全統合型にするか」「2枚持ちを選ぶか」といった選択肢ごとの違いを理解することが重要です。
以下の表に、それぞれの運用方法の特徴を簡単に整理しました:
| 選択肢 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 完全統合型(1枚) | 講習がオンライン対応、手続きが簡素化、住所変更がワンストップ | カード紛失時の影響が大きい、現場で認知されない可能性あり |
| 2枚持ち(マイナンバー+免許証) | 紛失リスク分散、旧来の利用方法に近く安心 | 講習がオンライン非対応、手続きが2段階になる |
どちらを選んでも法的には正規の免許証として有効ですが、利便性を最大化したいなら統合型を、慎重に運用したい人は2枚持ちを選ぶと良いでしょう。
📢 最新の制度アップデート情報をチェック
マイナ免許証はまだ始まったばかりの制度であり、今後も制度内容・対応範囲・対象者は変化していく可能性があります。
特に以下の情報は定期的に確認することをおすすめします:
- デジタル庁の公式発表(マイナポータルや公式SNS)
- 警察庁の運転免許制度に関する広報
- 自治体ごとの実施状況(都道府県によって対応窓口が異なる)
また、将来的にはスマホへの免許証搭載や、民間アプリとの連携拡大などが検討されています。
これらの動向をキャッチアップすることで、今後のアップデートに柔軟に対応できます。
現時点(2025年3月26日)では:
完全統合型マイナ免許証は全国で運用開始済ですが、スマホ搭載免許証は未対応。2026年以降に段階的な導入が検討されていると報じられています。

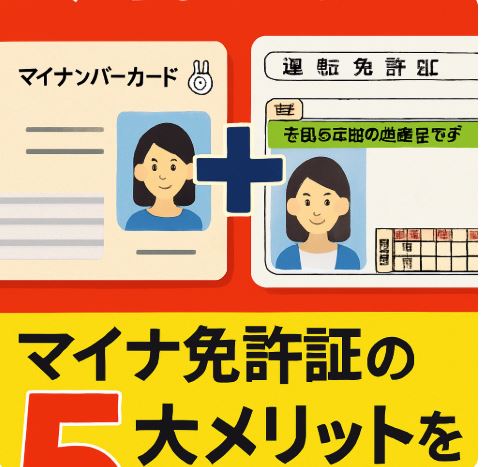


コメント