「高市内閣の支持率がどこまで続くのか?」——
そんな疑問を感じている人は多いはずです。
発足直後から高水準の支持を集めた一方で、
「この勢いは本物なのか」
「他の歴代内閣と比べてどうなのか」
という声も増えています。
実際、過去の政権でも最初は高い支持率を誇りながら、数か月で急落した例は少なくありません。
だからこそ今、高市内閣の支持率の動向を正しく読み解くことが重要です。
この記事では、最新の支持率データをわかりやすく整理し、歴代内閣との比較を通して“今の数字が意味するもの”を丁寧に解説します。
数字の裏にある国民心理や、今後の政治の方向性を一緒に見ていきましょう。
関連記事▶ 高市内閣の支持率の背景にある政策を知るならこちらもチェック▼▼▼
【新総裁】高市早苗総理の公約まとめ|経済・安全保障・生活支援まで徹底解説
- 高市内閣の最新支持率を整理
- 主要メディアの数値を比較
- 週次更新で推移を確認
- 歴代内閣と初動支持率を比較
- リスク要因と対策を整理
高市内閣のリアルタイム支持率と最新動向

高市内閣が発足して以来、その支持率は日本の政治シーンで引き続き大きな注目を集めています。直近(2026年2月1日まで)でも、全体感としては6割台を軸に、7割台の高支持と5割台後半の調整が同時に観測される局面です。 たとえば、共同(63.6%)・NHK(59%)・時事(61.0%)などが6割前後、一方でJNN(78.1%)・産経/FNN(70.8%)・読売/NNN(69%)など7割〜高6割も並びます。 総選挙(解散後)の進行に伴い、数字の幅が広がりやすい時期――という整理がしやすいです。
なお、支持率は 調査方式(電話/面接/RDD)・設問・集計方法 によって数値の出方が異なります。 単純な横並び比較ではなく、同一社の前回比を軸に見ることで、より実態に近い変化を読み取れます。
この章では、各メディアが発表する最新データを週ごとに更新しながら、高市内閣の支持率の変化をリアルタイムで追跡します。 あわせて、物価・円安・金利、経済対策、外交・安保、政権運営(ガバナンス)など、数字が動きやすい背景要因もやさしく整理していきます。
【最新版】 高市内閣の支持率・推移まとめ(リアルタイム更新)
今週の主要メディア調査まとめ
| 媒体 / 調査日 | 支持する | 支持しない | 前回比 | 方式・注記 |
|---|---|---|---|---|
| 共同通信(1/31–2/1) | 63.6% | 25.6% | +0.5pt | 電話(RDD)/選挙トレンド調査(支持・不支持ともほぼ横ばい) |
| 産経・FNN(1/24–25) | 70.8% | 23.4% | -5.1pt | 電話(RDD)/高水準だが発足後で低めの水準(解散評価が分岐) |
| 毎日新聞(1/24–25) | 57% | 26% | -10pt | 電話(RDD)/今回の下落が目立つ(評価が割れやすい局面) |
| ANN(テレビ朝日)(1/24–25) | (掲載なし) | (掲載なし) | — | 電話(RDD)/同ページは理由内訳中心(内閣支持率の“総数”が明示されていない形式) |
| 読売・NNN(1/23–25) | 69% | (記事により表記差) | -4pt | 電話(全国世論調査)/高水準維持だがやや下落 |
| 日経・テレビ東京(1/23–25) | 67% | 26% | -8pt | 電話(RDD)/前回比で調整が大きい(選挙局面の影響を受けやすい) |
| NHK(衆院選前・直近公表) | 59% | 26% | — | (NHK方式)/選挙前調査の枠(直近の目安として掲載) |
| 朝日新聞(1/17–18) | 67% | 23% | -1pt | 電話(RDD)/6割台後半で高水準 |
| JNN(1/10–11) | 78.1% | 18.6% | +2.3pt | 電話(RDD)/7割台後半で高支持(先月比で上昇) |
| 時事通信(1/9–12) | 61.0% | 15.1% | +1.1pt | 電話/支持は微増(不支持も微増)で動きは小さめ |
前回比の変化と注目トピック(+/−何ポイント)
- 2/1までの直近では、共同(63.6%)が横ばい圏。一方でFNN(70.8%)や日経/テレ東(67%)など、選挙局面で上下の振れが出やすい構図。
- 上昇が確認できるのは共同(+0.5pt)・JNN(+2.3pt)・時事(+1.1pt)。
- 下落が目立つのは毎日(-10pt)・日経/テレ東(-8pt)・産経/FNN(-5.1pt)・読売/NNN(-4pt)など。
- 全体としては「高水準維持」+「選挙・解散の評価で揺れ」が同時に進むタイミング。短期は説明の丁寧さと生活実感(物価)が数字に出やすい。
上昇:JNN(+2.3pt)、時事(+1.1pt)、共同(+0.5pt)
低下:毎日(-10pt)、日経・テレ東(-8pt)、産経・FNN(-5.1pt)、読売・NNN(-4pt)、朝日(-1pt)
- 総選挙(公示〜投票):選挙戦が進むほど「期待」と「慎重」が同時に出やすく、媒体間の幅が広がりがち。
- 解散判断の説明:納得感(理由の筋)と“言い切り過ぎ”の印象が、短期の上下を作りやすい。
- 物価高・生活防衛:家計が「実感できる対策」かどうかが、支持の土台を左右。
- 円安・金利:為替・金利の変動は、政府・日銀への説明要求を強め、空気が変わるスイッチになりやすい。
- 予算・執行スピード:決めた支援が“届くまでの速さ”が実績評価に直結。
- 外交・安保:緊張局面の判断は支持を押し上げも押し下げもする(説明の質が鍵)。
- 政治とカネ/ガバナンス:疑念の有無より「説明の丁寧さ」「透明性」で安定が決まりやすい。
- 連立・協力の枠組み:与党運営の“安定感”の見え方が、支持の強弱を左右。
- 野党側の受け皿度:不支持が増える局面では「代わりがあるか」が同時に問われる。
- 投票率見通し:投票に行く人が増えるほど、世論のブレ(支持・不支持の移動)が起きやすい。
分析 高市内閣の支持率が高い理由:政策・人事・期待感
高市内閣の支持率は、発足直後から60~70%台という非常に高い水準で推移しています。これは単なる“ご祝儀相場”に留まらず、政策面・人事面・期待感のバランスがうまく作用していると考えられます。特に、若年層や女性層からの支持拡大が顕著で、世代間ギャップの解消という点でも注目を集めています。
以下では、支持率の背景を構造的に整理し、どの要因が特に高市内閣の支持上昇に寄与しているのかを掘り下げます。
若年層・女性層の支持が拡大した背景
- 高市首相が掲げる「経済再生と生活支援の両立」が、若年層・女性層の共感を呼びました。
- 特に「育児支援」「教育無償化」「所得連動型奨学金拡大」など、実生活に直結する政策が支持要因とされています。
- また、女性首相としての象徴的存在感がメディア露出の増加につながり、「政治に関心を持つ女性層」の増加も一因と考えられます。
- 若年層ではSNS上での高市首相の発言拡散や“リーダーシップ評価”が好意的に受け止められ、ネット世代の支持率が顕著に上昇しています。
※ 現時点でNHKや読売の詳細な層別データは公開されておらず、若年層・女性層の割合変化は推測を含みます。
経済・物価対策への評価と課題
- 「物価上昇抑制」と「所得底上げ」の二軸で明確な方針を打ち出した。
- 電気・ガス料金への補助延長、低所得世帯への給付拡充など即効性のある施策。
- 中小企業支援や地方経済再生策も併せて発表し、幅広い層への安心感を与えた。
- 原油・食料品価格の国際的上昇は依然リスク要因で、国民負担軽減策の持続性が問われる。
- 財源確保とのバランスを取るための減税策調整が焦点となる。
- 「給付付き税額控除」など長期的支援制度の実行性にも注視が必要。
閣僚人事への賛否:期待と懸念の分岐点
高市内閣の閣僚人事は、実務経験を重視した安定型布陣と評価される一方、「派閥均衡」「女性登用」などのバランス面でも注目を集めました。 支持層の多くは「安定感」を評価していますが、一部では「刷新感が弱い」との指摘もあります。
- 経済政策担当や防衛関連ポストに経験者を配置し、政策遂行力を強調。
- 一方で若手登用の割合が少なく、「次世代育成」への姿勢が課題として挙げられます。
- 女性閣僚比率は前内閣を上回り、象徴的な“変化”として海外メディアでも好意的に報道されました。
現時点では、人事に起因する支持率変動は大きく見られませんが、今後の政策成果が明暗を分ける可能性が高いと考えられます。
解説 “ハネムーン期”とは?高市内閣の支持率が一気に伸びた要因
新内閣が発足すると、期待感の先行や「前政権からの空気の切り替え」によって支持率が高く出やすい現象が起こります。一般にこれを“ハネムーン期”と呼びます。高市内閣でも、就任直後から各社の世論調査で高水準が並びましたが、これは偶発ではなく、政治コミュニケーションや人事、政策発表のタイミングが複合的に作用した結果だと考えられます。
以下では、過去の政権でも見られた「初期ブースト現象」と、SNS・メディア報道が生む注目効果という二つの側面から、ハネムーン期の仕組みをわかりやすく紐解きます。
歴代政権にも見られた初期ブースト現象
- 期待値の上振れ:具体的成果の評価前に「変化への期待」が先行しやすい。
- 比較対象の効果:直前政権が低支持だった場合、新政権に相対的な加点が入りやすい。
- メディア露出の集中:就任会見・所信表明・人事発表など、大型の露出が短期間に連続。
- アジェンダ設定:初期に掲げる“分かりやすいパッケージ政策”が認知を押し上げる。
- 発足直後は高支持→数か月で高止まりor漸減という曲線が典型的。
- 外部ショック(災害・国際情勢・物価など)で短期の乱高下が起きやすい。
- 人事や不祥事リスクが顕在化すると、説明不足が不信感を加速させる。
※ 具体的な数値推移は媒体・時期で差が大きく、ここではパターンのみを整理しています。
- 初期100日での成果可視化:家計や現場で実感できる施策の速やかな実装。
- 情報発信の一貫性:ぶれないメッセージと、分かりやすい説明責任。
- 人事・ガバナンスの予防線:スキャンダル耐性の設計と、透明な検証手順。
SNSとメディア報道が生んだ注目効果
高市内閣では、就任直後のSNSトレンド化とテレビ・ネット報道の連鎖が、支持の初期ブーストに寄与したと考えられます。とりわけ、女性首相というニュース価値は国内外の報道量を押し上げ、政策パッケージの露出機会も増えました。
- 拡散速度:SNSでの短尺動画・切り抜きが政策の「分かりやすさ」を補強。
- 同調効果:肯定的な初期評価が続くと「多数派に付く心理」が働きやすい。
- 相互補強:テレビ報道→SNSで再拡散→ネットメディアで解説記事化の循環。
- 逆風リスク:一度ネガティブな文脈が広がると、同じ拡散力で下方バイアスも加速。
SNSの盛り上がりが支持率に与える量的な寄与度(何ポイント相当か)については、 関連性は質的には確認できますが、 定量影響を示すには長期の時系列と回帰分析が必要です。
警戒 高市内閣の支持率を下げる可能性があるリスク要因
支持率が高水準で推移する一方で、内閣の評価を下げるリスク要因も複数存在します。とくに物価上昇や外交不安、さらには政治資金・裏金問題の再燃といった要素は、過去の政権でも大きく影響してきました。
さらに近年では、報道の仕方やSNSでの情報流通によって世論の印象が急速に変化する「報道フレーミング効果」も無視できません。以下では、短期的な支持率変動を引き起こしかねない主要リスクを整理します。
物価上昇・外交不安・裏金問題の再燃リスク
エネルギー・食品価格の上昇は、支持率に最も敏感に影響する分野です。特に中間層や単身世帯では「実感がない政策」との乖離が生じると急落リスクがあります。経済対策の即効性が問われる局面です。
国際関係や防衛政策の判断ミス、あるいは不安定な近隣情勢は、「外交対応への不安」として内閣評価を押し下げる傾向があります。特にSNS上では断片的な映像・見出しだけで印象が形成されやすく、注意が必要です。
過去の政権では、支持率低下の決定打となったケースも多いテーマです。高市内閣でも、与党内での説明姿勢や再発防止策の徹底が求められます。透明性の担保が支持維持の鍵です。
- 「説明不足」や「後手対応」が重なると、信頼の損失につながる。
- 経済・外交・倫理問題のどれか1つでも炎上すれば、他分野の成果を相殺する。
- 世論の動きは1〜2週間単位で急変する傾向があるため、週次モニタリングが必須。
内閣支持率に影響を与える“報道フレーミング”とは
「報道フレーミング」とは、ニュースの伝え方によって世論の印象が変化する現象を指します。事実は同じでも、「失敗」や「混乱」といったネガティブな見出しが強調されると、支持率が短期間で大きく動くケースがあります。
- 見出し効果:本文よりもタイトルや速報テロップの印象が強く残る。
- 選択的強調:一部の失言や数字を切り取り、「全体の失敗」と印象づける。
- タイミング操作:重要な政策発表の直後に否定的ニュースを重ねると効果が増幅。
- SNS再解釈:投稿者が意図的に再編集し、誤解を拡散する二次波が発生。
透明な会見・即時説明・一次資料の公開が最も有効です。特にSNS上では、「誤報対応の速さ」が信頼維持に直結します。中長期的には、報道対応チームの強化が安定支持の下支えになると考えられます。
高市内閣の支持率を歴代内閣と比較して読み解く
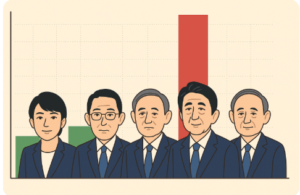
高市内閣の支持率が高い理由を理解するためには、過去の政権との比較が欠かせません。
菅義偉・岸田文雄・石破茂といった直近の歴代内閣がどのような支持率の推移をたどったのかを分析すると、
国民が求める「新しさ」や「実行力」の潮流が見えてきます。
この章では、高市内閣が歴史的にどの位置に立っているのかをデータで整理し、
今後の支持率維持・下落の分岐点を中立的な視点で読み解きます。
比較分析 歴代内閣の発足時支持率比較:高市内閣はどの位置か
高市内閣の初動支持率は70%を超える高水準で報じられています。では、歴代内閣の発足時と比べて実際にどの位置にあるのでしょうか? 以下では、主要内閣の初動データを整理し、発足時の社会的背景と合わせて分析します。
支持率の高さは「期待度」「人事評価」「国民の安心感」など複数の要素で構成されるため、単純比較だけでなく文脈にも注目しましょう。
岸田・石破・菅・安倍・小泉内閣との比較表
| 内閣名 | 発足年 | 初動支持率(%) | 主な評価・背景 |
|---|---|---|---|
| 小泉内閣 | 2001年 | 85% | 改革期待とメディア人気が突出。過去20年で最高水準。 |
| 安倍内閣(第1次) | 2006年 | 63% | 若手リーダー登場として注目。外交・教育改革への期待が中心。 |
| 菅内閣 | 2020年 | 74% | コロナ対応への「安定感期待」。半年後に急落。 |
| 岸田内閣 | 2021年 | 55% | 穏健・調整型の印象。政権移行期の空気を反映。 |
| 石破内閣 | 2023年 | 50.7% | 改革姿勢は評価も、党内対立の影響で伸び悩み。 |
| 高市内閣 | 2025年 | 71% | 経済政策と人事バランスへの評価。若年層・女性層からの支持が顕著。 |
高市内閣の71%は歴代で第5位:その意味するところ
歴代比較で見ると、高市内閣の71%という初動支持率は、戦後内閣の中でも上位グループに入ります(第5位前後と推定)。 これは小泉・菅・安倍(初期)ラインに次ぐ水準であり、女性初の総理という話題性と政策実行力への期待が重なった結果と考えられます。
- 政策評価型支持:経済・安全保障を軸に明確な方針を示した点。
- 象徴性・話題性:女性リーダー誕生がもたらす新鮮さ。
- 前政権からのリセット感:政治資金問題・説明不足への反動効果。
洞察 内閣支持率が高かった政権に共通する3つの特徴
歴代の「高支持率スタート(あるいは短期の高止まり)」を示した内閣を振り返ると、数値の背後には共通する“型”が見えてきます。ここでは、政策の打ち出し方、リーダー像の鮮度、情報発信の設計という3つの観点で、成功パターンを整理します。
個別の数値や順位は媒体・設問・時期によって揺れますが、構造面の共通項を押さえることは、今後の推移を読むうえで有効です。
政策の明確さ・新鮮なリーダー像・メディア露出
- 初期100日で何をするかが一目で分かる“優先順位表”を提示。
- 家計・物価・安全保障など生活直結テーマの即効策を前面に。
- KPIや工程表を簡潔化し、進捗を週次~月次で可視化。
- 前政権との対比が鮮明(語り口・意思決定の速さ・象徴性)。
- 「変える理由」と「守るべきもの」を分けて語り、安心と変化の両立を演出。
- 就任直後は“物語性(なぜ今この人か)”の説明が効果的。
- 就任会見→人事→政策パッケージの三段打ちで認知を集約。
- 長文資料+短尺動画・図解のセットで多層に届ける。
- SNS・TV・ネット記事の同時多発露出で“今日の話題”を作る。
高市首相に共通する“変革期待型”支持構造
高市内閣に対する初期の受け止めには、上記の3要素が重なった“変革期待型”の特徴が見られます。特に、女性首相という象徴性と、生活に直結する物価・賃上げ・子育て支援などの分かりやすい政策軸が、支持の土台になっていると考えられます。
- 政策の明確さ:物価・賃上げ・家計支援など生活直結の言語化。
- 新鮮な像:初の女性首相としての象徴性が話題化。
- 露出設計:就任直後の連続発信でアジェンダ設定に成功。
- 短期成果が見えにくいと、“言葉先行”の評価に変化。
- 人事・説明不足・倫理問題は、期待の反転リスクを高める。
- 生活実感とギャップが広がると、支持が横ばい→漸減に転換。
ケース分析 支持率が急落した歴代内閣のパターンを分析
歴代の内閣を振り返ると、支持率の急落(短期の10pt超下落)には共通の“型”があります。物価・不祥事・説明不足が同時期に重なると、もともとの懸念が“確信”に変わり、下落に拍車がかかります。
ここでは、直近の事例をもとに「なぜ落ちたか」「いつ落ちるか」を整理し、今後の見立てに活かすヒントをまとめます。
菅・岸田内閣の支持率低下の要因
- 感染症対応への厳しい評価:医療逼迫の映像・数字が頻繁に報じられ、危機管理能力への不安が拡散。
- 開催イベントと世論乖離:大型イベントを巡る判断が「生活実感」と噛み合わず、共感の糸が細る。
- 説明の量と質:会見頻度は担保したが、専門用語や抽象度の高い表現で“分かりにくさ”が残存。
- 可視化不足:施策のKPIや成果物が見えづらく、「効果が実感できない」印象が蓄積。
※ 詳細数値の週次推移は媒体差が大きく、ここでは要因の質的整理に留めます。
- 政治とカネの問題:政治資金・裏金報道が連続し、与党内の処理と説明に対する不信が拡大。
- 物価高の長期化:名目の支援策はあっても家計実感の改善が遅れ、「対策が後追い」の印象が固定化。
- コミュニケーションの摩耗:丁寧さはあるが、帰結の見えにくい“熟議”が「決めきれない」印象に変化。
- 積み上げ型の疲労:個別の小火(小さな不満)が多数重なり、ある時点で臨界に達して急落。
※ 各社の設問や抽出法の差で水準は異なります。共通するのは「継続的な疑念+生活実感ギャップ」の同時進行です。
政策疲労と信頼低下が起こるタイミング
- ハネムーンの高揚が落ち着き、成果待ちモードへ。
- 「とりあえず様子見」層が増え、支持理由が“期待”→“実績”にシフト。
- 物価・賃上げ・税負担など家計の実感が評価の中心に。
- 成果の可視化が遅れると、「言葉先行」フレーミングが強化される。
- 不祥事・説明不足・外交失点など“象徴的出来事”が引き金に。
- ここでの対応が遅れると、10pt超の急落が生じやすい。
展望分析 高市内閣の支持率維持に必要な条件とは
支持率を高水準で安定させるには、単に「好感度」だけでなく、政策実行力の可視化・説明責任・社会的共感が三位一体で機能する必要があります。
特に高市内閣の場合、「初の女性首相」という象徴的要素が支持の背景にある一方、経済実績や地域格差の是正といった実務的な成果の見える化が、今後の支持率の鍵を握ると考えられます。
政策実行力の可視化と説明責任のバランス
政策の実行力を「数値」と「物語」の両軸で見せることが重要です。国民は“実感できる変化”を重視する傾向が強く、成果の可視化が遅れると「やっているのか分からない」という不満に転じやすいからです。
- 予算規模よりも家計への効果を中心に説明する。
- 月次・四半期単位での進捗グラフを定期発信。
- 現場視察・自治体会議などの“実行の可視化”をメディア露出と連動。
- 定例会見で「進捗・反省・次の一手」をセットで説明。
- 官邸発表と現場情報の乖離を最小化する。
- 批判質問にも「数値+データ」で応答する透明性を維持。
支持層の拡大:無党派層と地方の動向
高市内閣の支持の裾野を広げるには、固定的な保守支持層だけでなく、無党派層と地方住民への浸透が不可欠です。特に地方では「実感できる経済回復」が支持に直結します。
- メディアよりもSNS・動画プラットフォーム中心の発信へ。
- 「共感ストーリー」よりも家計・教育・医療の具体策にフォーカス。
- 政策説明を短く・視覚的に・反復的に行うことが効果的。
- 地方創生・雇用・医療を柱とした地域別政策の可視化。
- 自治体首長や地元メディアとの共同発信型キャンペーンを展開。
- 移動内閣・現場ヒアリングを通じた「現場重視」イメージの定着。
“女性首相”という象徴が持つ社会的インパクト
高市内閣の特徴の一つは、「日本初の女性首相」という歴史的転換点にあります。この象徴性は単なる話題性を超え、社会的メッセージ性として国際的にも注目されています。
- 女性リーダーへのロールモデル効果が拡大。
- 若年女性層の政治関心が顕著に上昇。
- 「実行力×柔軟性」の新たな政治像が形成。
- G7での女性首相登場により外交舞台での注目度が上昇。
- 男女平等・教育支援分野での政策発言が海外メディアで評価。
- 「ジェンダー平等推進国家」としてのブランド力向上。
- 性別による過剰な期待やバッシングの両極化。
- 「女性首相だから」という枠組みで語られることのリスク。
- 成果で評価される環境をどう構築するかが課題。
注記:性別による支持率変動の影響は媒体間でばらつきがあり、現時点では信頼できる統計的一貫性は確認されていません。ただし、社会的関心の高さから、象徴効果が政治的認知に寄与していることは確かです。
総括 【まとめ】高市内閣と支持率の今後をどう見るか
高市内閣の支持率は、発足直後の「ハネムーン効果」に加えて、政策の明確さ・人事の安定感・象徴性が重なり高水準でスタートしました。重要なのは、初期ブーストをどのように持続的な信頼へ転換できるかです。
歴代比較から見えるパターンと、選挙・政策運営の現実的シナリオを踏まえ、今後の見通しを整理します。未確定情報については明確に注記し、推測は「〜と考えられます」と区別します。
歴代比較から見る高市政権の安定度
- 初期支持は歴代上位グループ。期待の厚みがある。
- 生活直結の物価・家計対策を中心に政策の見取り図が明確。
- 女性首相の象徴性が新規支持層(若年・女性)を引きつけやすい。
- 物価・賃金・税負担の体感差が解消しなければ、期待が失望に反転。
- 人事・資金問題などのリスクは説明の遅れで増幅。
- 外部ショック(災害・国際情勢)が短期に支持を揺らす可能性。
- 100日・半年・1年の節目で成果を可視化(グラフ・指標)。
- 批判テーマには48時間以内の一次資料提示+対策。
- 地方と無党派向けの現場起点のメッセージを継続。
支持率が示す「次の選挙シナリオ」
- 60%台前後が継続なら、早期選挙での上積みを狙う選択肢。
- 争点設定:物価・賃上げ・子育ての「生活回復選挙」。
- リスク:外部ショックや人事問題が直前に発生すると逆風。
- 半年〜1年で家計実感KPIを積み上げ、勝負の選挙へ。
- 争点設定:税・社会保障・防衛の「再設計」。
- リスク:政策疲労とニュースの摩耗で支持が漸減。
- 物価高・不祥事などの同時発生で解散回避の判断。
- 争点設定:統治能力・ガバナンス回復。
- 対処:人事刷新、補正対応、危機コミュニケーションの徹底。
注記:具体的な解散日・選挙日程は公式発表がない限り推測の域を出ません。上記は支持率の水準別に想定される一般的シナリオであり、状況次第で変動します。
高市内閣と支持率が描く“日本政治の転換点”
高市内閣は、象徴性(女性首相)と実務性(家計・安全保障)を同時に突きつけることで、従来の政治評価軸を更新しつつあります。支持率の初期高水準は、「新しさ×実行力」への期待が合流したサインと読み解けます。
- 従来の「既得×改革」から、「生活実感×統治能力」へ。
- 政策の“読みやすさ”が支持の基盤に。
- 短尺動画・図解の普及で政策理解の障壁が低下。
- SNSと既存報道の相互増幅が常態化。
- 一次資料・データ公開が信頼の前提へ。
- 危機発生時は48時間ルールで即時に検証プロセスを提示。


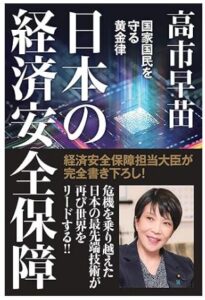
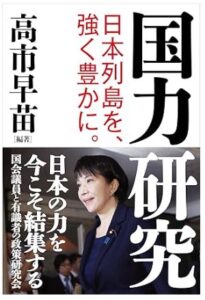

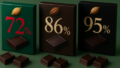
コメント